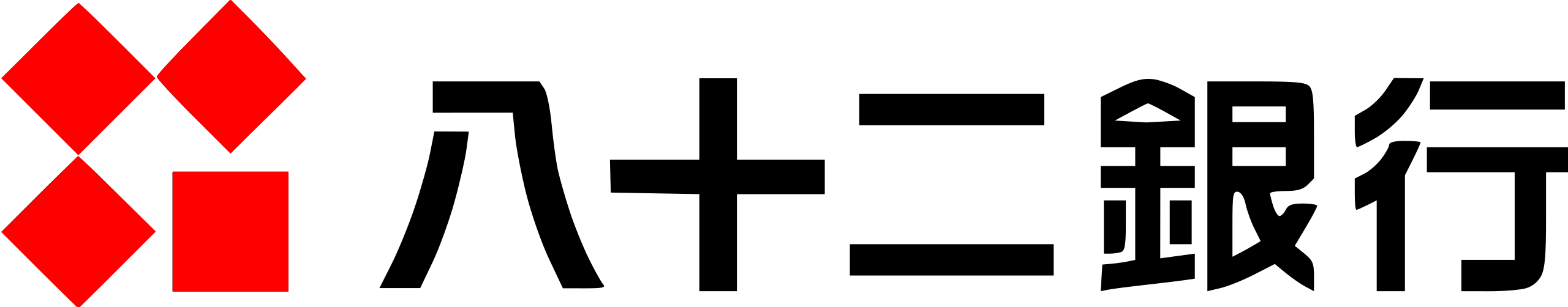概要
長野県に本社を置く八十二銀行は、豊かな長野の自然環境を守るため、長年にわたりサステナビリティ経営に力を入れてきました。ISO14001の認証取得や環境会計の導入など、環境意識の高さは職員一人一人に浸透しています。2021年からはサステナビリティを経営の根幹に据え、企画部内に専門部署「サステナビリティ統括室」を設置。国内銀行で初めてCDPの最高評価を獲得するなど、情報開示にも積極的に取り組んでいます。
今回、さらなるサステナビリティ経営の促進に向けた、脱炭素の取り組みとしてオフセットの実行を検討するにあたり、地域脱炭素推進コンソーシアムで、カーボンクレジットを軸とした地域脱炭素の推進に向けて協働していることを契機に、国内外のカーボンクレジット・証書の調達をバイウィルがご支援しました。
ご提供サービス
オフセット計画・設計のアドバイス
J-クレジット・VCS(*)認証の海外クレジットの調達支援
*VCSとは:「Verified Carbon Standard(認証カーボン基準)」の略で、国際的に最も広く使われているカーボンクレジットの認証制度のひとつ。第三者機関による厳格な審査を通じて、クレジットの信頼性が保証されています。
地域金融機関だからこそ地域貢献を第一に。環境経営の取り組みで地域経済を支え、長野県の発展を支え続ける
── まずは、八十二銀行様の事業特徴について教えてください。
神津様:自然豊かな長野県を地盤とする地域金融機関である八十二銀行は、県内で130を超える拠点を展開するリーディングカンパニーとしての役割を担っています。これまでも地元企業の脱炭素化や環境保全、海外展開支援、IT・DX支援等さまざまな面で先進的なチャレンジをお客様と共に続けてきました。
長野県といえば、豊かな自然が大きな特色で、観光や農業など自然を活かした産業も多くあります。だからこそ、八十二銀行はこれまで環境について意欲的に取り組んできました。地球温暖化対策や環境保全にしっかり取り組んでいくことは、地域の発展にもつながります。

── サステナビリティ経営を重要視され、様々な取り組みをされているとお聞きしましたが、具体的な取り組みとその背景について教えてください。
山浦様:八十二銀行は、サステナビリティやESGという言葉が一般的になる前から、環境経営に力を入れてきた銀行だと自負しています。いくつか取り組みをご紹介すると、1991年に銀行界で初めて、「古紙の回収・再生・利用」の一環システムを構築しました。その後の1999年には、地方銀行で初めて環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001認証」を取得しました。具体的な目標を定めグループ全体の環境保全活動の管理を徹底し、組織的に環境意識を高めてきました。
2005年には環境会計を導入し、環境保全活動にかかるコストとそれによる経済効果、環境保全効果を定量的に把握しています。
2009年から続けている「八十二の森」と名付けた森林保全活動も、職員が環境への貢献・行動を身近に感じられる機会になっています。目の前の森を整備する中で、自然と環境に対する意識が高まっていると感じています。
最近では、2023年、国際的な評価機関CDPの最高評価であるAリストに国内銀行で初めて選定されました。また翌年2024年も連続してAリスト入りしており、気候変動対策や情報開示に積極的に取り組んでいることが評価されています。
バイウィルさんとの地域脱炭素推進コンソーシアムもその取り組みの1つです。当行は当初からこのコンソーシアムに参画していますが、地域の脱炭素化を共に推進するなかで、今回のクレジット調達やオフセットの協力関係も始まりました。
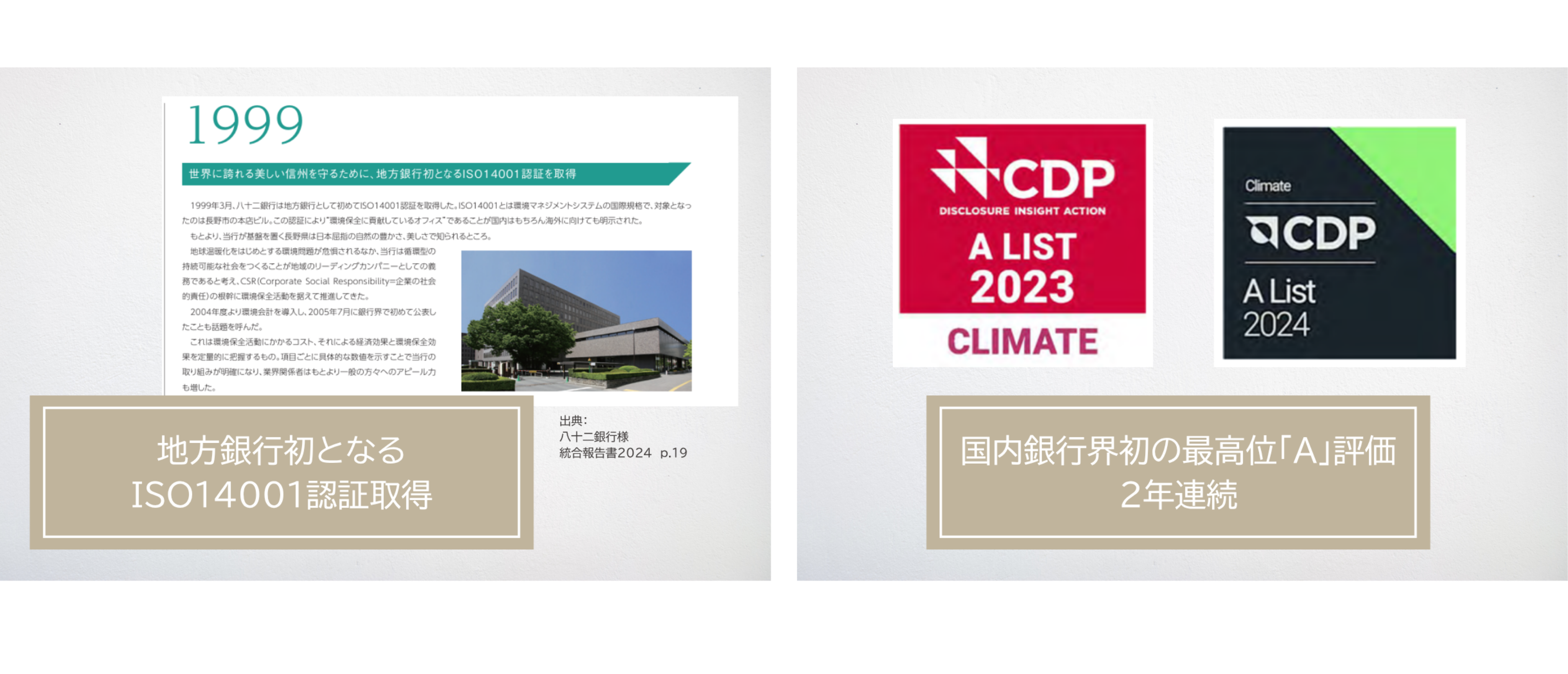
環境経営における長期的な目標だけではなく、短期的にも実行可能な目標を設定し、できることを明確化し、職員の行動を促進させる
── 八十二銀行様では、サステナビリティ経営の実践として、すでにScope1・2のネットゼロを達成していらっしゃいますが、早期に達成できた背景や、効果的な取り組みは何だったのでしょうか?
神津様:環境分野で先進的な銀行であり続けるという強い意識のもとネットゼロへのコミット自体が対外的な強いメッセージになると感じていました。また、地域の脱炭素化のためには、銀行の取引先企業であるお客様にも脱炭素化に取り組んでいただくことが大切ですので、まずは自分たちから行動することでより説得力が増すと考えています。
山浦様:2021年に策定した「中期経営ビジョン2021」において、サステナビリティを経営の根幹に据え、環境関連目標も設定したことで、銀行全体として脱炭素や地域との共創を強く意識した方針が今まで以上に明確になったことが大きかったと思います。
そして、その翌年2022年には自行のScope1・2の温室効果ガス排出量実質ゼロ、いわゆるネットゼロを達成しました。
達成のベースとなったのは省エネです。LED化、空調温度の厳格管理などの省エネ対策や、2021年度の岩村田支店を皮切りに、2022年度には富士見支店、大町支店、福島支店もZEBの最高ランクである『ZEB』(カギゼブ)店舗として新築しました。それらに加えて、再生可能エネルギーへの切り替えも大規模に進めており、2022年度から八十二銀行で使用する電力は全量実質再生可能エネルギー化しています。
 企画部(サステナビリティ統括室)主席役 山浦 雄一郎様
企画部(サステナビリティ統括室)主席役 山浦 雄一郎様
── Scope1・2のネットゼロに続き、八十二銀行様では中期経営目標の中で「お客様の排出量の見える化」にも取り組まれていますが、どのような背景や狙いがあるのでしょうか?
山浦様:Scope1・2については、削減の道筋が見えてきましたが、Scope3、特にカテゴリ15である「投融資先の排出量」については、以前から具体的な対応を始める必要があると考えていました。
2050年ネットゼロといった長期目標は、抽象的で現場レベルでは動きづらい面もあります。そこで、職員一人ひとりが日々の業務の中で行動に移せるように、中期経営目標の中で「融資先450社の排出量を把握する」という、Scope3への対応を目的とした具体的かつ実行可能な目標を掲げました。
営業店では、お客様に「まずは排出量を把握してみませんか」と声をかけるところから始めています。すでに算定に取り組んでいる企業には、次のステップとして削減のご提案を行うこともありますし、初めての企業には、外部サービスの紹介なども含めた支援を行っています。
排出量の把握は、削減に向けた最初のステップです。多くの中小企業のお客さまにとっては脱炭素の取組はやや遠い存在に思えるかもしれませんが、現状を知ることができれば、確実に次のアクションにつながると思っており、その環境を整えていくことが、地域金融機関としての私たちの役割だと考えています。
自助努力による削減に加え、クレジットや証書も効果的に活用しながら、Scope1・2のネットゼロ達成
── Scope1・2のネットゼロに向けて、削減だけでなくオフセットにも取り組まれてきたと伺いました。その背景や考え方について教えてください。
神津様:Scope1・2のネットゼロを目指す中で、Scope1をScope2に振替える、つまり電化が有力な手段となります。ただし、電化には設備投資が伴うため、どうしても長期スパンとなってしまいます。電化を進めつつも、短期的にはクレジットの購入によって相殺するという考え方を取りました。
再生可能エネルギーの導入も継続して進めています。銀行業ではScope2(ロケーション基準)の排出量が全体の大半を占めるため、再エネ化は重要です。昨年からオフサイトPPAを活用し、現在は3ヶ所の再エネ発電所が稼働していますが、こうした取り組みは、実際に太陽光を置くわけですから、相応の時間を要し、短期で成果が見えるものではありませんでした
そこで、「まずは、すぐにできることから着手しよう」という考えのもと、電力会社の再エネメニューへの切り替えや、非化石証書の購入による使用電力全量の実質再エネ化を実施しました。また、Scope1の相殺としてJ-クレジット(森林由来等)や海外のVCSクレジットも組み合わせたオフセットに取り組んでいます。
今後Scope3である取引先の排出量への取り組みも求められる中で、まずは自社が率先して動くことが、地域経済にとっても良い影響を生むと考えています。引き続き、一つひとつ地道に積み上げていきたいと思っています。
 総務部調査役 神津 喜英様
総務部調査役 神津 喜英様
── 今回のクレジット調達にあたって、バイウィルがご支援させていただきましたが、取引の中で感じたことなどございましたら、教えてください。
神津様:元々バイウィルさんとは、地域脱炭素推進コンソーシアムでご一緒させていただいており、地域の脱炭素化という共通の目標があります。カーボンクレジットは、一定の知識がないと、適切な比較や判断がやや難しい分野と感じていますが 、コンソーシアムを通じてバイウィルさんの豊富な知見を承知しておりましたので、信頼できる取引だったと感じています。
自社の「より精緻なネットゼロ」の実現を目指すとともに、金融機関として地域の脱炭素化を支援、地域産業のGXを後押しする存在へ
── 今後、カーボンニュートラル達成に向けて特に力を入れていきたい取り組みは何ですか?
神津様:現時点ではScope1・2のネットゼロは達成しましたが、今後は「より精緻なネットゼロ」を目指していきたいと考えています。単にクレジットを購入して終わりではなく、残余排出量の削減にも取り組む必要があります。省エネや業務プロセスの見直しなど、着実な削減努力を重ねていき、クレジットの購入の際には、信頼性の高いものを選定していきます。
山浦様:地域の脱炭素化や地域産業のGX化 を金融機関としてどう支援できるかも、今後の大きなテーマです。観光業にとっては自然資本の保全が必要不可欠であり、製造業では国際競争力を高めるための排出量削減が求められています。そのような地域の産業構造をふまえ、GXを後押しする存在でありたいと考えています。
この分野は制度や社会的要請の変化が早く、前例のないテーマも多くありますが、官公庁や専門企業と連携しながら、自らも挑戦し、経験を重ねることで実践知を蓄積していきたいと思っています。地域やお客さまの脱炭素化などをともに進める存在として、これからも実効性のあるアクションを積み重ねていきたいと思います。
───本日はありがとうございました。
(掲載されている所属、役職およびインタビュー内容などは取材当時のものです)