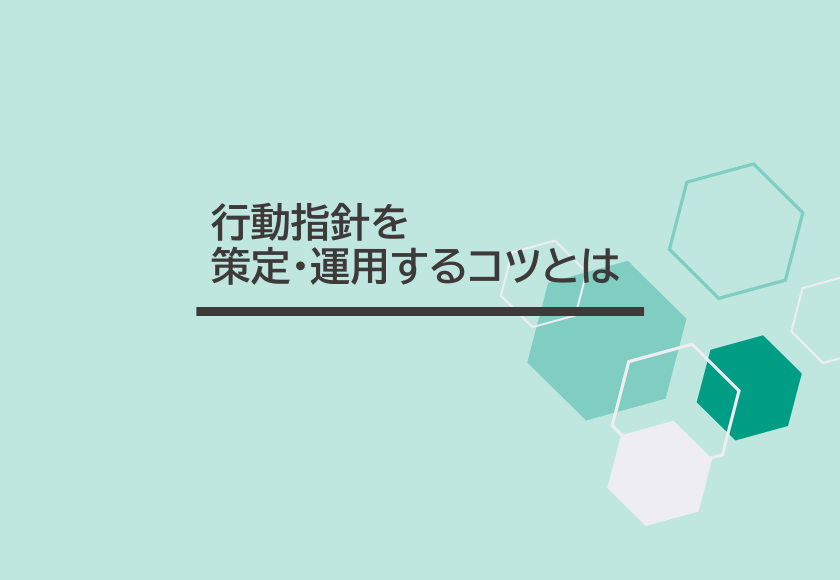さて、前回はインナーブランディングにおける「行動指針」が大まかにどのようなものなのか、その役割は何なのかをご説明致しました。おさらいすると、行動指針とは「ブランドコンセプトや企業理念といった抽象的かつ上位な概念を、各社員の具体的な末端業務まで浸透・反映させるための道しるべ」でしたね。(詳細は前回コラムをご参照ください)
今回は、上記のような役割を果たす行動指針を策定し、運用する際のポイントについてお話します。まずは、行動指針策定に際してのポイントについてです。策定方法の概要は以下です。順を追ってご説明させていただきます。
Step1 自社ブランドの「価値」「強み」「課題」を洗い出す
Step2 洗い出された要素を検証・集約する
Step3 適切な抽象度で言語化する
Step1 自社ブランドの「価値」「強み」「課題」を洗い出す
まず初めに、自社ブランドが提供している「価値」を再確認します。コンセプトワードなどの抽象的なレベルのものはもちろんですが、顧客に提供しているベネフィットレベルの要素もここに入るでしょう。例)「快適な居心地」「いつでもハイレベルな味のコーヒー」
「強み」には、自社ブランドの提供価値を発揮するために日々の業務で大事にしていること、今後も守り続けるべき社内基準などが入ります。例)「お客様との適切な距離感」「商品知識を増やすことを怠らない」
対して「弱み」にあたる「課題」には、実際の業務上の葛藤や今後、強化しなくてはならない社内基準などが入ります。例)「お客様が馴れ馴れしいと感じるかもしれない」
以上三つの観点を基に要素を洗い出すのですが、このステップにおける最大のポイントは「現場の声を起点に洗い出しを行うこと」です。というのも、全社の声を適切に吸い上げて策定することで社員一人一人のモチベーションが向上しやすく、逆に現場の声を考慮せずに策定すると的外れな内容になりやすいからです。
Step2 洗い出された要素を検証・集約する
ここでは、最初のステップで洗い出した大量の要素を削除・統合する作業を行います。ここで重要となる観点は以下の3つです。
- 「インパクト」
その要素がブランドへ与えるプラスのインパクトの大きさはどうか。また、どのようにブランド・社内が変わるかイメージできるかどうか。 - 「部署横断の運用可能性」
その要素は特定の部署のみに作用するものではないか。逆に特定の部署に作用しないものではないか。 - 「自社ブランドへの最適性」
他社には当てはまらない、自社特有の要素であるか。
このステップには大きな労力が必要となりますが、最終的に出来上がる行動指針の成否を大きく左右する部分になりますので、1つ1つの要素をしっかり吟味し、整理していくことが大切です。
Step3 適切な抽象度で言語化する
行動指針策定の最後のステップとして、削除・統合された要素を適切に言語化する作業が必要となります。
まず、言語化に際してポイントとなる2点をご紹介します。
- 内容が明確で分かり易く、業務に反映しやすい適度な抽象度で設定すること
- 策定後の運用方針までイメージして作り上げること
前者は、内容の抽象度が高いと日常業務への反映がしづらく、反対に具体性を意識しすぎると活用シーンが限定されてしまうためです。適切な抽象度で言語化することによって、日常業務の幅広いシーンにおいて各社員の主体的な行動が引き出されます。
後者は、どのような形で運用するかをイメージすることで、適切な分量・表現の行動指針を策定するためです。例えば、行動指針をハンドブックとして運用するのであれば、中身の濃い比較的分量の多い行動指針が効果的ですが、ポスターなどで運用する場合、簡潔かつ印象的な表現である必要があります。
厳密に言えば、運用手段(ハンドブックなのかポスターなのか)から行動指針の内容が規定されるということはあまりありませんが、行動指針の表現方法と運用手段をセットで考えておくことによって、策定後の社員への浸透活動がスムーズに動き出します。
次に行動指針運用に際してのポイントについてです。
せっかく時間とコストをかけて策定した行動指針ですが、きちんと運用がなされなければ絵に描いた餅です。
行動指針をしっかりと運用・機能させるための主な方法は以下の三つです。
Point1 定期的な情報共有
Point2 見える化
Point3 人事制度や表彰制度への組み込み
Point1 定期的な情報共有
行動指針は、策定の背景や文脈まで、深く社員にインプットすることが望ましいです。時間が取れる場合は、一方的な説明会方式ではなく、ワークショップ形式などで双方向の議論ができれば良いでしょう。
Point2 見える化
これは、ハンドブックやポスター、卓上プレートなどのツールやモノに落とし込むことで行動指針が常に視界に入るようにし、社員の意識に刷り込みを行うことを指します。徹底して行うのであれば、ボールペンやマグカップなど、社内で使うあらゆるものに印字し、オリジナルのグッズを作るのも良いかもしれません。
Point3 人事制度や表彰制度への組み込み
行動指針を体現できている社員・従業員を毎朝の朝礼や年度の節目などで大々的に表彰したり、人事考課の査定項目にも組み込んだりすることです。金銭的・精神的なインセンティブによって、行動指針は単なるスローガンではなく、憧れや権威の象徴にまで高めることができます。
これら3つのポイントがしっかり実行されると、社内はおそらく「行動指針が共通言語化しており、飛び交っている」状態であり、まさにその状態こそが「行動指針がうまく機能している」状態ではないでしょうか。
さて、ここまで行動指針の策定方法、運用方法についてご説明いたしました。行動指針の策定と運用には大きな労力が必要とされますが、それによって産みだされる”行動への推進力”はブランディングを進める上で極めて大きな力となります。改めて、ブランドの「行動指針」を見つめなおしてみてはいかがでしょうか?
長くなりましたが、最後までご拝読いただきありがとうございました!