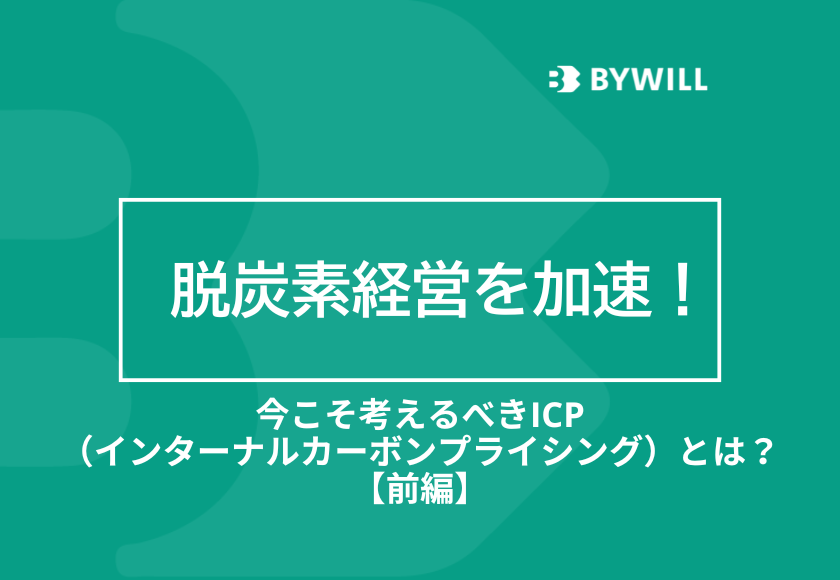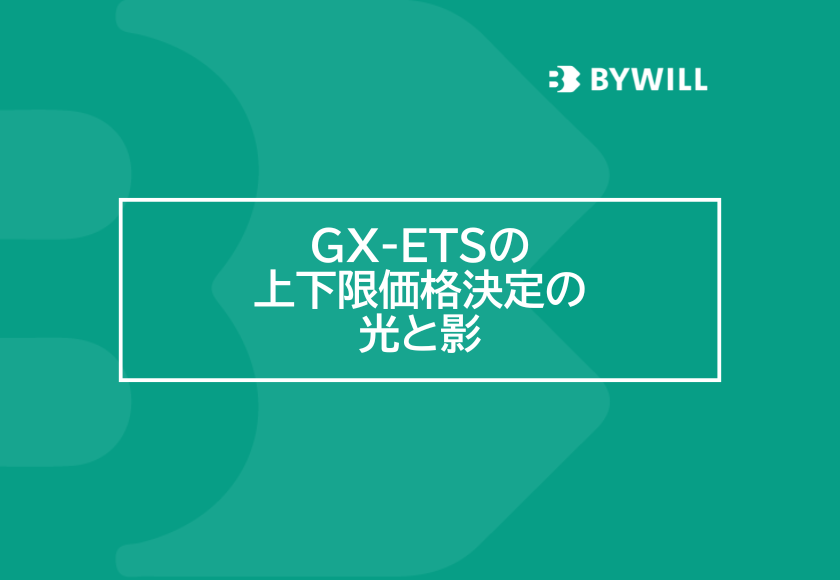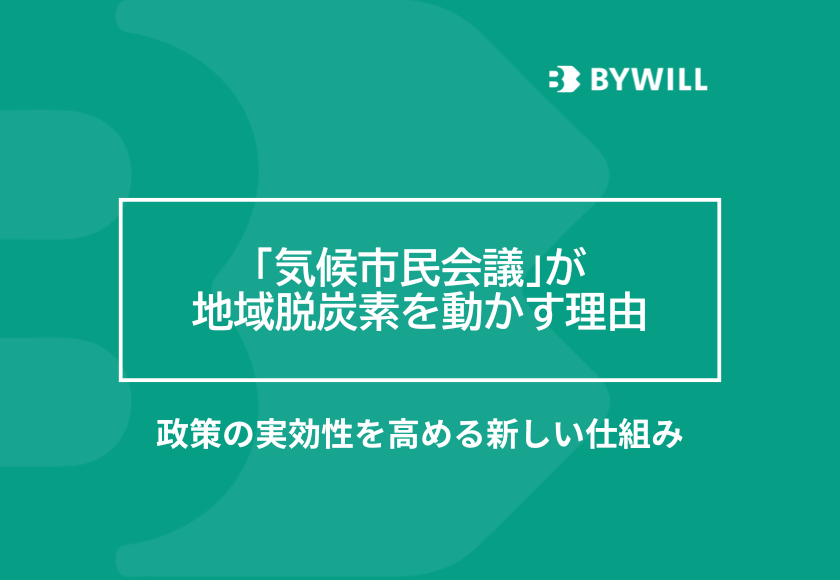「J-クレジットをつくる」ことを検討したことはありますか?
太陽光発電設備の設置や森林管理など、脱炭素に貢献する取り組みを行っている方の中には、「J-クレジットをつくると収入につながる」「J-クレジット創出をPRできる」といったことを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とはいえ「J-クレジットをつくる」といわれても、具体的なイメージが掴めないという方も多いかもしれません。
そこで本ブログでは、「J-クレジットをつくるとはどういうことか?」「どのような人がJ-クレジットをつくることができるのか?」「どのような手続きをしたら収益化できるのか?」といった疑問にお答えします!
◾️目次
1. J-クレジットをつくれるのは「温室効果ガスの排出削減・吸収活動をする人や団体」
2. J-クレジットとして認証されるのは「プロジェクト実施によって減ったCO2排出量」
3. J-クレジット創出の手続きは「プロジェクト登録→クレジット認証」
4. バイウィルのJ-クレジット創出支援は「完全成果報酬モデル」
1. J-クレジットをつくれるのは「温室効果ガスの排出削減・吸収活動をする人や団体」
J-クレジット制度とは、日本で行われた温室効果ガスの排出削減・吸収活動による削減量・吸収量を「クレジット」として販売・購入できる制度のことで、環境省・経済産業省・農林水産省が、日本の脱炭素推進を目指して運営しています。
この仕組みによって、脱炭素活動を応援したい企業や団体から、実際に活動に取り組む人・団体へ資金が回り、更なる脱炭素活動の取り組みを後押しすることにつながると考えられています。
※「J-クレジット制度の仕組みをもう少し詳しく知りたい」という方は、ぜひ下記のブログからご覧ください!↓
【J-クレジット制度を解説】購入者・創出者のメリットとは?
では、こちらの制度において、「J-クレジットをつくる人(創出者)」とはどのような人になるでしょうか?
簡単に言うと、J-クレジットの創出者とは「CO2をはじめとする温室効果ガスの排出削減・吸収活動をしている人や団体」です。
J-クレジット制度では、自らが取り組んだ活動による温室効果ガスの排出削減量・吸収量を「J-クレジット」として売却することができます。
ただし、実際の制度上では、クレジット化することのできる排出削減・吸収活動が「方法論」として定められており、全ての排出削減・吸収活動がJ-クレジット創出の対象となる訳ではありません。
方法論ごとに「何トン分のCO2の排出削減・吸収をおこなったのか」を算定する方法が定められており、この方法論がない場合には、制度上認められた削減量・吸収量の算定を行うことができないため、たとえ温室効果ガスの排出削減・吸収につながる活動を行っていたとしても、J-クレジットをつくることはできません。
2024年5月時点では70の方法論があり、方法論一覧はJ-クレジット制度の公式サイトから確認することができます。
▼ J-クレジット公式サイト「方法論」
https://japancredit.go.jp/about/methodology/

また、J-クレジット創出を行いたいが、当てはまる方法論がないという場合には、事務局への提案を行って、運営委員会の承認を得ることで、新規方法論をつくることも可能です。
ただし、こちらは様々な要件を満たすことが求められ、厳しい承認プロセスがあるため、ハードルは高いといえるでしょう。
「自分たちの行っている活動でJ-クレジットをつくれるのかを確認したい」という方は、まず方法論一覧から当てはまりそうなものを探し、要件を確認するというのが第1のステップとなります。
2. J-クレジットとして認証されるのは「プロジェクト実施によって減ったCO2排出量」
前章では、方法論に当てはまる活動をしている人や団体がJ-クレジットを創出できるとお伝えしました。
とはいえ、「温室効果ガスの削減量・吸収量がクレジットになる」ということがどういうことなのか、あまりイメージが湧かないという方もいらっしゃるかと思います。
そこで本章では、「何が『クレジット』になるのか?」ということをもう少し具体的にご説明します。
J-クレジットは、「○○t-CO2(読み:トンシーオーツー)」という単位で取引されています。
J-クレジット制度上では、J-クレジット創出のもととなる排出削減・吸収活動を「プロジェクト」と呼びますが、この「プロジェクト」を実施したことによって、実施しなかった時よりもCO2の排出量が少なくなると、その削減された分がJ-クレジットになります。
(吸収活動の場合には、プロジェクトを実施したことによって増えたCO2 の吸収量がJ-クレジットとなります。)
例えば、照明設備を入れ替えるプロジェクトによって、前の設備のままだったら排出されていたはずのCO2量が100トン分少なくなったという場合には、「100 t-CO2」のクレジットが認証されるということです。
大まかな算定方法のイメージは下記のようになります。
※実際の方法論で定められている算定方法はさらに細かいものとなります。詳しくは、各方法論をご確認ください。
[J-クレジットとして認証される削減量]=
[プロジェクトを実施しなかった場合のCO2排出量]ー[プロジェクト実施後のCO2排出量]
[J-クレジットとして認証される吸収量]=
[プロジェクト実施後のCO2吸収量]ー[プロジェクトを実施しなかった場合のCO2吸収量]

また、J-クレジット制度の対象となっている温室効果ガスには、CO2以外のガスもあり、それらの削減・吸収活動を行った場合には、各ガスの温室効果をCO2に換算して計算します。(単位は「t-CO2e」となります。)
当てはまる方法論が見つかり、J-クレジットを創出することになった場合には、方法論に定められた手順に則って、上記のような算定を行います。
3. J-クレジット創出の手続きは「プロジェクト登録→クレジット認証」
ここまで、J-クレジット創出はJ-クレジット制度で定められた方法論に当てはまる活動をしている人や団体が、その活動を行うことによって排出削減・吸収したCO2トン数をJ-クレジット化することができると説明しました。
J-クレジットがどのようなものなのか、少しイメージが湧いてきたでしょうか?
最後に本章では、J-クレジットを創出する際に必要な手続きについて、「準備する書類はどのようなものか?」や「どういった人や機関が関わるのか?」などを具体的にご説明します。
J-クレジットの発行を受けるためには、ただ削減・吸収活動の実績を報告すればよいというわけではありません。
J-クレジットが発行されるまでには、大きく2つのステップがあります。
まず、「温室効果ガスの排出削減・吸収の取り組みとしてどのような活動を行うのか」を登録する「プロジェクト登録」を行います。
そして、プロジェクト登録が完了すると、実際に行った活動実績を制度管理者に報告することができるようになります。登録したプロジェクトの活動実績に基づいて排出削減・吸収量を報告し、報告内容に間違いがないという認証を受けます。これを「クレジット認証」といいます。
「プロジェクト登録」→「クレジット認証」という2つのステップを終えると、国からJ-クレジットが発行されるという流れになります。

【①プロジェクト登録】
J-クレジットを創出したい活動(プロジェクト)の内容が制度の規程に沿った適切なものであると認められると、プロジェクトがJ-クレジット制度に登録されます。
プロジェクト登録が完了して初めて、実際の活動に基づく排出削減量・吸収量の報告を行うことができるようになるため、プロジェクト実施者はまずプロジェクト登録を目指すことになります。
各工程について、もう少し詳細にご説明します。
①-1. プロジェクト計画書の作成
「どのような排出削減・吸収活動を実施するのか」を記載した計画書を作成します。
記載する内容の一部としては、下記のようなものが挙げられます。
- 該当する方法論
- プロジェクト実施によって見込まれる排出削減量・吸収量
- 排出削減量・吸収量の計測(モニタリング)方法 など
プロジェクト計画書はプロジェクトに関する詳細な情報を方法論に沿った形で適切に記載することが求められるため、プロジェクト実施者が自力で作成するのが難しいというケースも少なくありません。
そうした場合には、J-クレジット制度事務局による計画書作成のコーチングや企業によるカーボンクレジット創出支援サービスの利用を検討することが考えられます。
①-2 妥当性確認
①-1で作成したプロジェクト計画書の内容が、「実際に行った(行う予定)の活動の実態を反映したものなのか」「J-クレジット制度の規程に沿っているか」ということについて、J-クレジット制度に登録されている審査機関から審査を受けます。
2024年5月現在では、5つの機関が審査機関として登録されています。
該当する方法論によっても対応できる審査機関が異なっているため、公式サイトから確認することが必要です。
▼ J-クレジット公式サイト「審査機関」
https://japancredit.go.jp/about/vvb/
プロジェクト登録のためには上記の審査機関からの審査を受けることが必須であるため、J-クレジット創出を行う人・団体が多い場合には、審査を依頼してから実際に審査を受けるまでに数か月かかることも考えられます。
登録の目標時期がある場合などには、余裕をもってスケジュールを立てることが重要です。
また、審査機関から審査を受ける際には、1つのプロジェクトにつき45万円~110万円程度※の審査費用が掛かるためこちらも注意が必要です。
※J-クレジット公式サイト公表の2021年度から2023年度の審査費用の平均値を参照(https://japancredit.go.jp/application/flow/)
①-3 プロジェクト登録申請
前述の審査機関による妥当性確認を通ると、J-クレジット制度管理者に対してプロジェクト登録申請を行うことができます。
登録申請を行うと、有識者によってプロジェクト登録・認証に関する審議を行う「認証委員会」に諮られます。
認証委員会は常時行われている訳ではなく、例年では年に5回ほど開催されています。
また、登録申請は認証委員会の開催日の2,3週間前が締め切りとされていることが多いので、審査後の登録申請を逃すことのないよう、スケジュールを管理することが重要になります。
認証委員会でプロジェクト内容が適切であると認められると、プロジェクトがJ-クレジット制度に登録されます。
【②クレジット認証】
プロジェクト登録が完了すると、実際に行ったプロジェクトやそれによる排出削減量・吸収量を報告するステップに移ります。各工程について以下で簡単に説明します。
②-1 モニタリング実施・報告書作成
①で登録したプロジェクト計画書に基づいて、排出量・吸収量算定に係る項目の測定を行います。
その上で、測定結果に基づいて削減量・吸収量を算定し、「モニタリング報告書」を作成します。
また、方法論やプロジェクトによっては、報告対象となっているデータを測定するために測定機器の導入や外部サービスの利用が必要となるケースもあります。
例えば、方法論FO-001「森林経営活動」では、初回のモニタリング実施時に面積や樹高の実測データ等が必要となるため、場合によっては航空機による測量業務を外部に委託することもあり、そのための費用が発生することも考えられます。
②-2 検証
①-2と同様に、「作成したモニタリング報告書の内容がJ-クレジット制度の規程やプロジェクト計画書に沿っているか」ということについて審査機関からの審査を受けます。
ここでも審査を受けるためには費用が掛かり、過去の平均では1つのプロジェクトにつき40万円~105万円程度※となっています。
※J-クレジット公式サイト公表の2021年度から2023年度の審査費用の平均値を参照(https://japancredit.go.jp/application/flow/)
②-3 クレジット認証申請
審査機関による検証を通ると、J-クレジット制度管理者に対して、クレジットの認証申請を行うことができます。
登録時と同様に、「認証委員会」で審議が行われ、モニタリング報告内容が適切であると認められると「クレジット認証」となり、売買可能な「J-クレジット」が発行されます。

J-クレジットは、「①プロジェクト登録→②クレジット認証」を行うことで創出することができます。
前述のような工程を全て終えてクレジットが発行されると、J-クレジット公式サイトの「売り出しクレジット一覧」や取引プラットフォームにクレジット情報を掲載したり、J-クレジット・プロバイダーなどの仲介を利用したりするなどの方法で売却を行うことができるようになります。
※クレジットの売買についての詳細は下記のブログをご参照ください↓
【J-クレジットの買い方が分かる!】購入方法をわかりやすく比較・解説します
登録・認証を行うためには、それぞれ書類の作成や審査機関の対応が必要になり、また審査やモニタリングの実施等で費用が発生します。
また、プロジェクト登録からクレジットの認証まで審査機関・認証委員会・モニタリング実施時の協力会社など複数の関係機関がある中で、適切なステップで進行するようスケジュール管理をすることが重要になります。
こうした費用や労力がかかることやプロジェクト管理の複雑さから、J-クレジット創出に関してハードルを感じるという企業様もいらっしゃるかと思います。
これら全てを自分たちで行うということが難しい場合には、クレジット創出の支援を行っている事業者などにサポートを依頼することも選択肢の一つと考えられます。
4. バイウィルのJ-クレジット創出支援は「完全成果報酬モデル」
バイウィルでは、J-クレジット創出に必要な書類作成や審査対応、申請手続きに関するサポートを行っています。
また、登録・認証に必要な審査費用やモニタリングにかかる費用も弊社が負担し、クレジット売却時に売却益から費用を回収する成果報酬モデルをとっています。もちろん、書類作成などに関しても個別に費用をいただくことはありません。
つまり、クレジット創出に取り組む方は、費用に関するリスクゼロで進めることができます。
また、弊社支援によって創出したクレジットは買手探索から収益化まで一貫してサポートするため、つくったクレジットの売り先を探す必要もありません。
▼バイウィルのJ-クレジット創出支援サービスに関する詳細は以下をご覧ください。
環境価値創出支援(クレジット創出支援)
「何t-CO2分のクレジットを創出できそうか?」の簡易算定も承っておりますので、「J-クレジット創出に興味はあるが自分たちだけで進められるか不安がある」、「実際に取り組んだ時にどれほど成果が得られるのか具体的なイメージを持ちたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください!