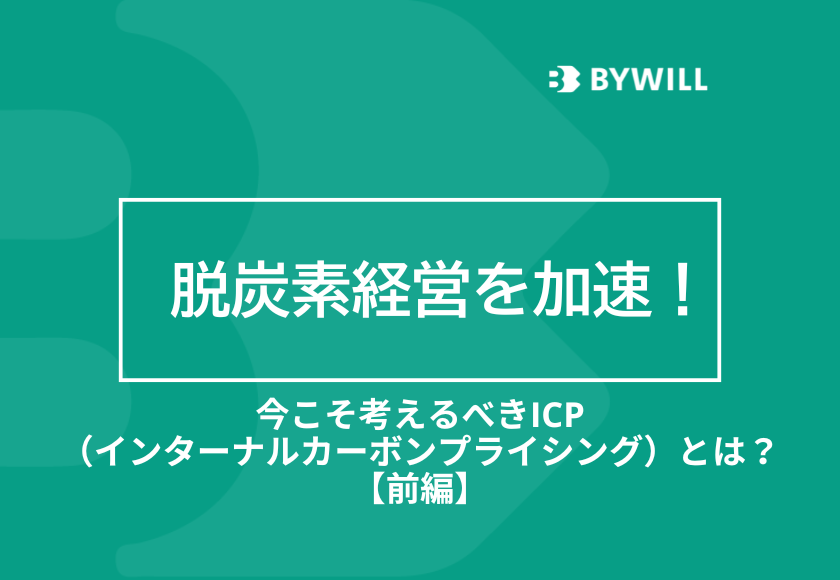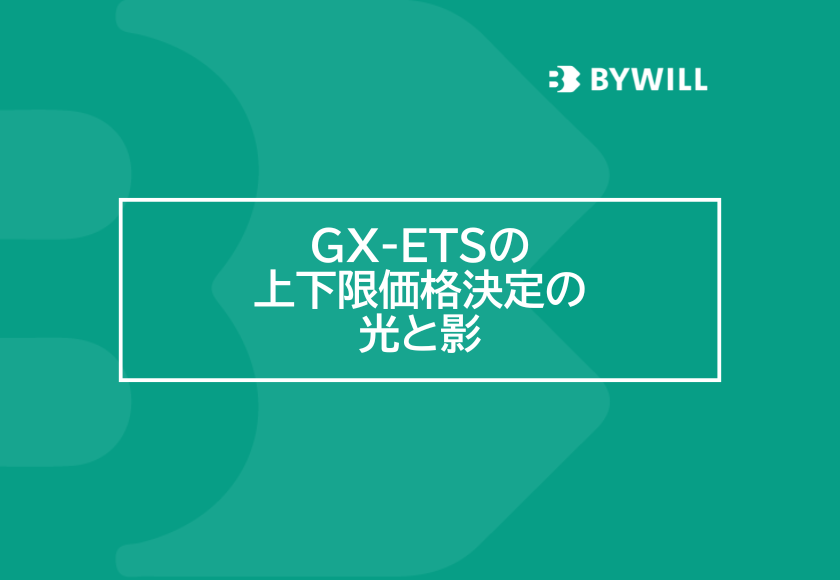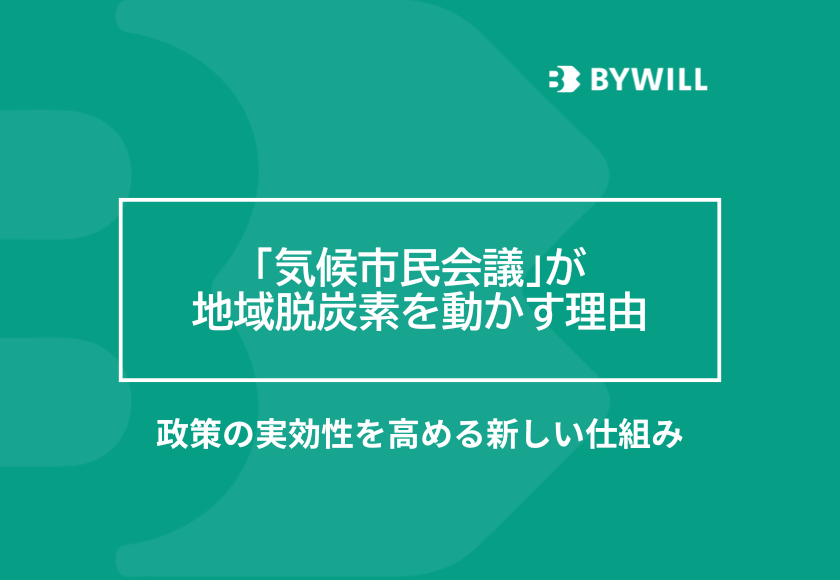日本の脱炭素推進を目的として、国によって運営されている「J-クレジット制度」ですが、購入したJ-クレジットはどのように活用することができるのか、皆様はご存じでしょうか?
「そもそもJ-クレジット制度とは?」「前提情報や制度の仕組みから理解したい」という方は、ぜひ前回のブログ(【J-クレジット制度を解説】購入者・創出者のメリットとは?)からご覧ください。
本ブログでは、「制度のイメージは掴めたが、もう少し具体的な活用方法が知りたい」「自社の行っている報告にJ-クレジットが使えるのかを確認したい」という方に向けて、J-クレジットを活用することのできる各種報告について解説します。
◾️目次
1.J-クレジットを活用できる各種報告について
J-クレジットは、日本の法律や国際イニシアチブ等で定められている報告のために活用することができます。
主要なものとしては、温対法・省エネ法・CDP・SBT・RE100などが挙げられます。これらの概要と、具体的にJ-クレジットがどのように活用できるかについて以下でご紹介します。
①温対法
「温対法」と略されることの多いこちらの法律は、正式には「地球温暖化対策の推進に関する法律」といいます。
温室効果ガスを一定以上排出する事業者(特定排出者)は、この「温対法」によって、温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。
具体的に対象となる排出者の要件は、環境省の温対法公式サイトから確認することができます。
※温対法公式サイト:https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about
対象となる事業者のうち、特定事業所排出者は、実際の温室効果ガスの排出量(基礎排出量)だけでなく、カーボンクレジットなどを活用して調整した排出量(調整後温室効果ガス排出量)の報告も行うこととなっています。
カーボンクレジットなどの活用によって排出量が実質ゼロとなっている電気やガスを使用したり、カーボンクレジットを購入して無効化したりすることによって、調整後温室効果ガス排出量を減らすことができます。
温対法における温室効果ガス排出量の調整には、種類に限らず、全てのJ-クレジットを活用することができます。
②省エネ法
温対法とセットで聞くことが多い「省エネ法」の正式名称は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」です。
この法律では、一定以上エネルギーを使用する事業者に対し、毎年度のエネルギーの使用等についての「定期報告書」などの提出を求めます。
詳しい要件は経済産業省の省エネ法公式サイトから確認することができます。
※省エネ法公式サイト:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/
ここで提出された報告書等の内容によって、経済産業省からS(優良事業者)・A(一般事業者)・B(停滞事業者)へのクラス分けが行われ、Sクラスの事業者は優良事業者としてホームページでの公表などが行われる一方、Bクラスの事業者へは報告徴収、立入検査などが行われる場合があります。
省エネ法では「単位量の製品や金額を生産するのに必要なエネルギー消費量(エネルギー消費原単位)を年平均1%以上改善すること」を事業者の目標としています。
事業者が、十分に努力を行っているにも関わらず、この目標を達成できていなかった場合、省エネルギー由来のJ-クレジットの購入などを行うと、そのことを勘案・評価するとされています。
また、2023年の省エネ法改正により、事業者は使用した電気全体に占める非化石エネルギーの比率についても報告を行うこととなりました。
こちらの非化石エネルギーの使用状況の報告においても、再生可能エネルギー由来や一部の省エネ由来※のJ-クレジットなどを購入した場合には、その非化石価値相当分のエネルギー使用量を考慮に入れた算出を行うことができ、報告する非化石エネルギーの比率を、実際の使用状況よりも高い数値として報告できるようになります。
※対象となるJ-クレジットについての詳細は、J-クレジット公式サイトをご確認ください。参考:https://japancredit.go.jp/case/cdp_sbt_re100/
③CDP
CDPとは、投資家向けに企業の環境情報の提供を行うことを目的とした国際的なNGOです。
各企業が気候変動等に関わる事業リスクにどのように対応しているか、質問書形式で調査し、評価したうえで公表するという情報開示システムを運営しています。
CDPは質問書への回答内容を基に、各企業にスコアをつけており、このスコアは気候変動に関心をもつ投資家や企業などの意思決定に大きな影響を与えています。
2023年には、CDPを通じて回答要請を受けた企業のうち、全世界で約23,000社、日本では約2,000社※が情報開示に取り組みました。
※CDP公式サイト,「CDP 2023 企業の情報開示」より:https://japan.cdp.net/scores
質問書の中では、温室効果ガスの排出量(Scope1,2,3)の回答が求められますが、そのうちのScope2(他者から供給された電気・熱・蒸気の使⽤に伴う間接排出)の算出にあたって、エネルギー属性証明にあたる再生可能エネルギー由来のJ-クレジットを再生可能エネルギー調達量として活用することができます。
④SBT
SBTとは、Science Based Targetsの略称で、企業が策定する「パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出量削減目標」のことを指します。
策定した目標をSBTの運営組織であるSBTiに申請し、妥当性確認を通るとSBTの認定を取得することとなります。
また、まだ目標を策定していない企業に関しては、「2年以内にSBT⽔準の排出削減⽬標を設定してSBTiに申請することを対外的に宣⾔(コミット)する」ということも可能です。
SBTの公式サイトでは、SBT認定を受けた企業やコミットメントを行った企業が公表されています。
2024年3月時点では、SBT認定取得または取得することを約束(コミット)した日本企業の数は1000社※を超えています。
※WWFジャパン,「日本企業SBT認定・コミットが1000社超え」より:https://www.wwf.or.jp/activities/news/5561.html
SBT認定を受けた企業は毎年排出量を開示し、目標達成の進捗状況を報告することが求められます。
こちらの報告においても、CDPの質問書への回答と同様に、再生可能エネルギー由来のJ-クレジットを再エネ調達量として報告することができます。
また、上記の使い方は、あくまで「再生可能エネルギーを調達している」ということを示すエネルギー属性証書としての活用方法であり、2024年4月現在、SBTiはカーボンクレジットを活用して温室効果ガスの排出量をオフセットすることは認めていません。
しかし、2024年4月9日にSBTiが公表した声明では、Scope3(事業者の活動に関連する他社の排出量)に関してカーボンクレジットの活用を認める方針が示されました。
SBTiにおけるJ-クレジットの活用方法が広がる可能性もあり、今後の動向に注目すべきといえるでしょう。
⑤RE100
RE100とは、企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブであり、脱炭素化を推進する国際NGO「クライメイトグループ(The Climate Group)」が運営しています。
消費電力量が一定以上であり、自社事業で使用する電力(Scope1,2の電力消費)の100%再生エネ化に向け、期限を切った目標を設定・公表することが参加の要件とされています。
2024年4月時点では、85社※の日本企業が参加しています。
※JCLP,「RE100・EP100・EV100国際企業イニシアチブについて」より:https://japan-clp.jp/climate/reoh
RE100参加企業は、毎年、The Climate Groupに対して電力消費量、再エネ調達量、再エネ発電量などの報告を行うことが必要です。
こちらの報告においては、再生可能エネルギー由来のJ-クレジットのうち、電力由来のものに限って、再エネ調達量として報告することができます。
また、消費電力量の小さな企業に関しては、RE100が推奨する「再エネ100宣言 RE Action」に参加することが可能であり、2023年10月時点で300社以上※が参加しています。
※再エネ100宣言 RE Action,「再エネ100宣言 RE Action年次報告書2023」より:https://saiene.jp/annualreport
「再エネ100宣言 RE Action」参加企業も、事務局に対して消費電力量と再エネ率の年次報告を行うことが規定されており、こちらの報告でも再生可能エネルギー(電力)由来のJ-クレジットが活用できるとされています。
2. J-クレジットの主な活用先と対応するクレジットの種類
J-クレジット制度では、2024年4月現在、70の活動をクレジット創出の対象としていますが、それらの方法は、その活動の性質によって、大きく6つの種類(再エネ由来・省エネ由来・工業プロセス由来・農業由来・廃棄物由来・森林由来)に分類されます。
また、「再エネ由来」のクレジットに関しては、さらに2つに分けて考えることが多く、太陽光発電やバイオマス発電のように、電力を自家消費したプロジェクトに由来する「再エネ(電力)由来」のものと、バイオマスボイラーのように熱を自家消費したプロジェクトに由来する「再エネ(熱)由来」のものに分類されます。
上記で説明した各種報告も、それぞれ活用可能なJ-クレジットの種類が定められています。
各種報告と対応可能なJ-クレジットの種類を一覧にまとめましたので、ぜひご確認ください。

参考文献:
- J-クレジット制度,「J-クレジットの活用方法」:https://japancredit.go.jp/case/outline/
- 環境省・経済産業省,「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0) (令和6年2月)」:
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual - 資源エネルギー庁,「省エネ法の手引き 工場・事業場編-令和5年度改訂版-」:
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/shoene_tebiki_01.pdf - 一般社団法人 CDP Worldwide-Japan公式サイト:https://japan.cdp.net/
- SBTi公式サイト:https://sciencebasedtargets.org/
- JCLP,「よくあるご質問(RE100参加について)」:https://japan-clp.jp/membership/faq-reoh
- 再エネ100宣言 RE Action公式サイト:https://saiene.jp/
バイウィルでは、J-クレジットの創出・売買のご支援や脱炭素コンサルティング、環境価値ブランディングなどを行っています。
J-クレジット・企業の脱炭素推進に関するご質問やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。