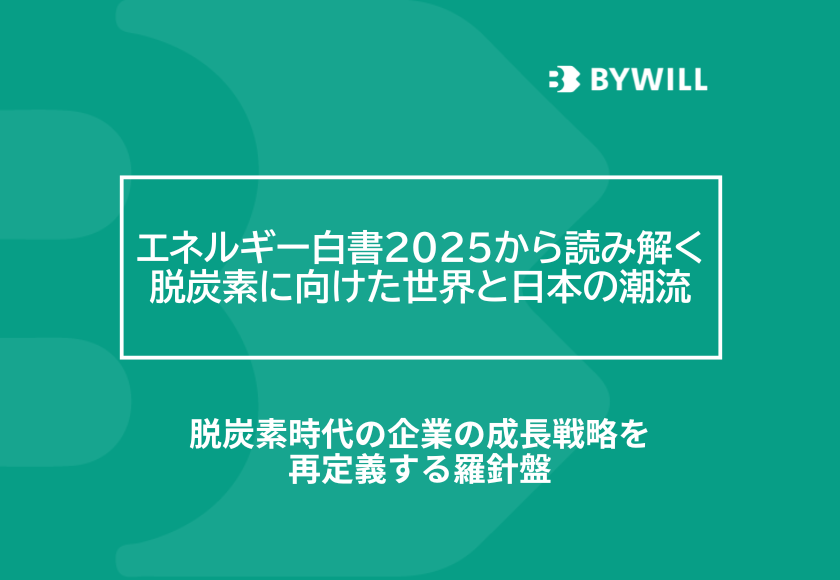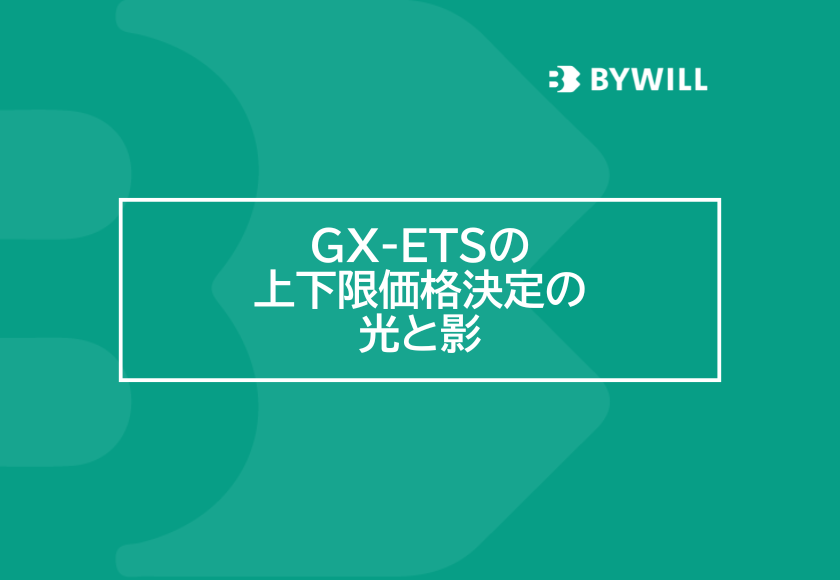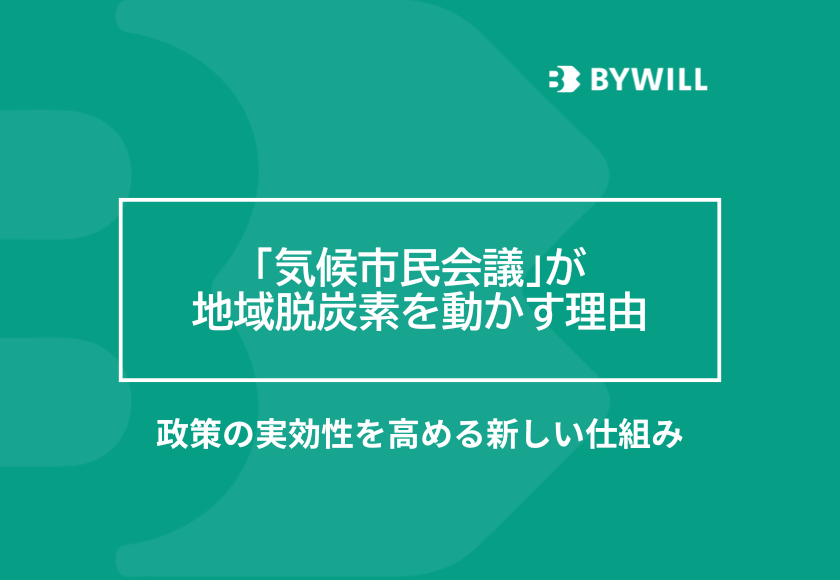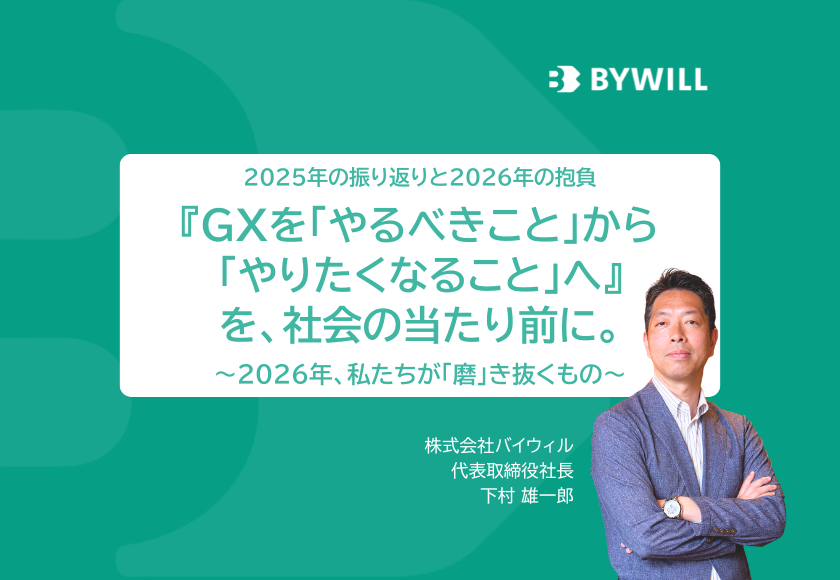2025年6月13日に日本のエネルギー政策の羅針盤「令和6年度エネルギーに関する年次報告」、通称「エネルギー白書2025」(以下、白書)が発表されました。
昨年もGXやカーボンニュートラル、新技術の重要性は語られていたものの、今年は次世代技術の進展や商用化への具体的な道筋が深堀されています。
白書は「脱炭素やカーボンニュートラルに向けて、日本はどこに向かっているのか?」という問いへの重要なヒントを提示しており、今回は「脱炭素に向けた世界と日本の潮流」という視点に焦点を当てて、「エネルギー白書2025」の全体像をカーボンニュートラル 総研の森 英哲がお伝えします。
激動する世界情勢と日本の選択
ロシアによるウクライナ侵攻以降、世界のエネルギー市場は混乱し、各国はエネルギー安全保障と脱炭素という二つの目標を同時に追求することへの難しさに直面しています。
そんな中、主要国は異なるアプローチでカーボンニュートラルを追求しています。
たとえば、米国はパリ協定からの脱退をはじめクリーンエネルギー政策の転換を進めているものの、原子力や地熱発電は導入を促進する方針で、EUはエネルギーの脱ロシア依存を加速しつつ、欧州域内のグリーン産業支援を強化しています。その他新興国も独自のエネルギーミックスを模索しており、各国が太陽光・風力・原子力・水素など、様々な電源を組み合わせながら脱炭素へ向かっているのが世界の潮流です。
それでは、資源に乏しい日本は、このグローバルな競争と課題にどう立ち向うのか?白書では、GXという包括的な戦略を通じて、技術革新への投資と国際連携を強化しながら、経済成長と排出削減の両立を図るという方針が示されています。
「エネルギー白書2025」が示す、GXに向けた現場での具体的な取組
白書では、政府が前年度(令和5年度)に講じた具体的な施策とその進捗が詳細に報告されており、日本の脱炭素への取り組みがすでに現場で着実に動き出している証と言えるでしょう。
その中で脱炭素に関わる主な取組みをいくつかご紹介します。
まずは最も基本的な脱炭素策となる省エネルギーについて、産業・家庭・運輸の各部門で、高効率機器導入や住宅断熱性能向上、AI/IoT活用によるスマートなエネルギー消費への転換が進んでいます。
次に、脱炭素の主役ともいえる再生可能エネルギーの導入です。再エネは「S+3E」(安全性、安定供給、経済性、環境適合)を前提に主力電源化を徹底し、FIP制度の運用改善や送配電網の増強に加え、洋上風力発電の導入が進められています。
そして、原子力政策の展開も不可欠です。福島第一原発事故の教訓を踏まえ、既存原発の安全性向上対策と再稼働、さらに運転期間延長に向けた法制度整備が進められています。加えて、次世代革新炉の開発や核燃料サイクルの推進も進み、エネルギーミックスの一翼としての貢献が期待されます。
また、自然災害やサイバー攻撃に備え、国内エネルギー供給網の強靱化も喫緊の課題です。災害対策強化、電力・ガス送配電網の強化・スマート化、サイバーセキュリティ対策など、強固なインフラ構築が進められています。
さらに、次世代の脱炭素燃料水素・アンモニアの導入拡大も加速しており、白書では製造から輸送、利用に至るまでのサプライチェーン構築への具体的な取り組みが示され、発電燃料や工場利用など、社会実装に向けた動きが活発化しています。
なお、日本の優れた技術を活かした国際連携と戦略的な技術開発も進められています。白書はアジア地域などへの脱炭素技術の展開や国際協力の状況、そして蓄電池やCCUS(CO2を回収・貯留・利用する技術のこと)といった革新的なエネルギー技術の研究開発への支援を強調しています。
白書は、企業の成長戦略を再定義する羅針盤
「エネルギー白書2025」は日本が世界の脱炭素競争の中でGXという野心的な戦略を描き、既に具体的な取組みを力強く推進していることを明示しています。
この白書は、企業にとって脱炭素時代のビジネス環境を理解し、新たな成長戦略を策定するための重要な羅針盤となり得ます。サプライチェーン全体の脱炭素化、GX推進法を活用した投資と資金調達、そしてレジリエンスの強化など、これら全てがGX戦略と深く結びついているのです。
ぜひこの機会に深く読み込み、世界の潮流と日本の脱炭素戦略を理解し、貴社の持続的な成長と企業価値向上に繋がる具体的なアクションを検討・推進してください。