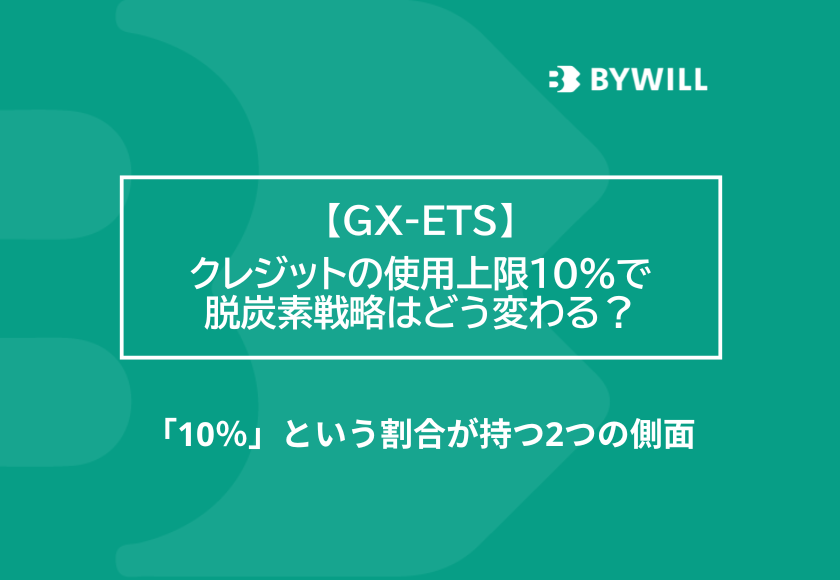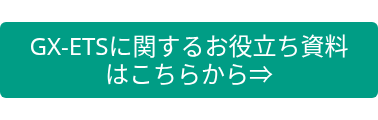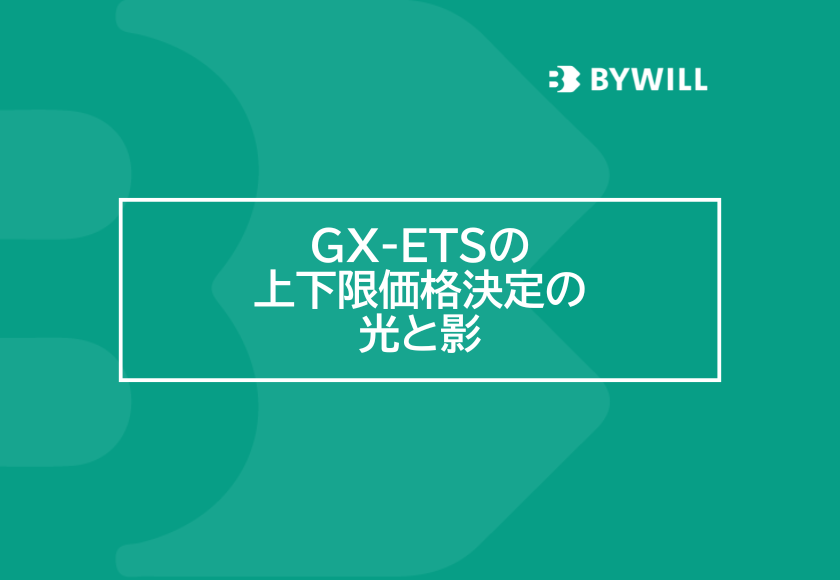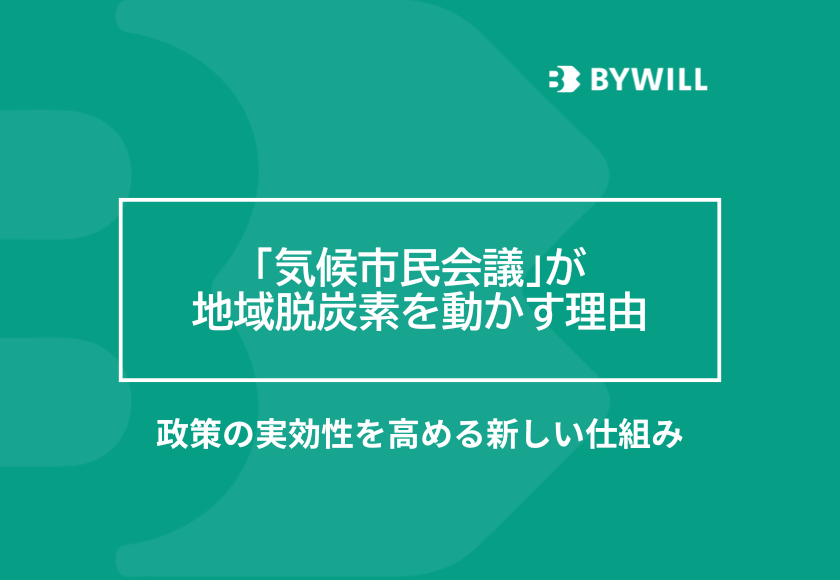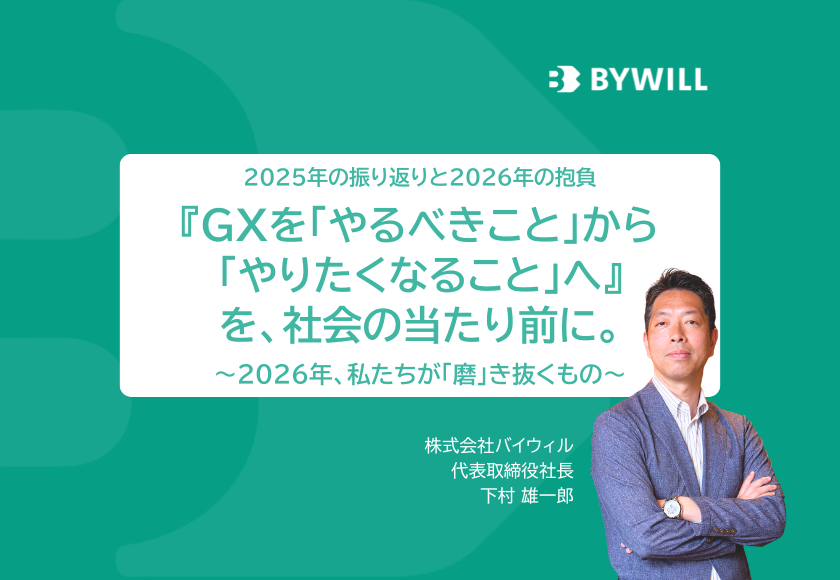7月2日、2026年度から本格導入される排出量取引制度において、経産省がカーボンクレジットの使用上限を排出量の10%に制限する方針を決定しました。
「10%」という数字は一見するとシンプルな基準に見えますが、本決定は自社の直接的な排出削減努力と社会全体の脱炭素加速を後押しする2つの側面を持ちます。
今回のブログでは、バイウィル カーボンニュートラル総研の森 英哲が、本決定の背景や日本の脱炭素戦略に与える影響について、海外動向や日本におけるカーボンクレジット取引の状況も踏まえながら解説します。
GX-ETSフェーズ2の概要とカーボンクレジットの位置づけ
GX-ETSはCO2削減を「成長の機会」と捉え、企業が自律的に脱炭素へ向かうインセンティブを生み出し、日本の産業構造改革をめざす戦略的な排出量取引制度です。
フェーズ2では、CO2直接排出量が一定規模以上の事業者に参加が義務付けられ、排出量の割り当てや取引市場の整備、未履行時のペナルティ導入で実効性が強化されます。
あわせて、カーボンクレジットによるオフセットが許容されますが、今回の方針決定で、その上限が排出量取引の対象となるCO2排出量の10%に決定しました。
カーボンクレジットの使用を許容するのは、中小企業を含めた制度対象外の事業者による脱炭素投資の促進や、制度対象事業者のスコープ3削減で生じる環境価値を制度内に取り込むためです。
それでは、その上限が10%というのは、多いのでしょうか、それとも少ないのでしょうか。
世界の排出量取引制度に見るカーボンクレジットの取引制限
海外の排出量取引制度を見ても、実質的な排出削減努力の促進や適正なクレジット価格の維持・形成を目的に、カーボンクレジットの使用には一定の制限があります。
EUはEU-ETSのフェーズ3まで一部のオフセットクレジットを認めていましたが、21年以降のフェーズ4からは域外クレジットを一切認めず、カリフォルニア州のキャップ&トレード制度では、2021年度からオフセットクレジットの使用上限を8%から4%に厳格化しました。また、韓国や中国でも同様に使用制限があります。
この点、日本の10%は、他国に比べると一見緩い制限と思われるかもしれませんが、上限を設けることで多排出企業の直接削減を軽視していないことをアピールしつつ、多排出企業以外も含めた社会全体で脱炭素の機運を醸成するという2つの側面があるのです。 
日本におけるカーボンクレジット取引の状況
日本のGHG排出量約10.8億トンに対してGX-ETSフェーズ2でカバーされるのは6.5億トンですが、今回の10%上限を加味するとオフセットできるのは6,500万トンとなります。
これに対して、J-クレジットの累積創出量は約1,000万トンで、その半分は無効化されており、4割程度しか残っていない状況です。
それを踏まえると、日本国内のクレジット創出・取引量は限定的で、今回の10%というのは、制限していないのと同義と捉えることもできます。
まとめ
今回の10%という排出量取引におけるクレジットの使用上限は、GX-ETSの対象企業に自社の直接削減を要求しつつ、対象企業以外を含めた日本全体で脱炭素アクションを進めていこうとする意志の表れです。
日本の現状を踏まえても、決してクレジット取引に消極的な水準ではなく、今回の決定は「規制」ではなく「機会」と捉えるべきだと考えます。
GX-ETSの対象企業もそうでない企業も、この変化を前向きに捉え、サプライチェーン全体の効率化・最適化や技術革新への投資加速、カーボンクレジット取引を進めることで、日本の脱炭素や国際的な競争力向上に一丸となって取り組んでいきましょう。