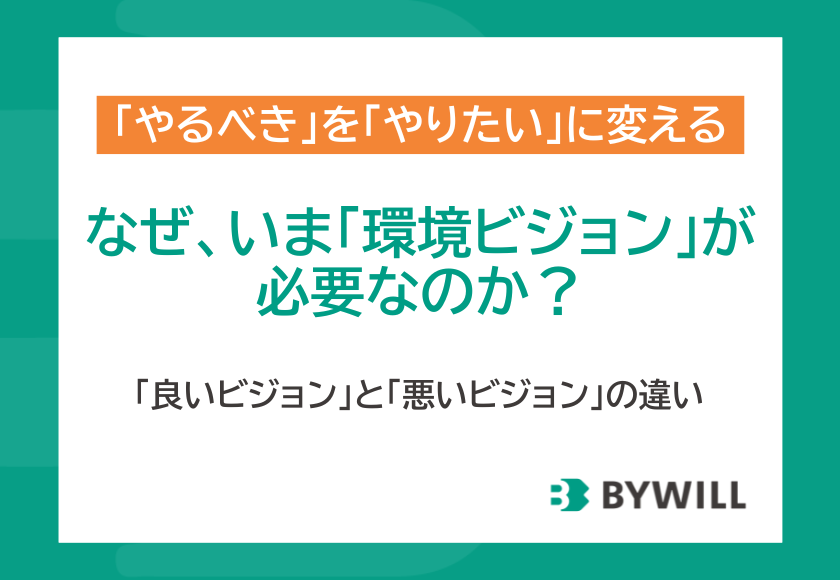概要
1957年10月に創立、国内コンタクトレンズ業界をけん引する存在である株式会社シード様。
知名度のある自社商品ブランドだけでなく、企業名でも顧客から選ばれる存在となることを目指し、コーポレートブランディングに着手することに。その取り組みにバイウィルが伴走させていただき、ブランド構築から社内外への浸透まで、一貫してご支援しました。
ご提供サービス
・市場調査、従業員調査の実施
・ブランドコンセプト策定
・パーパス、 経営理念、 カルチャー策定
・ブランドロードマップ策定
・コーポレートロゴ、キーエレメント制作
・管理職向けのパーパス浸透ワークショップ実施
・パーパスポスター・ブック・ムービー、オンライン会議ツール用背景、PowerPointテンプレート制作
ご支援の流れ

商品ブランドは知っていても、企業名は知られていない。長年抱えた課題を解決するために着手した、コーポレートブランディング
── Pureシリーズなど、よく知られたコンタクトレンズブランドを多数抱えておられるなか、なぜコーポレートブランディングに取り組まれることになったのですか?
山口様:これまで長い間、当社の「企業としての知名度」には危機感を感じていました。当社が企業として認知されているのは関東圏の40代以上の方々が中心で、若年層は「商品ブランドは知っているが企業は知らない」という方が多いというのが現状です。
これは、過去、「シードのコンタクトレンズ」を謳うテレビCMを集中投下していたことがあったため、その頃を知っている方々には一定数は認知していただけているものの、その後は商品ブランドの訴求に集中していたことが原因です。
そうしている間に、他国内メーカーや海外の競合メーカーのほうが多くの方に知られるようになりました。その結果、企業としての認知度が競合と比較して低い、という状況がこの20年ほど続いていたのです。
信國様:イベントに出展しても、「シードって、この商品を扱っている会社なんだ」と言われることも多く、企業としての知名度の低さを、身をもって実感する場面は多かったです。
山口様:当社はこれまで、会社が目指すべき姿として“『眼』の専門総合メーカーとしてお客様の『見える』をサポートする”というスローガンを掲げ、経営の軸としていました。
ですが、ホームページに掲載している程度で強く訴求していなかったため、企業の認知度向上には繋がっていませんでした。
そこで、会社の認知度を上げるために、ブランディングをしていこうと動き始めたのが5~6年前のことです。

(写真左から)山口様、信國様
── 5~6年前から検討されていたなかで、いざプロジェクトとして進めていこうと思い切ったきっかけはあるのでしょうか。
山口様:コーポレートブランディングについて勉強を進めるなかで、バイウィルさんのブランディングに関する無料セミナーに参加したのを皮切りに、バイウィルさんとはそこから1年以上もの間、ディスカッションを続けていました。
そのディスカッションを通して、本格的に動き出そうという意識が高まったことで、これまでは経営企画部のメンバーが業務の一部として進めていたところ、コーポレートブランディングを担当とする「コーポレートコミュニケーション部」を立ち上げることになりました。その変化が、取り組みを最も加速させたきっかけになったと思います。
専門の組織が立ち上がったことが後押しになり、バイウィルさんにも上申資料の作成に伴走していただいて、社長をはじめとした経営層の承認を得たところからプロジェクトが動き始めました。
「みえる」に寄り添う。大切にすべき会社の根幹は変えず、新たな一歩を踏み出すためのパーパス策定
── コーポレートブランドの軸として策定したのが、「パーパス」でした。パーパスを新たに策定すると伝えた際、経営層など策定に携わってくださった方々の反応はいかがでしたか?


山口様:「パーパスを策定する」と伝えて、すぐに受け入れられたかと言われると、そうではない方のほうが多かったと思います。「パーパスって何?」というところからのスタートでしたし、今までの“「見える」をサポートします”というワードがダメだったということ?」と捉えた方もいましたね。
そのため、パーパスの必要性と重要性については、バイウィルさんから丁寧に説明していただきました。
企業としての認知が取れないと、商品のブランディングにおいてもロスが大きいこと。採用も大変になり、優秀な人材獲得が危ぶまれること。そのような幅広い課題を解決するのが、シードが“何のために存在するのか”を明確にする「パーパス」なのだということをお伝えしました。その結果、今までが悪かったわけでも、大きく変えたいわけでもなく、これまでやってきたことを整理して、適切な形にまとめ、これからに繋げていくということなのだと納得してもらえたと思います。
そこからは、経営層のワークショップでも活発に議論がなされるようになりました。それによって、変わらずにやること、今後新たにやるべきことの整理ができたなという印象です。
また、パーパスを策定する前には、市場調査や従業員調査を実施し、良い点も課題も含めて、現在の当社を形作る要素を洗い出しました。耳が痛い指摘もありましたね。経営層にとっては元々気づいていることではあったものの、第三者の視点を活用したことで整理が進み、すんなりと受け入れられたのかなと感じています。
── 新たなパーパスは、社員の皆さまにどう受け取られていますか?
 企業ビジョンサイト(https://www.seed.co.jp/vision/)に掲載されているパーパス
企業ビジョンサイト(https://www.seed.co.jp/vision/)に掲載されているパーパス
信國様:私は、パーパスの策定が終わったあとからこのプロジェクトに参加したため、自身の感想になるのですが。元々あった“「見える」をサポートする”は短く、かつ分かりやすかったので、変える必要はないのでは、という気持ちも正直ありました。ただ、新しいパーパスの中身を見てみると、これまでやってきたことから何かが大きく変わるわけではなく、「『みえる』に向き合う」という、会社の根幹は変わらないのだと理解できました。
そのうえで、パーパスに加えて、経営理念、カルチャーまで策定されたことで、これまではあまり明確ではなかった「会社が目指す姿に近づくために何をすべきか」が整理され、言語化されたので、会社および社員一人ひとりが取るべき行動が分かりやすくなったと思います。
阿部様:パーパスは抽象度が高い概念だからこそ、一見するとよくわからないなと感じてしまう人も少なくなかったと思います。ですが、紐解いていくと決して難しいものではなく、これまでやってきたことを再定義しているものです。それが伝われば、社員の皆さんにも受け入れていただきやすいと思うので、どのように伝えていくか考えているところです。
山口様:「まだみぬ、世界は、美しい」はあくまでキャッチコピーであって、パーパスの本質はそこに込められた想いそのものなのですよね。会社としてやらなければいけないこと、社会やお客さまへの提供価値を言語化したものが、パーパスに反映されているのだということを丁寧に伝えていきたいです。
 (写真左から)佐藤様、阿部様
(写真左から)佐藤様、阿部様
ロゴや資料のデザインを一新したことで、対外的な印象に統一感が生まれた
── 長らく使われていたロゴを変えられたのも、大きな変化だったかと思います。皆さまの印象や、社員の方々からのご意見があれば教えてください。

山口様:私としては、ロゴを変えるというのは一大事でした。私は中途入社ですが、この会社も長いので、やはり愛着もあったのです。そして、ロゴについている“「見える」をサポートします”というスローガンも気に入っていました。
 変更前のコーポレートロゴ
変更前のコーポレートロゴ
傍から見ると、そんなに変わっていないと思われるのかもしれませんが、やはり中の人間からすると明確に変わっているのですよね。ですので、はじめはロゴを変えると言われて、抵抗感があったのは正直なところです。ですが、制作を進めるなかで、コンタクトレンズを模したシンボルや、カラーに込められた意味などを理解し、本質は変わらないのだと感じられました。今では気に入っています。
信國様:ロゴが変わってまだ少ししか経ってはいませんが、お取引先の反応も良好です。ロゴだけでなく、全体的に統一感が出たことも大きいのだと思います。これまでは、たとえば資料ひとつ作るとしても、決まったフォーマットではなく、社員がそれぞれアレンジしたデザインになってしまっていました。今回、PowerPointのフォーマットや、オンライン会議用の背景画像も制作したことで、社外の方から見たときの統一感は格段に上がったと感じています。
佐藤様:洗練されたデザインになったことで、若い世代の方にも受け入れてもらいやすくなったように思います。ロゴで入社する会社を決めるということはないと思うのですが、それでも、採用活動において、さらによい印象を持ってもらえるようになったのではないでしょうか。
また、海外拠点にも翻訳したパーパスと併せてロゴを展開しており、ベトナム語、中国語、英語と準備しているのですが、これがとても好評なのです。海外で行ったイベントでも、お褒めの言葉をいただくことがありました。このような反応を見ても、このブランディングプロジェクトをやってよかったと思っています。
バイウィル:「みえる」に向き合っておられる企業さまだからこそ、ロゴの形、文字の可読性、色などへのこだわりが、他の企業さまと比べても群を抜いていらっしゃったことは特に印象的でした。VI策定プロセスの中でも、「みえる」に寄り添うシード様の姿勢を感じさせていただきましたね。
── 国内外の拠点で、新企業ビジョン(パーパス・経営理念・カルチャー)とロゴのお披露目イベントをされましたが、社員の皆さまの反応はいかがでしたか?
山口様:まずは、小難しい説明をするのではなく、「何かが前向きに変わるのでは」という空気を感じていただくことを目的に、イベントを開催しました。アンケートにおける参加者の満足度は高かったですね。
イベントのため、シードの歴史を振り返るムービーを作成したのですが、「これまでを踏まえて新たに進んでいくぞ」という想いが伝わるように工夫したので、これからへの期待を感じていただけたのかなと思います。
また、本社勤務の社員と、製造部門の社員、グローバルの子会社社員が一堂に会するのは周年イベントくらいなので、そもそも当社では珍しいです。そういった意味でも、すべての社員が空気感を共有しながら、同じタイミングで新企業ビジョンを知っていただく場を持てたというのは意義深いですね。
パーパスと日々の業務を紐づけてもらうべく、管理職層を巻き込んだ浸透活動を推進中
── 社内でのお披露目から対外発信までの間に、バイウィルも伴走させていただきながら、管理職層の方々対象のワークショップを開催しました。イベントよりも近い距離で新企業ビジョン について伝え、管理職の皆さんにも手を動かし考えていただく場でしたが、印象に残っていることはありますか?

佐藤様:全体で5日程、うち、鴻巣の研究所でも2日程で、各回20名ほどの管理職層に参加してもらい、自部門への新ビジョン浸透について考えるワークショップを実施しました。開催してみると、本社勤務の社員と研究所の社員では、日々感じていることや見ている視点も異なることが分かり、バイウィルさんには資料を調整してもらいながら実施しました。
結果として、5日程終了後のアンケートでは、8割以上の管理職層から「メンバーにも周知しました」という声をいただき、実施してよかったと感じています。
信國様:実は現在、コンタクトレンズ業界全体が需要過多になっており、当社でも一部商品において納期遅延が起きるなど製造現場はぎりぎりの状況です。ですので、はじめにワークショップに参加してほしいと案内したときは、「この時期にやるべきことなのか」という意見もありました。
ですが、会社のこれからにとって非常に重要なのでとお願いし、私たちもできる限りの調整をしながら、なんとか製造部門の管理職層にも参加してもらったのです。
そのような状況でも、ワークショップには前向きに参加してもらえたので、とてもありがたかったですね。特に、「自部署に浸透させるためには、具体的にどうすればよいのか」という質問がたくさん出ており、バイウィルさんにはそれに応える資料を追加いただくなど、消化してから自部門に戻ってもらえるよう動いていただきました。その甲斐もあって、社内浸透のファーストステップとして手ごたえを感じています。
また、今回のワークショップは全体を通して積極的に意見が出ていて、とてもよい変化を感じました。場の設計が積極的な参加を促す要因となったのだと考えていますが、前向きな雰囲気で進められたのはよかったですね。
── ワークショップのほかにも、浸透に向けて進めておられることはありますか?
佐藤様:パーパスのポスターを制作して社内でよく目に触れるところに掲示したり、パーパスブックを制作して社員全員に配布したりと、接触頻度を増やすために取り組んできました。現在はパーパスムービーの制作を進めています。
 廊下に掲示されているパーパスポスター
廊下に掲示されているパーパスポスター
山口様:さらに、評価制度も変更し、半期に一度の目標設定にカルチャーを組み込むことにしました。自身の業務と照らし合わせたときに、どのカルチャーを特に大事にしたいのかを各自で考えてもらい、ひとつ決めてもらいます。そして、そのために次の半期で何をするのかを言語化してもらったものを、目標に含めています。
その際、管理職層には、カルチャーを体現することが、経営理念や、会社として叶えたい姿に繋がっているのだということを説明してもらっています。
信國様:ワークショップを経験した管理職層は、メンバーと一緒にパーパスを読み合わせてくれていたり、会議のなかで議題に挙げてくれていたりするようです。カルチャーの存在が日々の業務内容を直接変えるわけではありませんが、まずは意味を知り、自身の業務に紐づけてもらうことが重要だと考えています。社員の皆さんが業務とカルチャーの繋がりを理解し、納得して行動に移せるよう、丁寧にフォローしていきたいです。
 全社員に配布されているパーパスブック
全社員に配布されているパーパスブック
── 社外への発信・浸透においては、「まだみぬ、世界は、美しい」を取り入れたコーポレートCMも放映されましたよね。
山口様:テレビCMでは「人生にコンタクトするレンズ」というフレーズも採用し、幼少期から歳を重ねるまでを、見ている本人側の視点で描くことで、“「みえる」に寄り添う”という私たちの姿勢を表しました。また、パーパスの「まだみぬ、世界は、美しい」も台詞として読み上げたことで、インパクトがあったのではないかと思います。
佐藤様:「シード」という社名での検索数は、CMの放映によって伸びたと聞いています。企業の認知度を上げるという当初の目的に立ち返ると、さっそく意味があったと言えるかもしれません。また、社員から「見たよ」という声をもらったのはもちろん、海外拠点の社員からは、「こっちでも流せないのですか」と問い合わせをもらうなど、社内でも好評でしたね。
コーポレートTVCMの動画はこちらから※Youtubeへ遷移します
https://www.youtube.com/watch?v=EdIgdntFuLw
─── 最後に、今後の浸透や発展にむけて、期待・意気込みをお聞かせください。
佐藤様:特にお客さまへの浸透については、商品パッケージが切り替わってようやく実感いただけるものなのかなと考えています。在庫なども含めると、すべての商品のロゴを切り替えるには2年半ほどかかると見込んでいるため、その頃には社内にも浸透して、企業ブランドとしてよい変化が見えていることを目指し、取り組みを進めていきます。
山口様:このプロジェクトにおける最終的な結果が出るのは、数年後になるはずです。よい結果が出るよう、新企業ビジョンの浸透を私たちの部署の目標にも掲げて、推進していきます。
─── ありがとうございました。
(掲載されている所属、役職およびインタビュー内容などは取材当時のものです)