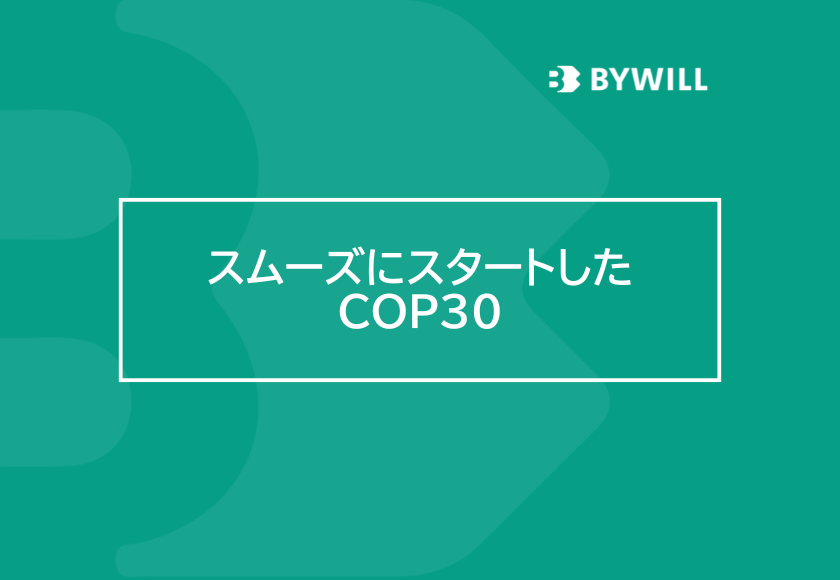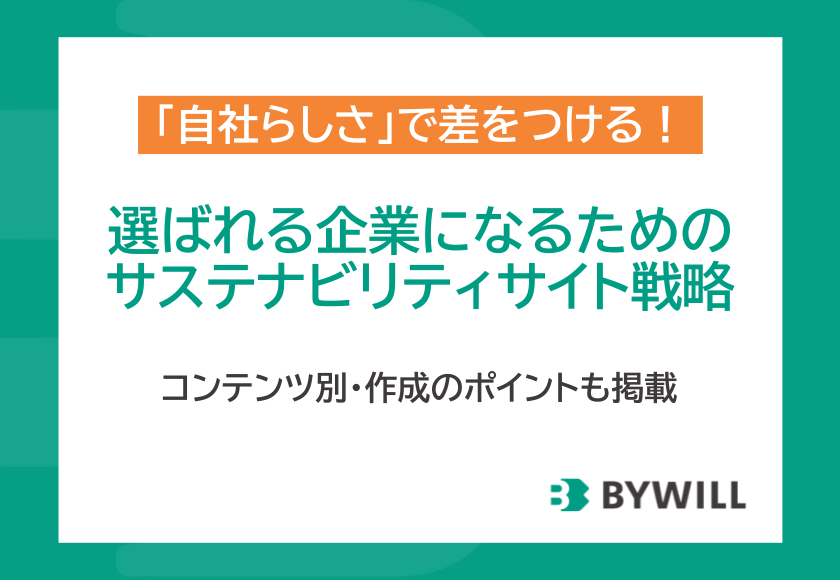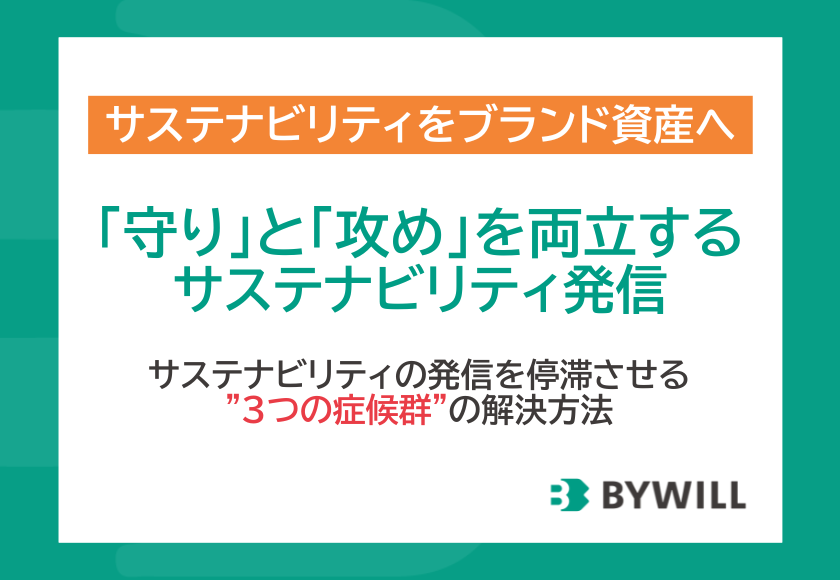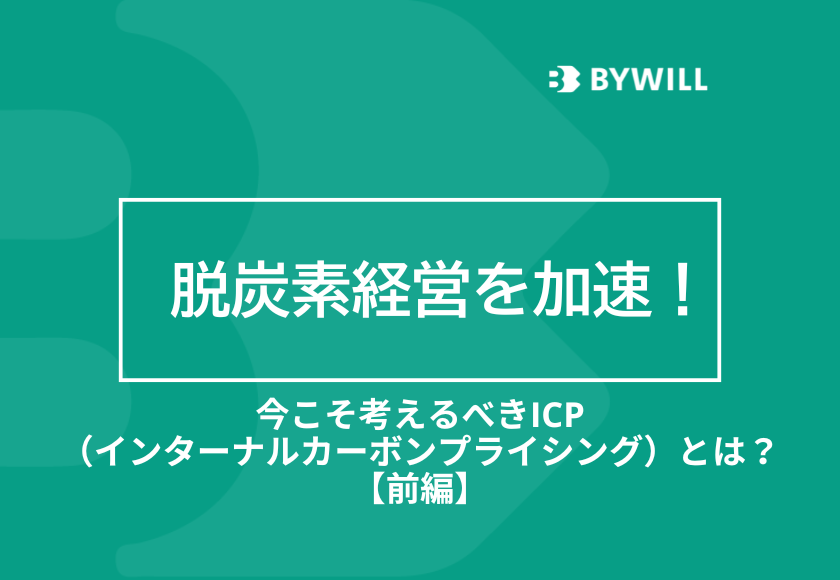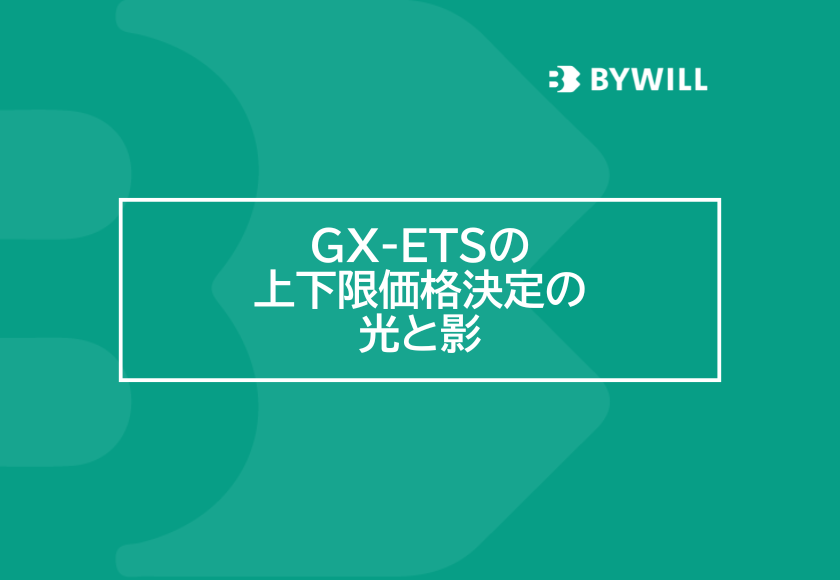11月10日から始まったUNFCCC-COP30(以下、「COP30」)は、これまでと違い、スムーズに始まりました。議長国ブラジルの強力なリーダーシップが功を奏しているようです。初日の迅速なアジェンダ採択の背景についてカーボンニュートラル総研のS.ENDOが考察します。
なお、以下、「COP」は全て、「UNFCCC-COP」の略です。
前回のCOP29はアジェンダ採択に難航
昨年、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29では、交渉初期段階のアジェンダ採択で難航しました。会期自体が2日間伸びたのは、アジェンダ採択の遅れが直接の原因ではありませんが、少なからず影響は与えたと思われます。特に、EUが進める炭素国境調整メカニズム(CBAM)のような貿易措置に係る政治的論点が「アジェンダ闘争」になったとされています。
一方で、最終的に会期が2日間延長された本質的な要因は、気候資金(NCQG:新規合同数値目標)に関して、目標金額、先進国の責任、公的資金と民間資金の割合などの論点で対立が激しかったためでした。今回のCOP30でも、論点が具体的になればなるほど加盟国間での対立が激しくなる可能性があります。
COP30初日で合意した3つの主要アジェンダ
主要アジェンダとして、以下3つの合意がなされました。
・気候資金(NCQG:新規合同数値目標)の実行加速
・排出削減目標(NDC3.0)の野心的向上
・適応に関する世界全体の目標(GGA)の具体的な指標の選定と枠組みの構築
気候資金(NCQG:新規合同数値目標)の実行加速
COP29の時と同様、途上国と先進国の間での対立が起こり得ることが容易に想像できます。COP29で合意に至った下限額3,000億USドルと長期目標1.3兆USドルについて、具体的な実行計画に合意できるか、今後の動きが注目されます。
排出削減目標(NDC3.0)の野心的向上
1.5℃目標達成に必要な2030年までに2019年比で43%という削減レベルとは大きな隔たりがあり、各国が相当の意思を持って高い目標を掲げなければいけないことが分かっています。どの国にとっても厳しい目標設定が求められる中で、省エネをはじめとする技術で先行しノウハウもある日本が先陣を切って高い目標を宣言することを期待しています。
適応に関する世界全体の目標(GGA)の具体的な指標の選定と枠組みの構築
指標の設定とともに途上国での実効性をどう確保するかが争点です。先進国からの資金や技術の援助が求められ、この点も日本が率先してリードしていくことができる分野です。米国がパリ協定からの離脱を表明し、EUは加盟国間の合意を取るのが難しい状況の中で、日本が積極的に関与し、主導する立場を確保する良い機会ととらえることもできます。
合意の背景には議長国ブラジルの包摂的アプローチ
アジェンダ闘争とならなかった一つの理由が、議長国ブラジルがとった包摂的アプローチにあります。
ブラジルは、気候変動を生態系、社会問題、経済発展と一体的に考えるべき、と主張しており、これらを合わせた解決策(Integrated Solution)として進めることを目指しています。例えば、森林破壊の防止は、二酸化炭素の吸収にプラスになるだけでなく、生物多様性の保全や先住民族の生活保障といった複数の便益をもたらすものとして実行していくといった形です。
そして、政府だけでなく、多様な主体の参加を求めています。先住民や地域社会は当然として、地方自治体、民間セクター、金融機関、科学者など、これまで以上に幅広い主体から意見を募ることを目指しています。
さらに、交渉の原則として、脱炭素経済への移行に伴う変化の負の側面を途上国や先住民のような脆弱な主体に押し付けることをしないことを宣言しています。
まとめ:議長国のリーダーシップは継続するか
議長国ブラジルのリーダーシップにより、スムーズにスタートしたCOP30。初期段階として最重要なアジェンダ採択は終わりましたが、交渉はこれから本格的に始まります。COP29のように対立が深まり会期が延びるのかどうか、合意できたとしても骨抜きの内容にならずに野心的かつ実効性を伴った内容となるのか、注目です。
これまでとは異なり、COP30は「実行のCOP(Implementation COP)」とも言われ、目標を設定するフェーズからどうそれを達成していくか、誰がどの程度コミットするのか、そういった具体的な内容を各国に求めていくこととなっています。
議長国がアジェンダ採択で見せたリーダーシップを引き続き発揮していけるか、そして各国が熱量をもって合意に向けて動いていけるか、期待と不安が入り混じります。