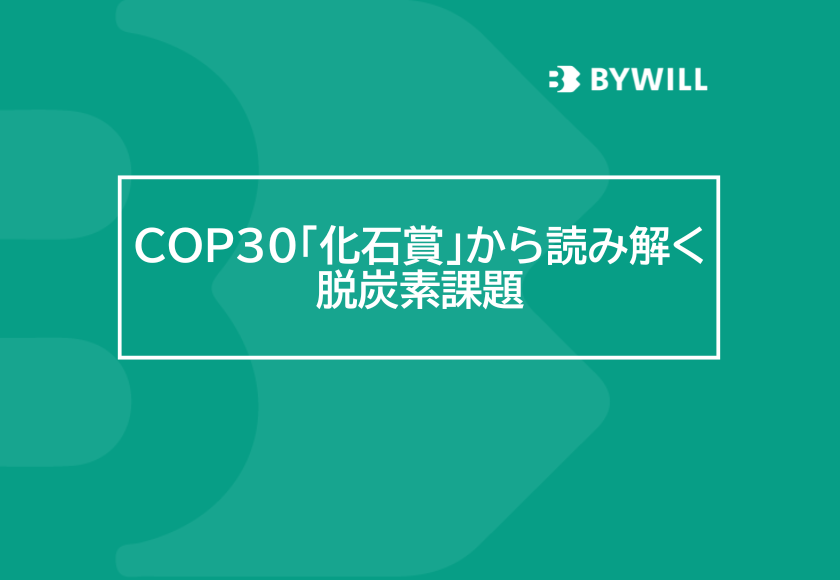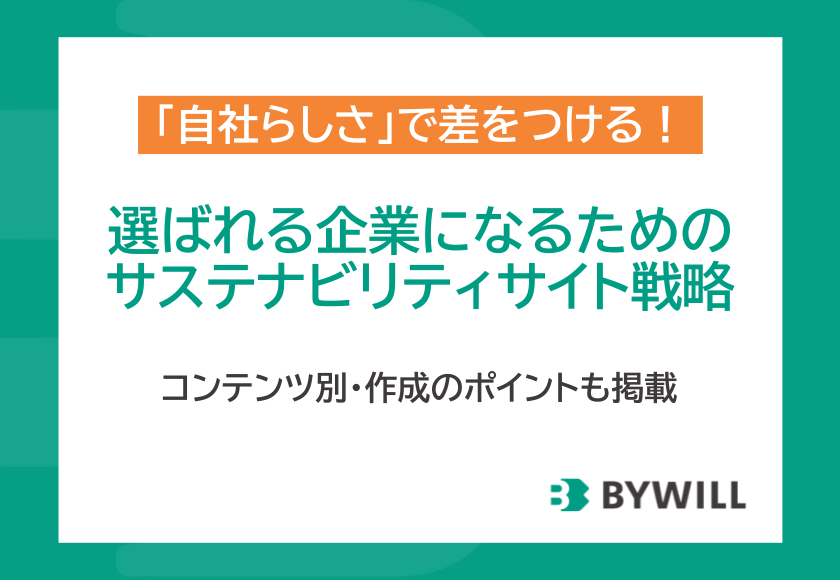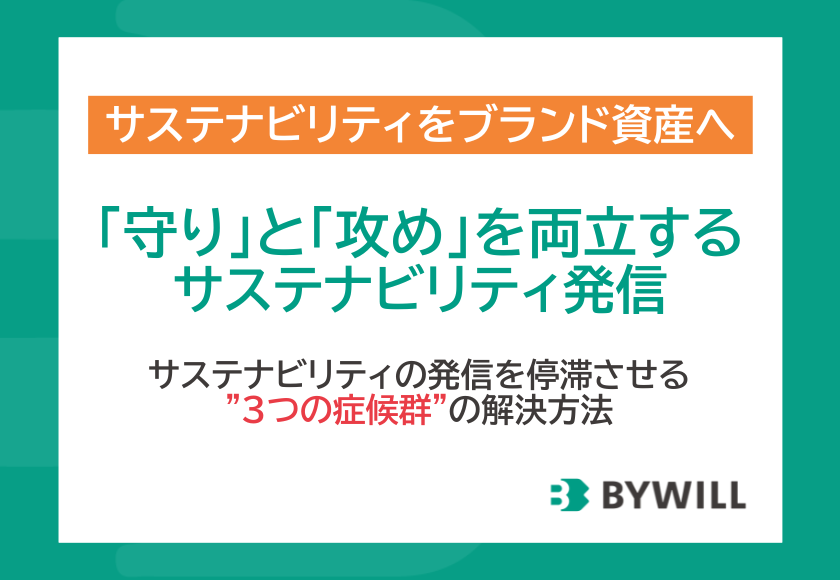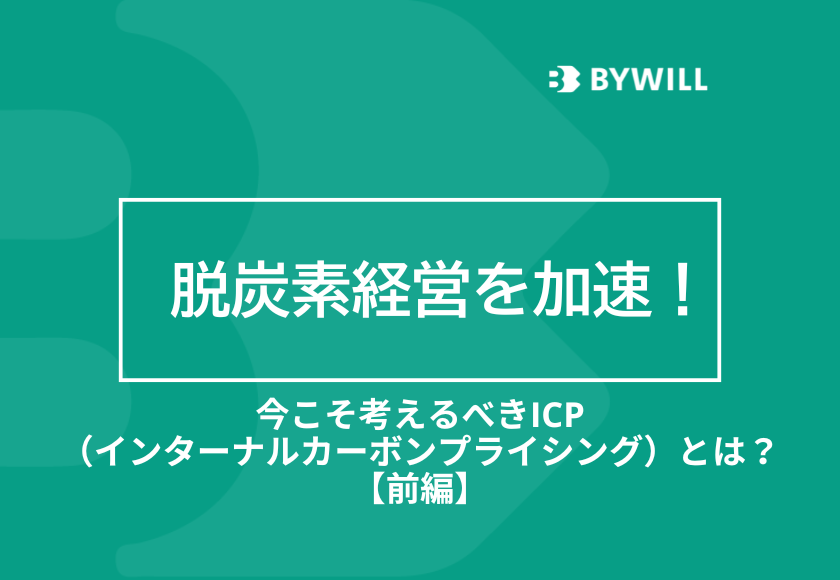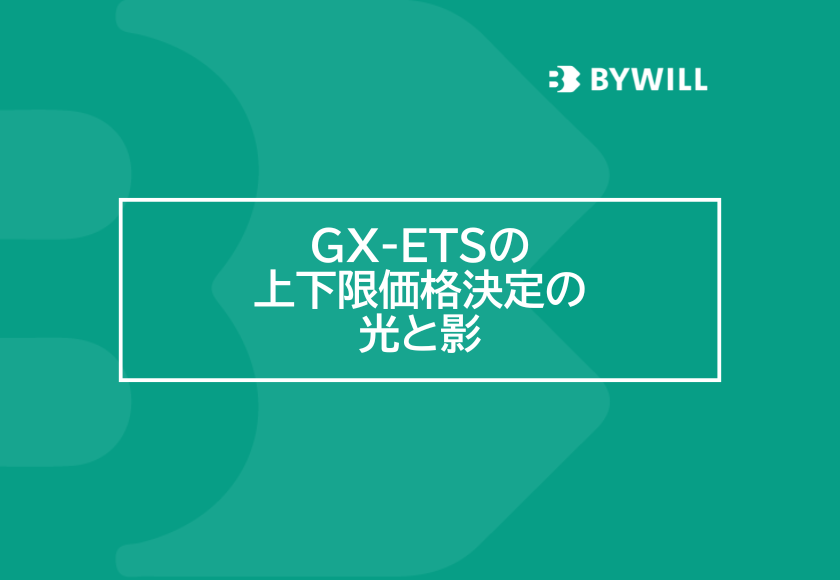日本は、現在開催中のUNFCCC-COP30(以下、「COP30」)において、気候変動ネットワーク(CAN)が発表する「化石賞」を受賞しました。
日本は同賞の常連国として知られていますが、今年の受賞理由は「水素、アンモニア混焼、CCSといった技術の推進が化石燃料の促進につながること等」でした。
地球温暖化対策への取り組みに特に消極的であると見なされた国や企業に贈られる化石賞について、カーボンニュートラル総研のN.UEDAが解説します。
日本の「化石賞」受賞実績
日本は、2010年のCOP16での京都議定書第2約束期間への不参加表明や、2019年のCOP25における石炭火力の維持姿勢など、過去に何度も批判の的となってきました。
近年では特に、「ゼロエミッション火力」などの脱炭素燃料への移行戦略を巡る論争が国際的な注目を集めています。
| COP | 開催年 | 受賞の主な理由 | CAN-Japan プレス |
| COP27 | 2022年 | 2030年以降もアンモニア混焼など石炭火力の延命ともいえる誤った解決策を他国に輸出しようとしていること | 日本が「本日の化石賞」を受賞 1.5℃目標の達成を阻む、石炭火力の延命に対する警鐘(2022年11月10日) |
| COP28 | 2023年 | 「排出削減対策を講じられていない石炭火力の新規建設の終了」を脱炭素の取り組みとして世界にアピールする日本政府の方針 |
COP28にて日本が再び「本日の化石賞」を受賞(2023年12月5日) |
| COP29 | 2024年 | G7は20年間にわたり、発展途上国に対して膨れ上がる気候資金の債務を退け続けていたこと |
COP29にて日本がG7の一員として「本日の化石賞」を受賞(2024年11月15日) |
| COP30 | 2025年 | 水素、アンモニア混焼、CCS(二酸化炭素貯留・回収)といった技術の推進が化石燃料の促進につながること等 |
日本がCOP30にて「本日の化石賞」を受賞(2025年11月13日) |
「ゼロエミッション火力」戦略を巡る国際的な論点
日本が現在推進する「ゼロエミッション火力」戦略、特に水素・アンモニア混焼技術は、電力の安定供給と脱炭素化を両立させる現実的な「移行戦略(トランジション)」として位置づけられています。
この戦略は、既存の火力発電インフラを有効活用し、再生可能エネルギーの導入を補完する調整力を維持できるという点で、現実的な解であると考えられています。
一方で、気候変動ネットワーク(CAN:Climate Action Network)の視点は異なり、この技術が石炭火力の稼働を長期化させ、国際社会が求める1.5℃目標達成のスピード感に逆行するのではないかという懸念を表明しています。
具体的には、初期の混焼率の低さによる実質的なCO2削減効果の限定性や、燃料製造時にもCO2を排出する化石燃料由来の水素・アンモニアの使用が避けられない場合、ライフサイクル全体(LCA:Life Cycle Assessment)で見ると、十分な脱炭素化とは言えないという懸念が、国際的な論点となっています。
LCA(ライフサイクルアセスメント)的視野の不可欠性
化石賞が繰り返し示す警告は、部分的な対策に留まらない、本質的な脱炭素の必要性です。
発電時のみの排出(Scope 1)だけでなく、燃料の採掘、輸送、製造に至るサプライチェーン全体(Scope 2・3)を含むLCAの視野が、真の排出ゼロを目指す上で不可欠となります。
このLCA的視野は、国内政策の設計においても重要です。
例えば、来年度から本格稼働する排出量取引制度(GX-ETS)のインセンティブ設計がScope 1(発電時など直接排出)の削減に限定されている点に留意が必要です。
Scope 1のみにインセンティブが集中すると、企業がサプライチェーンを通じて排出源を他へ移転する「カーボンリーケージ(排出源を規制の緩い他所へ移転すること)」といった部分最適な行動を誘発し、結果として国全体の排出削減という全体最適を阻害するリスクが生じ得ます。
全体を見据え、迅速な行動を
エネルギー安定供給や経済効率の追求は、国、企業にとって不可欠な取り組みです。その上で、真の脱炭素を実現するためには、その努力が「部分最適」に留まらないよう、ライフサイクル全体(LCA)という広い視野を持ち、2050年ネットゼロという未来を見据えることが重要になります。
本当に必要な脱炭素への取り組みを、政策決定を担う国、技術開発と事業構造変革を進める企業、そして消費行動や意識を変える国民レベルのすべてにおいて、スピード感をもって実行していくことも、日本の持続的な成長と地球規模の課題解決に不可欠です。