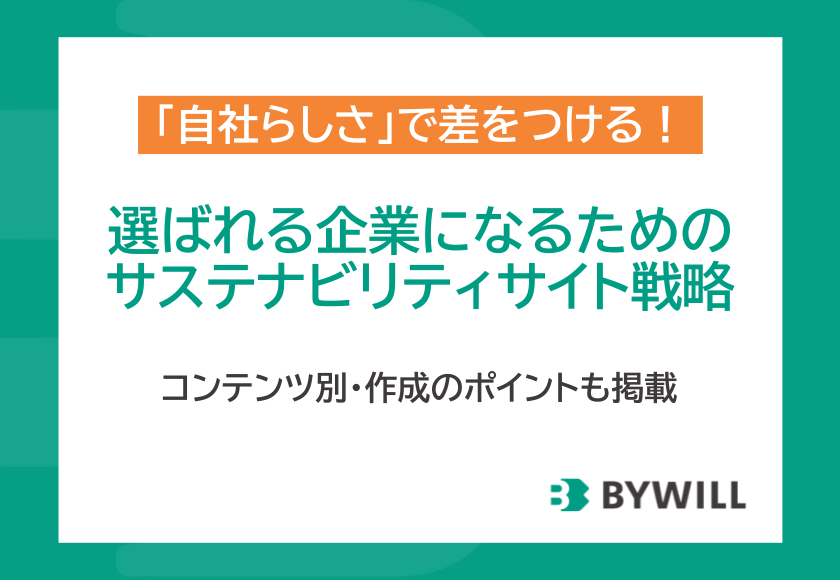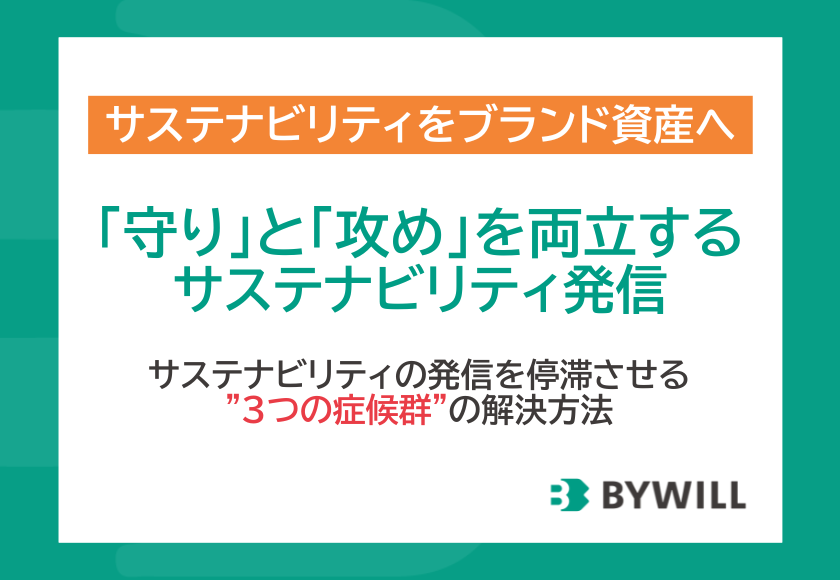はじめに:ブランド構築の3ステップ
前回の記事では、脱炭素商品・サービスをブランド化する際の戦略パターン、「プロダクトブランディング」と「カテゴリーブランディング」についてご説明しました。
戦略パターン(プロダクト vs カテゴリー)を選択したら、いよいよ具体的なブランド構築のフェーズに入ります。ブランド構築は、以下の3つのプロセスで進められます。
1.ブランドコンセプトの策定(価値設計と軸の設定)
2.ブランドアセットの制作(識別記号の具体化)
3.サービスサイトや営業資料への展開(顧客接点での一貫性の確保)
1.全ての軸となるブランドコンセプトの設計と価値の定義
「ブランドコンセプトの策定」は、脱炭素商品・サービスのブランディングプロセスにおける最初の、そしてすべての根幹となる重要なステップです。
ブランドを確立し、ステークホルダーの期待を高め続けるためには、あらゆる顧客接点での「一貫性」と「継続性」が極めて重要となります。この一貫性と継続性を担保する軸となるのが、ブランドの価値を規定するコンセプトです。コンセプトが曖昧だと、商品企画、広告宣伝、営業といった各部門の目指すところがバラバラになり、「機能性で勝つ」「見た目のデザインで差別化する」「結局コストが一番大事」といったように、価値訴求の一貫性が保てなくなってしまいます。
そのため、ブランドコンセプトを策定する際は、単なる「言葉遊び」に留まらない明確なブランド価値定義を行い、社内における納得感のある形で進めることが重要となります。
ブランドコンセプトを構成する4つの概念
ブランドコンセプトは、主に以下の4つの要素によって構造的に構成されます。
1. コアバリュー (Core Value)
ブランド価値を一言で言い表すものです。
これがブランドの軸となり、社内外のコミュニケーションにおける立脚点となります。
2. ベネフィット (Benefit)
顧客が得られる具体的な便益(利益や恩恵)であり、選ぶ理由になるものです。
機能的ベネフィットと心理的(情緒的)ベネフィットに分けて考えられます。
3. エビデンス (Evidence)
ベネフィットをもたらす根拠や事実です。これは主にマーケティングの4P(Product, Price, Place, Promotion)に関連する要素です。
4. リソース (Resource)
エビデンスを創り出すことに効果的な自社の資源や資産です。
この4つの概念を明確に定義し、各要素の間で一貫性を保つことによって、顧客に「(識別記号=ブランドの名前やロゴ)を見たら、こういう価値を持つブランドだ」と認識してもらうための土台が完成します。
コスト増の壁を打ち破る「ベネフィット」の定義
脱炭素商品・サービスの拡販における最大の課題の一つは、「コスト増」です。多くの場合、「脱炭素=コスト増」という認識は、導入時のイニシャルコストに目を向けた近視眼的な視点から生まれます。
この、価格の議論を超えるためには、顧客に「価格が高いから選ばない」ではなく、「価格を超越した価値があるから選ぶ」と感じてもらうための構造設計が必要です。
その鍵となるのが、脱炭素(排出量削減)という機能を顧客にとっての具体的な「ベネフィット」に翻訳してあげることです。具体的には、以下の4つの切り口で、顧客の文脈に合わせた価値を提示します。
① 経済的ベネフィット
- ライフサイクルコスト(LCC)の最小化:初期費用だけでなく、運用期間全体で見たランニングコストの削減効果を具体的に提示します。
- 補助金・優遇税制の活用:グリーン投資関連の優遇措置が適用されれば、実質的な導入コストを圧縮できることを伝えます。
② リスク回避ベネフィット
- 将来の法規制リスクの回避:今後強化される炭素税や排出量取引制度に先回り対応することで、将来的な追加投資や罰則のリスクを回避できることを訴求します。
- 事業継続性(BCP)の強化:災害や外部要因による電力・燃料供給途絶リスクを低減し、緊急時にも事業活動を継続できる体制が確立できることを示します。
③ 競争優位ベネフィット
- サプライチェーンでの選定優位性:グリーン・サプライヤーとしての地位を確立し、大手取引先が求める環境基準を満たすことで、安定した取引維持や新規受注の機会を確保できることを訴求します。
- 先行者利益の獲得:早期導入により業界内でリーダーシップを発揮し、高付加価値なブランドイメージを市場に定着させます。
④ 社会的ベネフィット
- 投資家評価の向上:ESG投資家からの評価を獲得し、資金調達を有利に進めることができます。
- 人材獲得力と顧客ロイヤルティの強化:環境意識の高い優秀な人材を惹きつけ、企業への愛着(ロイヤルティ)を深めます。

これらのベネフィットを整理・優先順位付けし、社員にも顧客にも伝わりやすいコアバリューとしてまとめ上げることが、価格競争を超越する構造設計の第一歩となります。
2.記憶を高めるブランドアセットの制作
ブランドアセット(Brand Asset)とは、企業や商品が持つブランドを、顧客の頭の中に認識・記憶させるために用いる、すべての構成要素(資産)のことです。
表現を変えると、ブランドの核となるコンセプトや価値を、目に見える形や感覚で伝え、競合と明確に区別するための「識別記号」の総称でもあります。脱炭素市場のように、多くのプレイヤーが流入し、機能や見た目の同質化が進みやすい市場においては、自社の商品・サービスに「識別記号」という「焼き印」をつけることが、差別化を実現するためのシンプルな本質となります。
ブランドイメージは、顧客接点における「接触頻度」と「インパクト」の掛け算によって形成されますが、識別記号(アセット)は、この両方を高める役割を担います。
識別記号の重要性と役割
- 記憶性の向上(器としての役割):識別記号(名前やロゴ)がないと、たとえ商品・サービスの意味や価値が一時的に顧客に伝わっても、その印象を強く記憶することが難しくなり、他の競合製品と混同されてしまうリスクがあります。アセットは、価値の記憶を貯めるための「器」となります。
- 直感的な理解の促進:脱炭素技術やサービスは「難解で難しい領域」であるため、覚えやすく、意味が込められたネーミングや、視覚的に魅力的なロゴといった識別記号は、複雑な技術内容を顧客が直感的に理解し、記憶する手助けをします。
- 独自性の表現:アセットは、単に機能や仕様の説明に留まらず、貴社のソリューションが持つ独自の技術、機能、思想を際立たせることができます。
代表的なブランドアセットの4要素
実用性や用途の広がりを考慮すると、識別記号として以下の4つの要素をセットで制作することが一般的です。
- ロゴ・ネーミング:記憶性を高めるための「器」であり、すべての印象がここに紐づく最も重要な要素です。
- タグライン:ブランドの姿勢や存在価値などを、わかりやすく端的に表現するワンセンテンスのメッセージです。パッと見でメッセージを印象に残す役割があります。
- ステートメント:タグラインを補足する文章であり、ブランドの価値観、使命、存在意義などを、ある程度の具体性をもって説明的に明文化します。
- キービジュアル:各種制作物におけるメインのイメージ画像であり、ブランドの世界観を視覚表現に落とし込み、情緒的・感性に訴えかけることで、より強く印象づけます。

ブランドアセットへの「自社らしさ」の組み込み
脱炭素系のネーミングやロゴは「グリーン○○」「エコ△△」といったワードなど、グリーン系・自然を連想させるデザインに収束し、画一的になりがちです。他社との明確な差別化を図るためには、ブランドアセットに「自社らしさ」を組み込むことが不可欠です。
この「自社らしさ」は、企業理念、哲学、価値観、自社ならではの強み、開発背景といった目に見えない思想やリソースを、環境要件と掛け合わせることで生まれます。3.営業の「武器」となる顧客接点への展開
ブランドコンセプトの策定とブランドアセットの制作が完了した後、その価値を実際の顧客接点に展開する「サービスサイトや営業資料への落とし込み」は、ブランディングプロセスにおける第3の重要なステップです。このフェーズの目的は、開発した「ブランドコンセプト」と「ブランドアセット」を最大限に活用し、営業活動における「武器化」を図ることです。
サービスサイト構築におけるコンセプトの活用
サービスサイトは、策定したブランドコンセプトを具体的な顧客体験として提供する場です。コンセプトが曖昧だと、サイトは単なる「カタログ的なサイト」になってしまいますが、コンセプトが整理されていれば訴求力が担保されます。
サイト構成の主要なポイント
- TOP/ファーストビュー(印象付け):ロゴ、ネーミング、タグライン、キービジュアルといった分かりやすいブランドアセットを活用し、顧客に強い印象を与えます。識別記号は、複雑な脱炭素技術の内容を顧客が直感的に理解し、記憶する手助けをします。
- ベネフィット:顧客の課題や、ブランドコンセプトで整理した4つの切り口(経済的、リスク回避、競争優位、社会的)に基づき、具体的な顧客ベネフィットを訴求します。
- 商品・サービス概要(エビデンスの「翻訳」):難解で差別化が難しい脱炭素領域においては、ベネフィットの論拠となるファクト(エビデンス)を、顧客にとって分かりやすい言語やレベル感に「翻訳」して紹介することが重要です。特に設備投資の負担軽減(経済的ベネフィット)や品質維持(リスク回避ベネフィット)につながる根拠を丁寧に紹介します。
- 導入事例:事例の紹介は、顧客の課題と提供するベネフィットのつながりを整理し、経済的、リスク回避、社会的など異なるパターンの事例を網羅的に含めます。
- 資料請求(リード獲得の仕掛け):資料ダウンロード(ホワイトペーパーなど)を設け、問い合わせのハードルを下げることが必須です。

営業資料を通じた価値訴求力の標準化
また、B2Bビジネスにおいて、営業パーソンは最大の「広告塔」になることが多いため、サービスサイトだけでなく営業資料にもコンセプトとアセットを落とし込むことが、営業の武器となります。
コンセプトを反映した営業資料作成(営業の武器化)による効果
- 商品・サービスの基本理解:対顧客同様に、サービスサイトや営業資料に一貫して組み込まれたロゴやネーミングが社員の記憶にも残ることにも加え、会社としてのコミットメントも感じやすいです。(特に、他部署にも拡販や紹介を依頼する場合には有効)
- 顧客への価値訴求:スペックや機能を単に説明するのではなく、整理された4つのベネフィットを通じて、顧客にとっての価値に転換して体系的に説明しやすくなります。
- 営業組織力の向上:ブランドコンセプト(整理されたベネフィット)や、コピー・ビジュアルが統一されることで、提案の再現性が向上します。これにより、専門性の高い領域にもかかわらず、個々の営業担当者のスキルに頼らず(属人化を防ぎ)、誰が話しても高水準な訴求が可能になります。
このように、一貫性を持ったブランドコンセプトに基づき、サービスサイトと営業資料を構築・活用することで、営業パーソンは自信を持って商品・サービスの価値を語り、競争優位性を高めることができます。

さいごに
ここまで、全3回の記事を通じて、脱炭素商品・サービスのブランディングプロセスについて解説してきました。
バイウィルでは、貴社の脱炭素ビジネスに最適なブランディングプロセスを、「戦略デザイン」「表現デザイン」「体験デザイン」の3つのデザインを通じて、一貫してサポートいたします。
サービスの詳細・費用や、貴社に合わせた具体的な進め方などは、ぜひ一度お問い合わせください。
▼サービスの詳細・費用などのお問い合わせはこちらから
https://www.bywill.co.jp/contact
▼関連する資料はこちら(無料)
【お役立ち資料】脱炭素商品・サービスブランディング