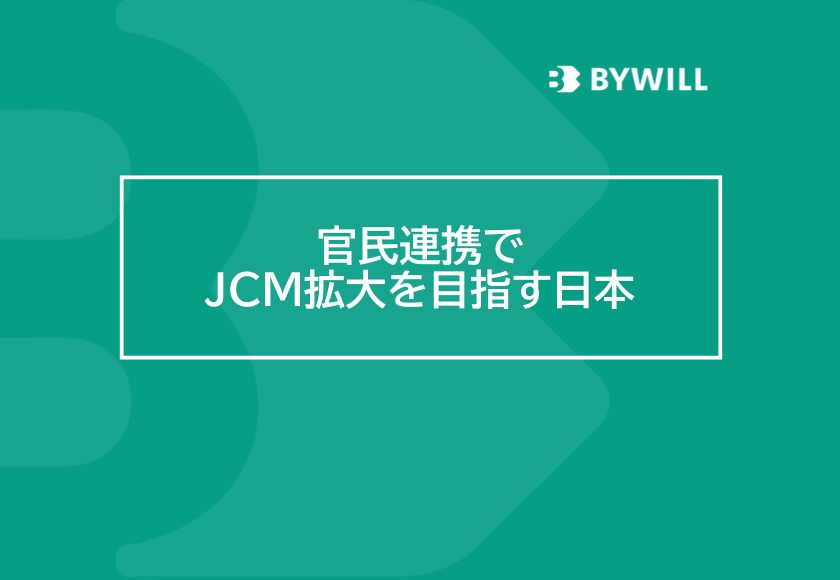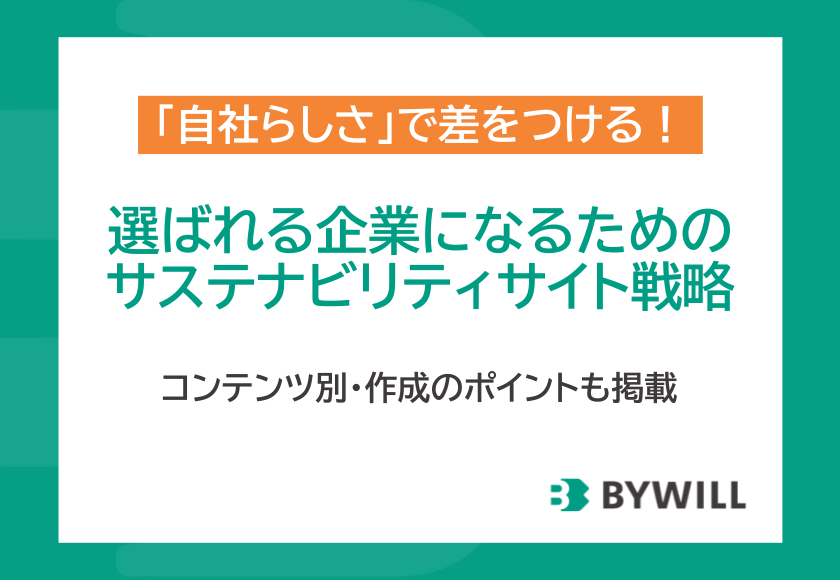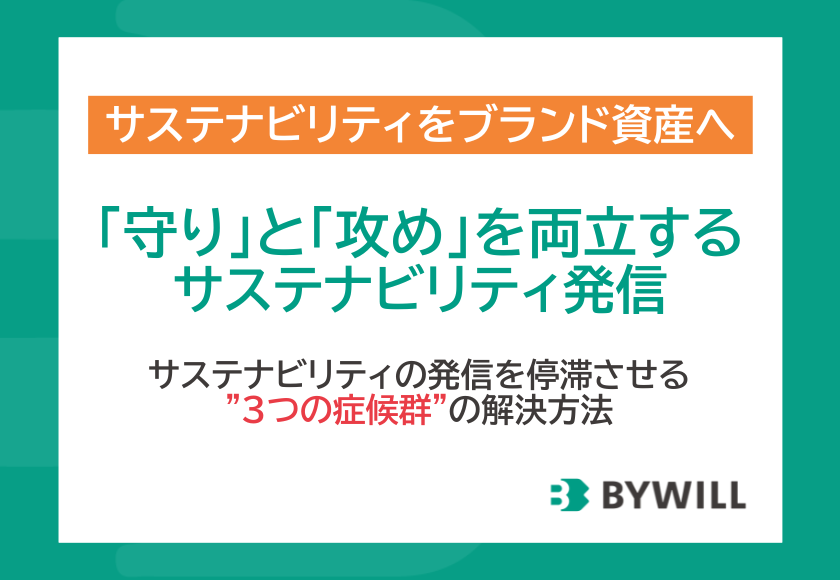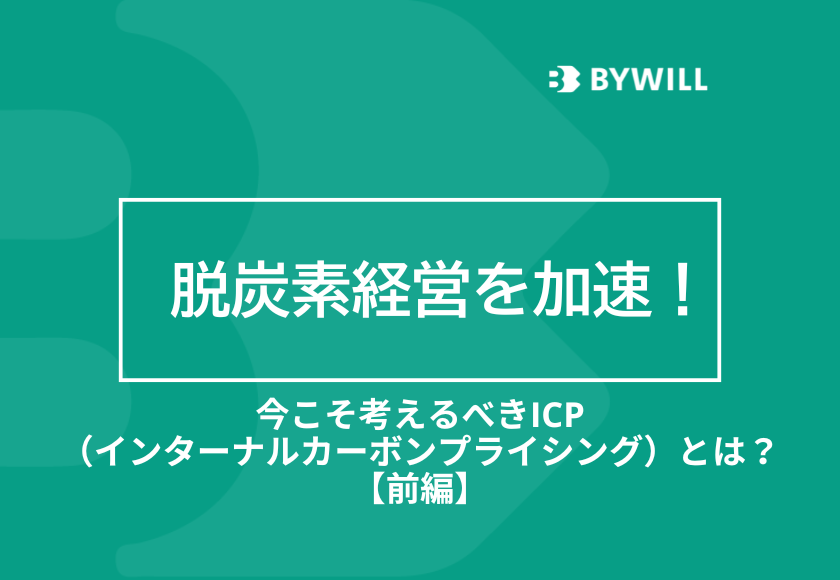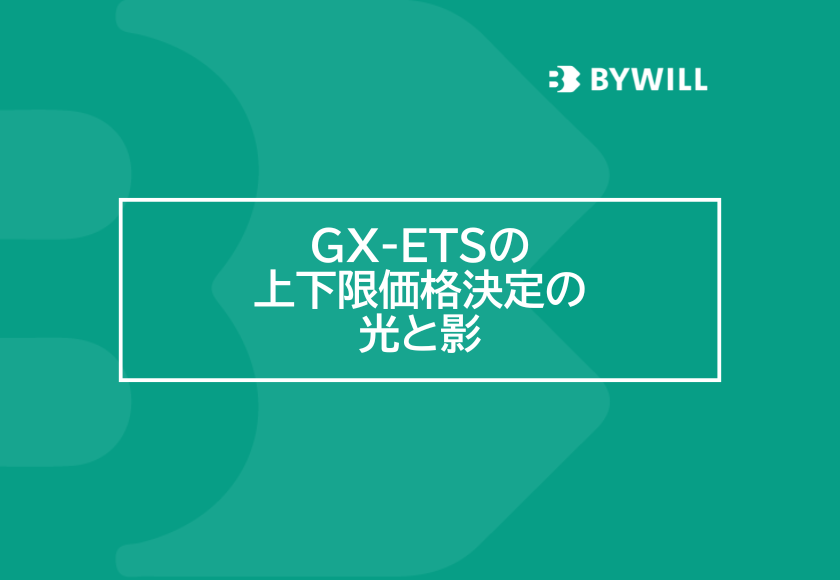COP30にて、日本の様々な企業や団体が加盟するコンソーシアムが二国間クレジット制度(以下、「JCM」)拡大に向けて共同声明を発表しました。
官民連携によるJCMの構築・実施の加速化に向けて、何が必要となるか、カーボンニュートラル総研のS.ENDOが考察します。
なお、以下、「COP」は全て、「UNFCCC-COP」の略です。
COP30で100社超からなるコンソーシアムがアピール
COP30に向けて、農林水産省は食料安全保障に資する温室効果ガス削減技術の海外展開のために、ミドリ・インフィニティ(農林水産分野GHG排出削減技術海外展開パッケージ)をまとめ、その実現に向けた組織として、みどり脱炭素海外展開コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」)を今年6月に立ち上げています。
本コンソーシアムには、官民ファンドの脱炭素化支援機構を筆頭に、井関農機などの農機メーカー、エス・ディー・エス バイオテックのような飼料・肥料メーカー、明治ホールディングスのような食品関連企業に加え、バイオ炭メーカー、スマート農業開発業者、コンサルティング会社、総合商社、金融機関、IT企業、大学・研究機関など、様々な分野の企業や団体100者以上が参加しており、オールジャパンとも言える体制となっています。
COP30では、本コンソーシアム参加企業の有志32社が、「農業」「畜産」「MRV(温室効果ガスの測定、報告及び検証)」「気候資金」の4つの課題に対する各社の取り組みについて共同声明を発表しました。
農林水産省発表:https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/251112-1.pdf
日本は、南北に長く、土壌や気候が多様なため、様々な地域で適用可能な技術を実証できる利点があり、今回の共同声明で発表された技術はアジア各国だけではなく、グローバルでの展開が見込まれます。
官民連携の成功例としてのインフラ輸出
官民連携による技術の海外展開は、発電所建設や橋梁・道路建設、上下水道整備などで、これまで成功してきた実績があります。在外公館や国際協力機構が各国のニーズをキャッチし、基礎調査などを経て、商社や設備メーカー、現地企業などと組んだJVを組成して現地政府に提案する形で、官民がタッグを組んで取り組んできました。また、最近では設備だけでなく、運営および維持管理(Operation & Maintenance:O&M)も重要であり、人材育成なども積極的に取り組んでいます。
脱炭素技術の海外展開においても、官が風穴を開け、民が結集してプロジェクト化する、という勝ちパターンを踏襲することが重要です。そして、それに加えて単品の技術での勝負だけでなく、上記の「農業」「畜産」「MRV」「気候資金」の4つが有機的に連携し、包括的なパッケージとして途上国へ提供することで他国との違いを見せることができます。
JCMの現状
JCMの取り組みは必ずしもうまくいっていないのが実情です。MRVレベルが高く検証費用が高いこと、創出したクレジットの50%以上を日本政府が取得するため企業側が売買できるクレジット量に上限があり利益確保が難しいこと、パリ協定では途上国も削減義務を負う中でパリ協定6条に規定される相当調整により相手国側は自国の削減量からJCM実施分を差し引かなければならないこと、承認プロセスの遅さなどが、その要因と言われています。
また、規模が大きく質の良いプロジェクトは他国との奪い合いとなっている状況も無視できません。
技術+金融+ソフト支援で脱炭素化支援を加速
戦後、アジア諸国と信頼関係を築いてきた日本。初期のインフラ輸出は、戦後賠償の一環として行われてきた側面があり、設備とその調達に係る金融支援が中心でした。それが人材育成などのソフト支援へ広がり、より実効性のある取り組みとなってきました。
脱炭素化についても、JCM実施の過程の中で、技術だけでなく支援対象国の公務員や教育機関、O&Mに携わる企業や人材などへのソフト支援も含めて行うことが期待されます。また、インフラ輸出として典型的な火力発電所についても、代替としての再生可能エネルギー開発や省エネなどの支援も合わせることで、他国にはできない、日本独自の支援の形を作ることが出来ます。
パリ協定のルールは一朝一夕に変えることはないため、ルールの中で相手国にとって実効性のある仕組みをつくること、例えば、相手国の炭素市場の立ち上げや潜在的な炭素吸収源の開発(例えばブルーカーボンの可能性やCCS技術の実用化等)などの支援も併せて行うことが考えられます。