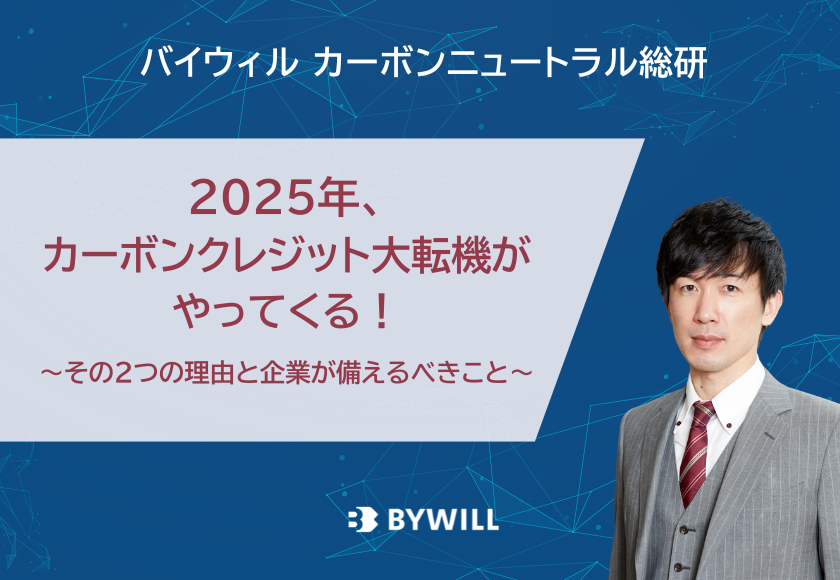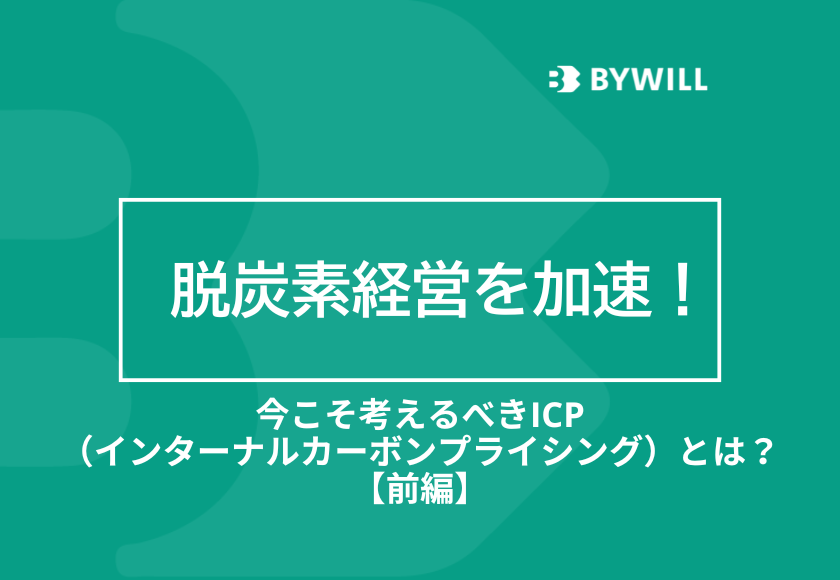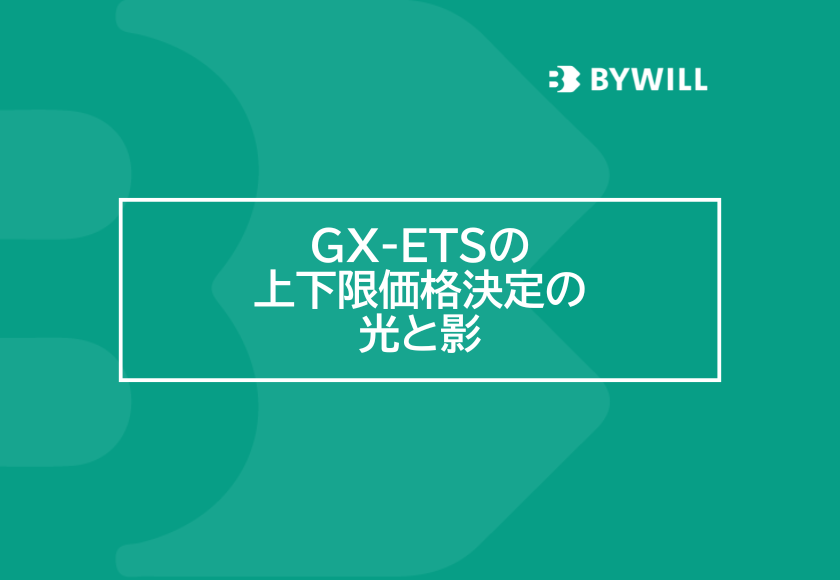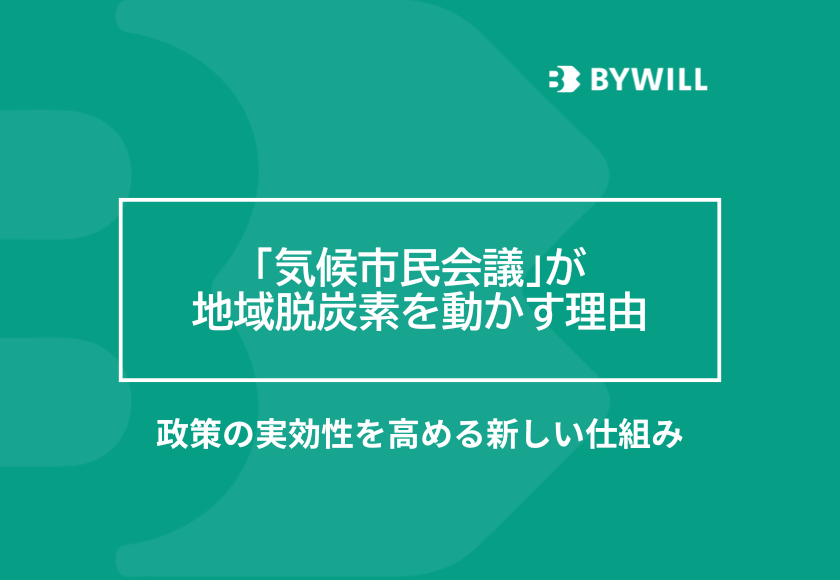バイウィル 代表取締役CSO 兼 カーボンニュートラル総研 所長の伊佐です。
2025年は、世界各国が35年以降を見据えた温室効果ガス排出削減の新たな目標を国連の条約事務局に提出する重要な年です。日本も24年12月の地球温暖化対策推進本部で、35年度に13年度比60%、40年度に同73%減らす案がまとめられました。
そんな重要な意味を持つ2025年ですが、私は断言します。
2025年はカーボンクレジットの活用が急速に進む大転換の年になることを。
私が「2025年はカーボンクレジット大転換」の年になると考える、その理由と背景、そんな大転換に備えて企業が準備しておくべきことなどを解説します。
気候変動・脱炭素対応への“本気度”の変化
どうして、カーボンクレジットが2025年に大転換をするのか、その理由のひとつが「みんなの本気度」。2024年末に、『COP29とは何だったのか? ~検討の概観と、そこから見える1.5℃目標達成に向けた資金循環の今後~』を書いたように、アジェンダはさまざまありましたが、現地参加していた人々が口をそろえていうことがあるのです。それは「気候変動・脱炭素対応への“本気度”が上がっている」ということです。
現在ロサンゼルスの山火事が話題になっていますが、日本の夏も異常な暑さを記録していますし、気候変動による海面上昇により島がなくなる、崖が崩れ落ちるなどといった現実に直面し、これまでは「気候変動に対して、さまざまな取り組みを行うべき」となんとなくふわふわしていた関係者の議論も、今回はとにかく本気度が高く、熱かった。脱炭素に直結しないことにエネルギーを割いている場合ではないという雰囲気が、COP29全体に漂っていたといいます。
こうした雰囲気から、国も企業も、直接的・本質的な環境投資に集中すべきだという要請は、今後ますます高まっていくことが予想される点が理由のひとつ目です。
カーボンクレジットは間接的な環境投資です。自社のGHG排出量を削減する直接投資のほうが、企業は「これだけ削減しました」と開示もできるし、本質的な解決になる。この直接的・本質的な環境投資に集中すべきであるという文脈であれば、カーボンクレジットは後回しでよいはずです。しかし今回のCOP29では国連公認のカーボンクレジットのルールメイクについての採択が行われました。
これまで議論が紛糾していた、パリ条約6条に規定された「カーボンクレジット」のルール、6条2項4項がすんなりと、COP29で採択されたのは「みんなの本気度が上がっている」証だと、私は考えています。
ちなみに採択された内容の概要は下記の通りです。
- 6条2項 国をまたぐような分散型のカーボン取引は、国連主導型のカーボンメカニズムによって運営されていく。ただし、収益分配ルール(SOP)や2%キャンセルルール(OMGE)については、義務ではなく「推奨」に留まる
- 6条4項 究極の高品質クレジットとされてきた除去系クレジットの方法論が、6条4項監督機関による改善を試みつつも、正式に認められた
NDCが達成できない!日本企業が抱える危機感と焦り
ふたつ目の理由は、世界各国および企業が、GHG排出量削減目標未達になるリスクを抱えはじめているという事実です。
世界各国ともに、脱炭素におけるNDCの目標が達成できる見込みが立っていません。言葉を選ばずに言うと、「目標達成は無理だということが確定的である」ともいえるでしょう。自助努力で目標達成が難しいのであれば、「カーボンクレジットを使わざるを得ない」という声が各国から上がっています。それであればと、「どのクレジットだったら、使用可能なのか」などの品質面、オフセット可能な量、クレジットへの投資の的確な手法ほか、グローバルなルールメイキングを国連に委ねることをCOP29で決めたわけです。
世界各国がGHG排出量削減の目標達成に苦労する中、企業の現状はどうなっているのでしょうか。私が交流のある大手企業などは、世界各国と状況は変わりません。実際、気候慈善団体ハイ・タイド財団のマネージングディレクター、アレクシア・ケリー氏は「企業は炭素削減目標を達成するのに苦労しており、何らかの形のカーボンオフセットの使用は多くの企業にとって必要不可欠である可能性が高い」と述べています。「SBTiが米国で存在感を保ちたいのであれば、自らを統治する方法と選択を変える必要があるだろう」とまで同氏が述べたほど、企業は脱炭素対策に苦労しているのです。もうやれることはやったという限界状態の企業も多いのではないでしょうか。
日本でも、これまで自社の努力で「できる削減はしてきた」という企業も多いはずです。私が交流のある某大手企業の方から聞いた話では、「オフセットなしでは、2025年から削減目標達成ができなくなる」といった状況にまで追い込まれているといいます。そのほかの企業も、2027~28年あたりには、削減目標を達成するにはカーボンクレジットを活用し、オフセットをするしかない状況になっていくと見込まれます。
カーボンクレジットを使わないと、削減目標が達成できない!

では、削減目標が達成できなくなった企業は、今後どのような取り組みを行っていくのでしょうか?そこで登場するのが、カーボンクレジットを使った、間接的脱炭素投資です。ただし、日本企業の多くが取得しているSBTiはカーボンクレジットによるオフセットを認めていません。しかし、前述の、気候慈善団体ハイ・タイド財団のマネージングディレクター、アレクシア・ケリー氏による「企業は炭素削減目標を達成するのに苦労しており、何らかの形のカーボンオフセットの使用は多くの企業にとって必要不可欠である可能性が高い」という言葉のように、もはやカーボンクレジットなしでは、GHG削減目標達成は難しいのです。
さて、どうしよう……となったとき、企業はどうするか?
答えはカーボンクレジットを使って、オフセットを導入していくしか術がない、となるわけです。
実際、前述の2025年からGHG削減目標が達成できなくなると語った某大手企業は、今年からオフセットを実施することを決定していました。
これまで、カーボンクレジットを、何の(どの排出源の)オフセットに使ってよいのか、という国際的なルールが未整備だったことに加えて、グリーンウォッシュなどと揶揄されることを避けるために、カーボンクレジットによるオフセットに後ろ向きだった日本企業が、いよいよ、その活用に本格的に乗り出すことになるわけです。大手企業がオフセットをはじめれば、そのサプライチェーン・バリューチェーンにあたる企業もカーボンクレジットを活用しはじめるようになるでしょう。
ルールメイクに時間はかかるでしょうが、国連公認クレジットもスタートしますし、ICVCMやVCMIがカーボンクレジットに対して前向きなコメントも出しているため、「弊社は、こういうルールに則り、こうした方法でオフセットを実施します」と、オフセットをすることを決断せざるを得なくなるのです。
その端緒が、GHG排出量削減目標達成に苦しむ大手企業のオフセットが本格的にスタートする2025年であり、これこそが、カーボンクレジットの大転換期となるのです。
すると、しばらくして、「GX-ETS」などを含めたルールメーカーたちは「もう企業は、それぞれのルールでオフセットしているから、みんな基準はわかっているよね」というように、カーボンクレジットを柔軟に取り入れやすいルールメイクの後押しをするでしょう。つまり、企業が「一定のルールで、カーボンクレジットによるオフセットに依存はしないけれど、こうした方法で削減目標を達成していきます」と宣言するというファクトが先行し、その流れが徐々に容認され、デジュール(必然的に)になるという構図になるだろうと、私は見ています。
そして、2027~2028年には「カーボンクレジット・クライシス」が
では、この2025年カーボンクレジット大転機をきっかけに一体何が起きるでしょうか。
まず起きるのが「カーボンクレジット」の二極化です。「ICVCMのコアカーボン原則(CCPs)に沿ったような高品質のもの≒世界の脱炭素推進に本質的に資するクレジット」と「本質的な脱炭素効果が少なく、グリーンウォッシュの誤解を与えかねない低品質のクレジット」で、徹底的に分類されていくことになるでしょう。
ここで問題になるのは、「高品質なクレジット」はまだ流通量が少ないため、ニーズが高まり価格が高騰する一方で、ニーズの低い「低品質なクレジット」が現在まだ主流で、価格はさほど高くなく、流通量が多いというギャップが生じること。そして、ニーズの低い「低品質なクレジット」は安価だった価格がさらに下がり、淘汰され、姿を消していくことになるでしょう。
そして、その次に起こるのが「カーボンクレジット・クライシス」です。
「GX-ETS」が2026年度に本格化することを考慮に入れると、今年もしくは来年にはトップ企業が先行事例でオフセットをはじめるのは前述のとおりです。その後、トッププライム上場企業を中心とした約500社ほども着手。その事実が世の中に知れ渡ったころ、主要なサプライヤーおよび主要なプレーヤーなどに波及していくでしょう。
ここまでくるのが、2027~28年になると予測しているのですが、このころにはおそらくJ-クレジットが欠乏します。ニーズに対して足りない状況に陥るでしょう。同じく、「高品質な」ボランタリークレジットも足りなくなるでしょう。そしてさらにカーボンクレジットの需要が高騰し、ニーズに応えるには足りないという事実が世間に知れ渡ったとき、お尻に火がつき、カーボンクレジット・クライシスが起きると、私は読んでいます。あくまで、私個人の見解ですが。
2025年、企業が備えるべきこととは
では、いざカーボンクレジット・クライシスが起きる前に、ステークホルダーはじめ皆が納得するカーボンクレジット活用をするため、2025年、企業はどんなことに備えておけばいいのでしょうか。
まずしていただきたいのは「自社にとって最も合理的な脱炭素計画を、カーボンクレジットやオフセットを含めて改めて考え直す」ことです。
日本企業の多くはSBTiやCDPといった認証に合わせ目標を定め、やるべきことを決め、実行することで、ここまで脱炭素に取り組んできました。しかし、本稿の中盤でご説明した通り、2025年あたりから、企業が設定したGHG削減目標が達成できない現実が、実際に訪れます。
だからこそ、再エネなら再エネポートフォリオを改めて組んでみるべきですし、省エネも省エネポートフォリオを再度組んでみてください。各種認証をとるための目標を達成することでいっぱいになった頭を、もう一度整理してみましょう。何にどの順番で投資をしたら、実際にGHGが減るのか、そのなかで「間接的脱炭素」にも投資した場合と、しない場合でコストパフォーマンスはどれだけ異なるのかを検討し直すべきです。自社なりのGHG排出量削減目標達成のためのポリシーと戦略を2025年中に、と言わず、今すぐ見直しましょう。
カーボンクレジットは、「いざ、探そう」としても、すぐに理想のものが見つかるわけではありません。もし、カーボンクレジットをつかったオフセットを行うのであれば、「自社では、どういう条件のクレジットを使うべきなのか」を検討し、実際に利用する最低2年くらい前から投資をはじめておくという目線が大切です。
オフセットをするのであれば、「この条件にマッチした、あの方法論の、あのエリアで作られたものでやるべき」という検証を行い、それが実現できるクレジット投資をする。そして脱炭素事業をおこして、その新しく作った事業で生まれた環境価値をつかってオフセットをするのであれば、ステークホルダーも社会も「グリーンウォッシュ」だと文句は言いません。
と言うのは簡単ですが、実際に自社内のみで行おうとすると、いくつもの壁にぶつかると思います。
そんな際は、ぜひバイウィルまでご相談ください。