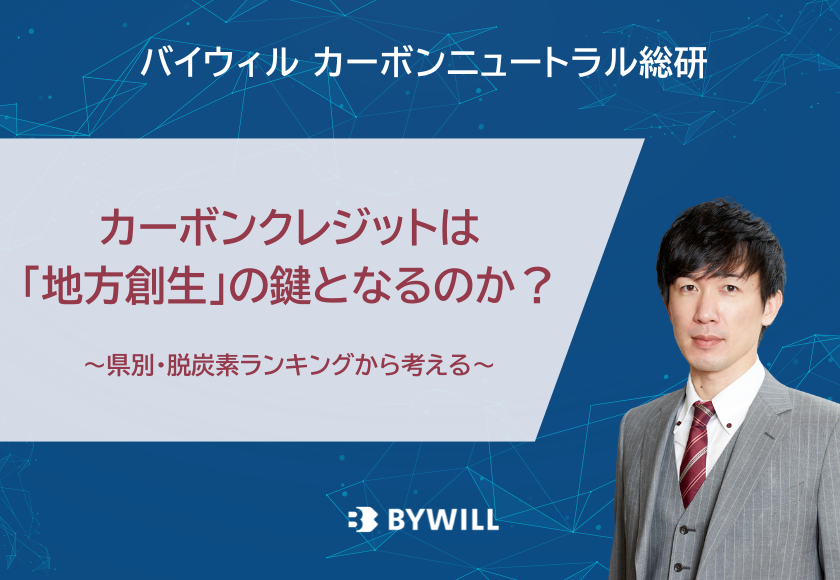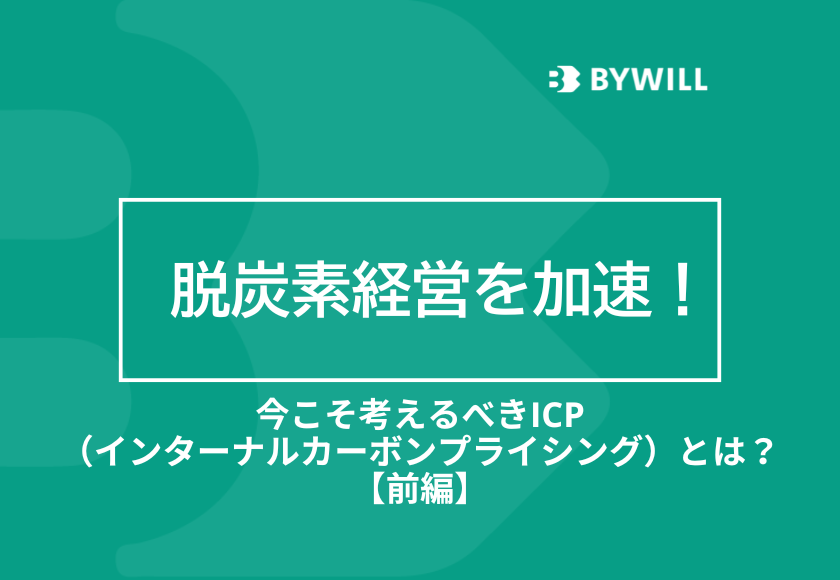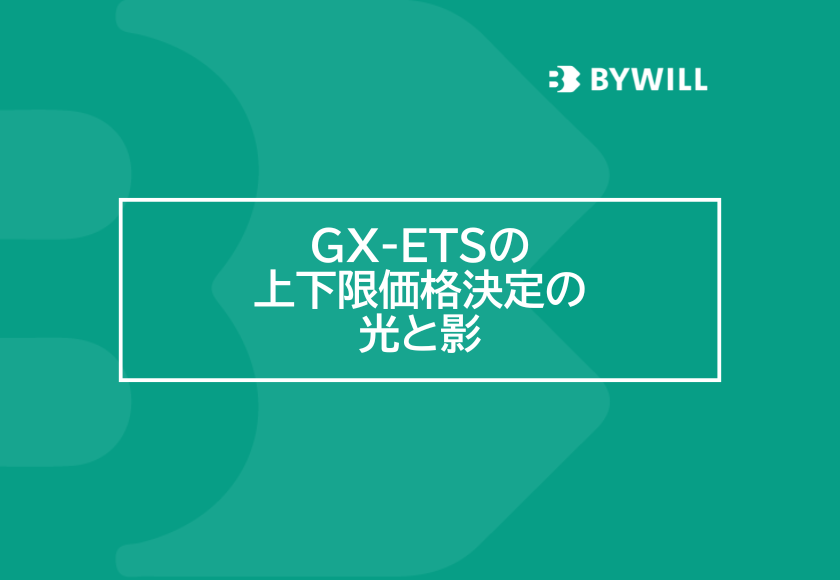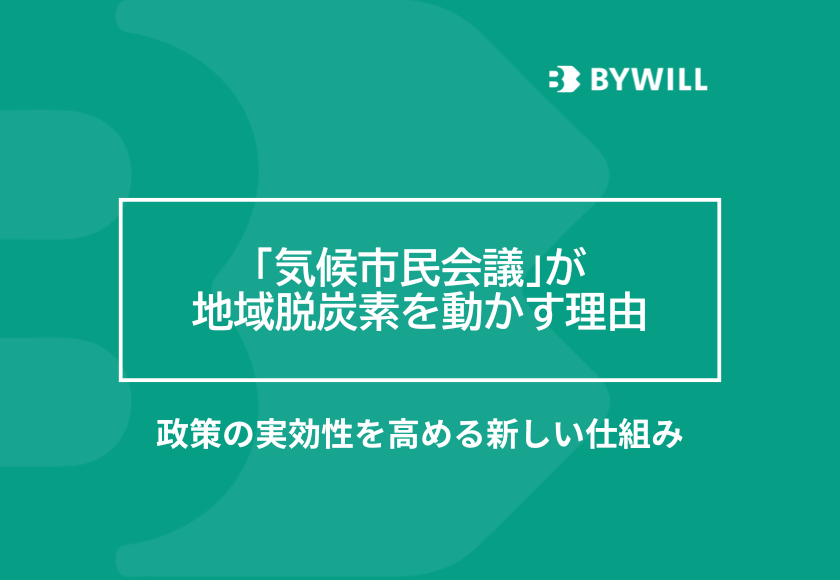バイウィル 代表取締役CSO 兼 カーボンニュートラル総研 所長の伊佐です。
2014年に施行された「まち・ひと・しごと創生法」とともに打ち出された、地方活性化を目指す政策または取り組みを指す「地方創生」という言葉は、今ではほぼすべての日本人が知っているものと言っても過言ではないでしょう。石破首相も一貫して地方創生を政策に掲げ、「新しい地方経済・生活環境創生本部」を設置し、具体策を走らせようとしています。一方で、この地方創生の成功事例は?と聞かれて、具体的に例を挙げられる人は意外と少ないのではないでしょうか。むしろ、石破政権の看板政策として今でも「地方創生」が掲げられていること自体が、逆説的に「地方創生、未だ成らず」の証拠であると言えるのかもしれません。
今回の記事では、このチャレンジが長く続けられながらも、なかなか成功事例が生まれない地方創生というテーマと、脱炭素・カーボンクレジットを関連づけて考えていきたいと思います。
「地方創生」とはサステナビリティである
「そもそも“地方創生”とは?」という話題については、さすがにここでは触れませんが、要は、日本には明確に「経済面を含む活力が足りないがゆえに、サステナブルでない自治体」が多数、存在しているということです。加えて、「地域の特性を活かせば、課題解決が可能になり、現在足りない部分を活性化でき(または、活性化を実現するための政策が実行可能になる)、サステナブルになる」ということです。そこで、まずは各都道府県の活力について考えてみましょう。
そもそも、地域が持つ“活力”とは?
地域の活力を評価するための指標は、いくつも考えられます。
人口、面積、人口密度、経済規模……これらの現状と時間経過による傾向を複数の要素で複合的に「活力」を試算することは有意義ですが、評価が難しく複雑です。
そこで本稿では、内閣府の出している「県民経済計算※」の統計を元に、いわば『県別の一人当たりGDP』を参考指標として地域の活力を考えてみましょう。これは、簡単に言えば、各県の県内総生産を県内人口で割ったもので、各県の経済がどれだけ循環し、活力につながっているかを示す指標のひとつと言えるでしょう。本来であれば、「県」という枠組みではなく、国の行政区画の中で最小の単位である基礎自治体レベルで詳細に分析した方が、よりリアリティのある数値が算出でき、分析も可能ですが、基礎自治体レベルでの算出は、後述する排出量の数値との整合性をとりにくいため、ここでは敢えて県単位で考えていきます。
※2021年確報値:https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/main_2021.html)
最も『県別の一人当たりGDP』が高いところは?

この『県別の一人当たりGDP』の上位10県は、上から東京、愛知、茨城、三重、滋賀、静岡、福井、栃木、群馬、山口の順となっています。これらの県は、住民一人ひとりの生産性が高く、トップの東京では約784万円/人、10位の山口でも472万円/人の水準です。一方で、下位10県は下から奈良、沖縄、埼玉、千葉、高知、宮崎、鳥取、長崎、青森、熊本となっており、どの県も365万円/人以下の水準で、上位県との差は明らかです。
もちろん、この指標と県民の幸福度は関係ありませんし、この指標による順位で県の実状全てを語れる訳ではありません。ただ、これは県の生産性を表すひとつの指標であり、この数値が高いほど経済的に活性化する余地が大きいと言えます。逆に低いほど経済的な活性化の余地・余力が小さく、それゆえに地方創生の要請が高いと見ることができるのではないでしょうか。
根本的な解決をめざす「地方創生」が必要
そして、冒頭で触れた「地方創生の成功事例が意外と思いつかない」理由のひとつは、まさに地方創生に向けた取り組みが、経済的イパクトと継続性に欠けているためだと私は考えています。
例えば群馬県草津市や三重県松阪市などのように、地方でかつての賑わいを失いつつある商店街が、手を取り合ってさまざまな工夫を凝らして町おこしを行い、かつてのような来客が復活した事例が多々あります。これらの取り組みは、まさに地方創生の象徴としてさまざまなメディアに取り上げられ、私もこうした取り組みを心から喜ばしく、尊いものだと感じています。街全体で手をとりあって企画したイベントに足を運び、地元に根差した、血の通った営みに触れる度に、応援したくもなります。
しかし、こうした取り組みが10年以上続いているとか、それによって過疎化が解消されたとか、前述した一人当たりGDPが大きく伸びたとかいう事例には、ほとんど触れたことがありません。その理由は、こうした町おこし的なイベントをきっかけにして、その地域の課題を根本的に解決し、一定の経済インパクトを継続的にもたらすことができていないからではないでしょうか。地域創生を目指すには、一時的な取り組みではなく、根本的な解決につながる施策の連動が必要なのだと私は考えています。
県別脱炭素ランキングを見てみると・・・
ここで視点を変えて、同じく県別に脱炭素の現状を見ていきましょう。まずは県別の排出量を、前述の一人当たりGDPと同様、2021年確報値でランキングすると、上位10県は上から千葉、東京、愛知、神奈川、北海道、岩手、兵庫、広島、大阪、茨城となります、逆に下位10県は下から鳥取、佐賀、奈良、山梨、島根、高知、徳島、長崎、福井、山形です。

さらに、2013年を基準年、2050年をカーボンニュートラル達成目標年として、リニア(等差数列的)に2021年目標を設定した際の、実績と目標の割合をランキングに直して見てみると、上位10県(目標に対して排出量が多い)は上から三重、長野、茨城、山口、沖縄、愛知、千葉、神奈川、岐阜、栃木で、下位10県(目標に対して排出量が少ない)は下から佐賀、熊本、和歌山、長崎、滋賀、鹿児島、大阪、奈良、宮崎、京都となっています。

この結果を見て私が感じたのは、目標に対する実績の割合が下位の10県にも、まだまだGHG排出量削減のポテンシャルがありそうである、ということです。佐賀県は林業のマネジメントが行き届いた県で、日本で最も森林経営計画のカバー率が高い県です。熊本や鹿児島、宮崎も畜産・酪農が盛んですし、和歌山も自然資源の豊かな県です。農業や林業が盛んであること、自然資源が豊かであることは、場合によっては経済的な成長性が低いと受け取られがちなのかもしれません。
しかし脱炭素の文脈では、GHG削減・吸収のポテンシャルが大いにあるということになるのです。森林は、日本にとって貴重なGHG吸収源です。農業は総じてかなりのメタンガスが発生しますが、メタンガスの温室効果は二酸化炭素の28倍もあるため、よく使われる二酸化炭素1トンを意味する単位「t-CO2」に換算すると、メタンガスの発生量を減らすことで、非常に大きなGHG排出量の削減効果を出せます。
地方にとって、まだまだハードルが高い脱炭素
グローバルメガトレンドである脱炭素は、国や企業が取り組むべきものであって、多くの地方にとってはまだまだ「他人ごと」と感じているかもしれません。しかし、視点を変えてみれば、実は地方≒農業・林業などが盛んで自然資源が豊富≒脱炭素ポテンシャルが大きい、という構図も成り立つ訳です。
問題は、経済的な余力が少ないと、脱炭素に取り組むためのイニシャルコストやマンパワーが不足しがちで、なかなか具体的な施策がはじめられない(もしくはそのモチベーションが湧かない)点と、仮に取り組みを始められたとしても、その成果を経済的なメリットに直結させることが難しい点です。後者については、よく「新たなビジネスチャンスにつながる」と言われますし、弊社でもさまざまなパートナーの皆さんと一緒に、そのお手伝いをしています。しかし、脱炭素をビジネスチャンスに直結させられる企業は限定的ですし、やはりまだまだ難易度は高いと言わざるを得ません。
カーボンクレジットは地方にとってビジネスチャンス
そこで、地方の脱炭素において重要な意味を持ち、大きな役割を担うのが、カーボンクレジットです。カーボンクレジットは、一般的に「GHG排出量削減目標を掲げる企業が、削減努力をしたうえで、未達成になってしまった分を補完するための補助ツール」と理解されていますし、それは間違いではありません。
しかし、もっと本質的な役割は、「気候変動対応のための資金循環を促す社会ツール」です。これは、GHG排出量削減目標を掲げる大手企業の目線で言うなら、「追加的、かつ合理的なバリューチェーン外への脱炭素のための間接投資手段」ですし、前述した地方、あるいはそこにある中小企業にとっては、「自らが行ったGHG排出量削減の取り組みによって生まれた環境価値を経済価値化する手段」になるということです。
「GHG排出量削減によって生まれた環境価値を経済価値化する」というこのカーボンクレジットの意味や役割を、これまでに述べてきた地域の文脈でとらえるならば、「カーボンクレジットとは、国や行政、大手企業の脱炭素・環境投資を、地方に引き込むための資金循環ツール」と言えるでしょう。
カーボンクレジットのポジティブな機能を地方に
日本の一大テーマである「地方創生」の課題として、その取り組みの経済的なインパクトの大きさと一時的な取り組みではなく、根本的な解決につながる施策の連動が必要が挙げられるのは先に述べた通りです。そして日本のもう一つの大きなテーマである脱炭素について、地方創生が求められる地域の多くが高いポテンシャルを持っているということも述べました。
つまり、カーボンクレジットが本質的に備えている機能である「気候変動に関する資金循環促進」は、まさにこうした自然資源豊かな地域に、地方創生の起点となる資金を流入させ、継続的な経済効果を齎す効果を持っていることになるわけです。
脱炭素という大きなトレンドと地域課題解決を別々に捉え処理していくのではなく、カーボンクレジットの持つポジティブな機能を軸として地方の課題と繋ぎそれぞれが持つ独自の強みに連動させ、運動論的に地方創生を実現していきたいものです。