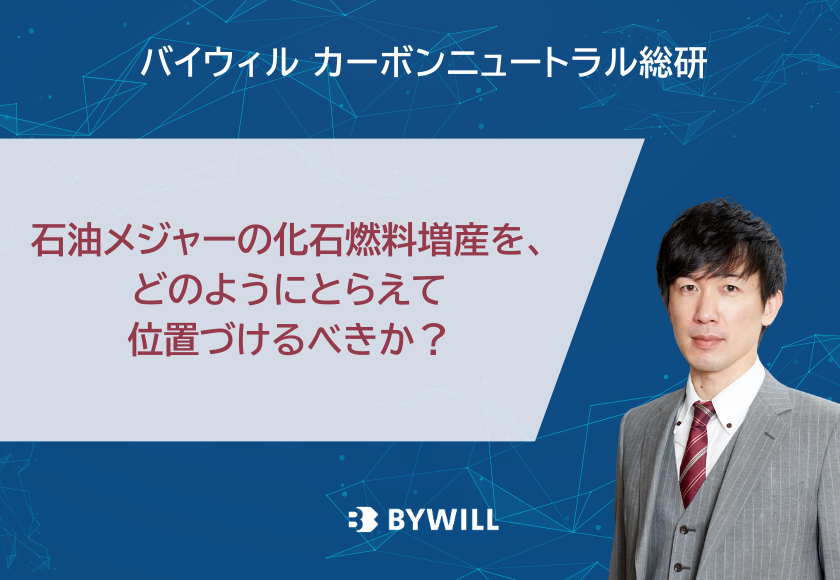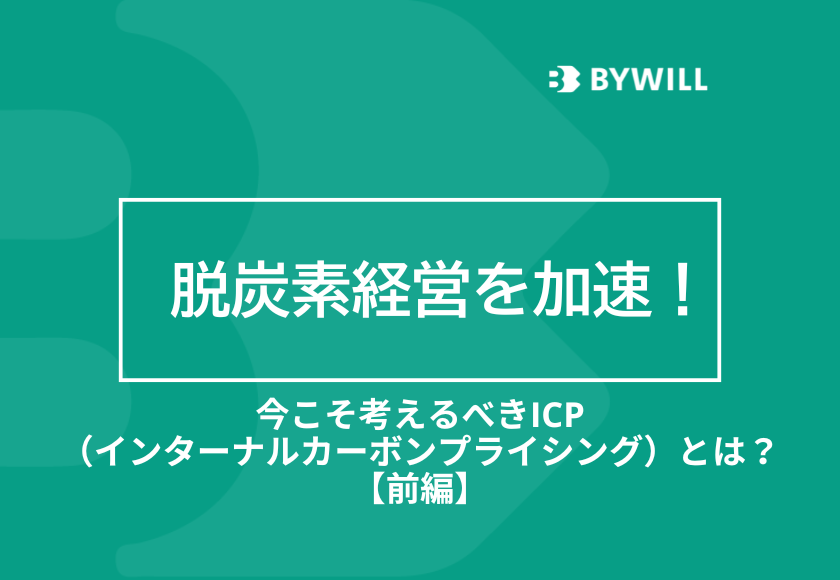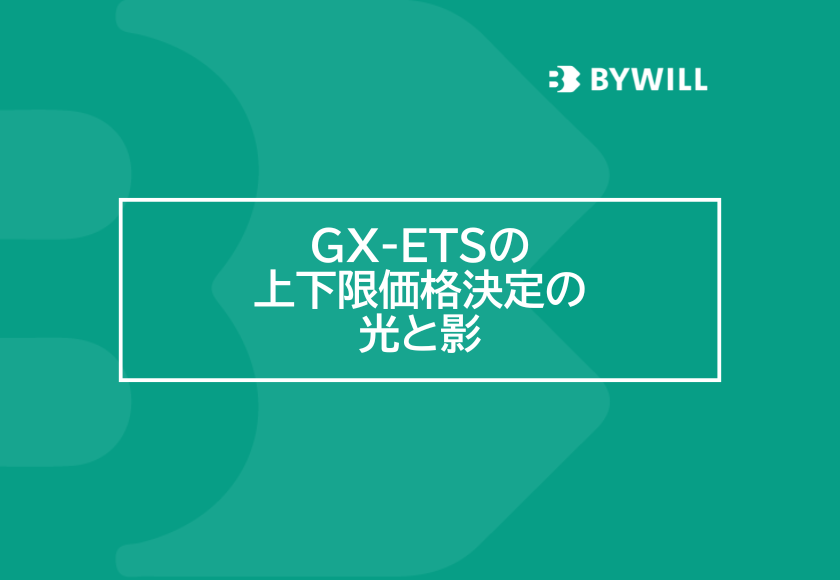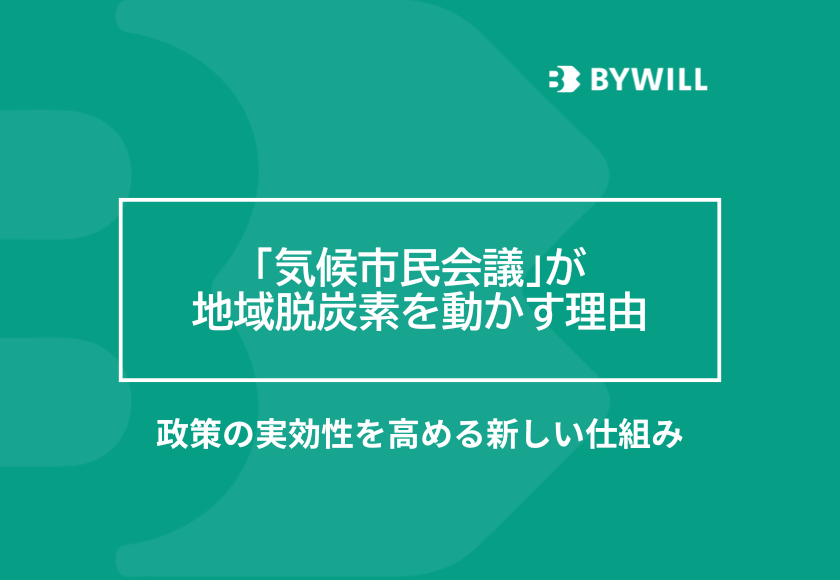バイウィル 代表取締役CSO 兼 カーボンニュートラル総研 所長の伊佐です。
2025年2月26日、石油メジャーであるイギリスのBP社が、石油・天然ガスなどの化石燃料の増産計画を発表しました。
今回の記事は、石油メジャーの化石燃料増産というトピックを、「脱炭素・カーボンニュートラル」の観点からどのように捉えて位置付けるべきなのか?といった点について解説したいと思います。
「安全性」と「安定供給」を優先すべきというメッセージ
2025年2月26日、石油メジャーであるイギリスのBP社が、石油・天然ガスなどの化石燃料の増産計画を発表しました。同社は、2020年に「最も野心的(英HSBC銀行:キム・フスティエ氏)」とされた脱炭素戦略を打ち出し、再エネやバイオ燃料などの低炭素領域への投資を最大50億$/年とするなど、石油メジャーの中でもエネルギー構造転換に対して強い意欲を見せていました。
またBP社は、2023年のCOP23でも主要アジェンダとされた「世界の再エネ化」「化石燃料からの脱却」に沿う戦略を立てていたのですが、新たな中期経営計画では、「2030年までに、石油・ガスなどの化石燃料の生産量を、2019年比で25%削減(日産量195万バレル程度)する」という目標を撤回。低炭素領域への投資は最大50億$/年から27年までに8億$/年未満へ縮小し、逆に化石燃料への投資額は約2割増の100億$/年にするとしています。
この化石燃料事業再強化の動きは、石油メジャー各社とも程度の差はあれど、おおむね共通していて、トランプ2.0の所謂「ドリル、ベイビー、ドリル」発言の衝撃などもあいまって、メディアでは「いよいよ脱炭素化の流れも止まってしまうのか?」という見方が出てきているようです。確かに、これらの動きは、脱炭素化の象徴のひとつでもあった再エネ化の停滞であり、カーボンニュートラル実現に向けたグローバルメガトレンドに逆行している、ととらえることもできます。しかし、もう少し巨視的・俯瞰的に見れば、これらの動きは別の位置づけができるのでは? というのが、個人的な見解です。
まず、冒頭で触れたイギリス・BP社の中期経営計画では、投資の方針転換とあわせて、「化石燃料の生産量」にも触れています。そこには、24年の約235万バレルから、30年には「最大250万バレルとする可能性」があることを示唆しています。つまり、「可能性として、化石燃料の生産量を、2030年までは『横ばい』とするかもしれない」と言っているわけです。
次に、石油メジャーの社会的ミッションです。化石燃料の生産者である石油メジャーは、カーボンニュートラルの世界観の中では「CO2排出量を増やす悪者」だったかもしれません。しかしそもそも、産業革命以降の人類の発展の歴史は、エネルギーの増産と安定供給の歴史でもあります。つまり、石油メジャー各社は、第一に、エネルギーの安全・安定供給を実現することこそが使命です。多くの再エネは、クリーンで安全ではありますが、「安定供給」の面での懸念をまだ拭いきれていません。22年のロシアのウクライナ侵略を発端にエネルギーの供給不安が世界的に生じたことからも、これらは明確です。
先日、閣議決定された日本のエネルギー基本計画でも、いわゆる「S+3E(安全性・Safetyを大前提として、安定供給・Energy Security、経済効率性・Economic Efficiency、環境適合・Environment)を同時に実現する考え方」」が掲げられています。経済発展やDXとともに今後もエネルギー消費量が増えつづけることを前提としたエネルギー政策の第一は、「安全性(Safety)」と「安定供給(Energy Security)」です。こうした意味では、石油メジャーやトランプの方針には、「再エネ化を進めてきたが、それだけではDXや経済発展によるエネルギー消費量増加に対応しきれない。化石燃料もあわせて、まずはエネルギーの増産と安定供給を優先すべきタイミング」というメッセージも込められているでしょう。
経済成長と脱炭素化の両立に向けて
最後に、経済発展と脱炭素化の両立、というGXに於ける最大テーマです。これは「石油メジャーも営利企業であり株式会社。利益を出さなければならない」という表面的な意味合いよりも、もっと世界的な流れをとらえるべきです。
つまり、
- カーボンニュートラル実現に向けた資金循環を生み続けるためには、その原資となる経済的発展が必須
- これまで、脱炭素化の力学は大きく 脱炭素化 > 経済成長 に傾いていた(あるいは、意図的・模索的に傾けられていた)。しかし限界削減費用が急速に増加しており、経済合理性の維持限界が見えてきている
- ゆえに、脱炭素化の力学が、脱炭素化 ≦ 経済成長 に、必然的に働きはじめている

これらを踏まえた私の見解は、イギリスのBP社の戦略転換は、経済成長と脱炭素化を両立させるために必要な、あるいは起こるべくして起こった当然の、「世界的なトランジション」である、というものです。
カーボンニュートラルは、誰も正解を持たない世界的な挑戦です。ゆえに、100年以上続いた経済成長至上主義とは別の力学を働かせるために、かつてないほど強い(あるいは極端な)脱炭素化重視の方針を示す必要がありました。その中で、どのような脱炭素化の手段があり得るのか、有効なのかが大いに模索されてきたのです。
しかし一方で、経済成長なくして脱炭素化の継続はあり得ません。前述の、一見すると「カーボンニュートラルに逆行する」ような動きは、上がりつづける限界削減費用を見据え、脱炭素化を継続するためにも、経済合理性を担保可能な「現実解」を模索しはじめた、ととらえるべきです。
もちろん、誤解のないように言及しておけば、「脱炭素化はもう十分」「模索は終わったので、次は経済成長に振り切りましょう」ということが言いたいわけではありません。日本もその他の先進諸国も、2050年カーボンニュートラルの実現が見えていない以上、省エネも再エネ化も、ネガティブエミッション技術開発と普及も、推進しつづけなければなりません。
お伝えしたかったのは、海外のこうした動向は、「脱炭素投資も、投資対削減効果が最も高い合理的なものに集中し、経済成長と両立させる方向で見直すべき時期がきている」ということです。とくに日本は、世界で最も限界削減費用の推計値が高い国です。いち早く、脱炭素化と経済成長が両立する独自のモデルを確立していかなければなりません。