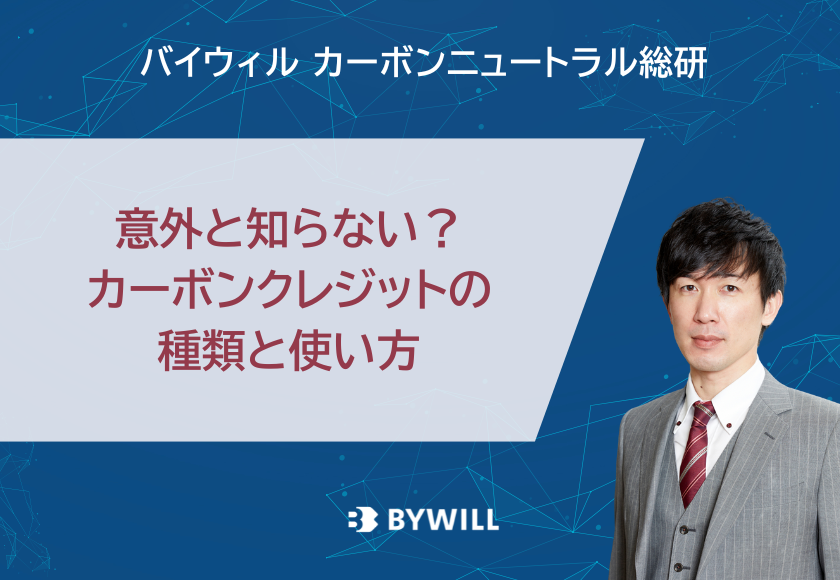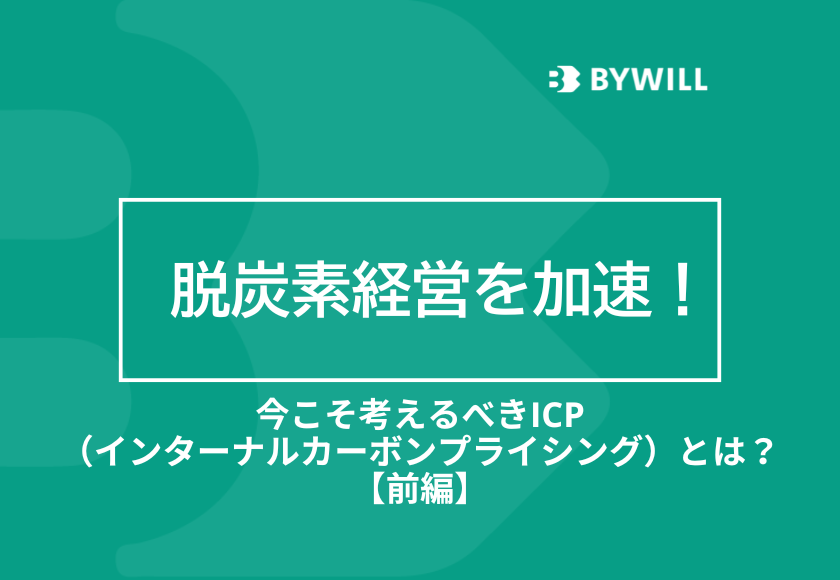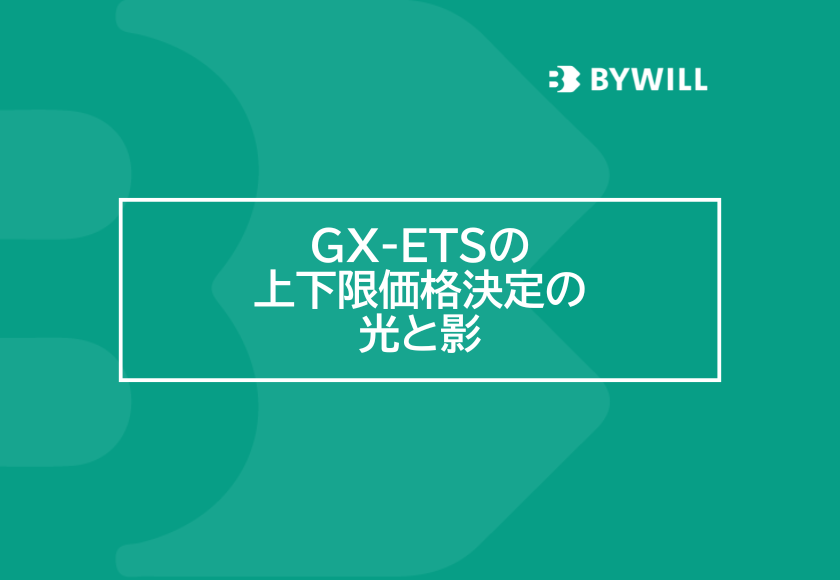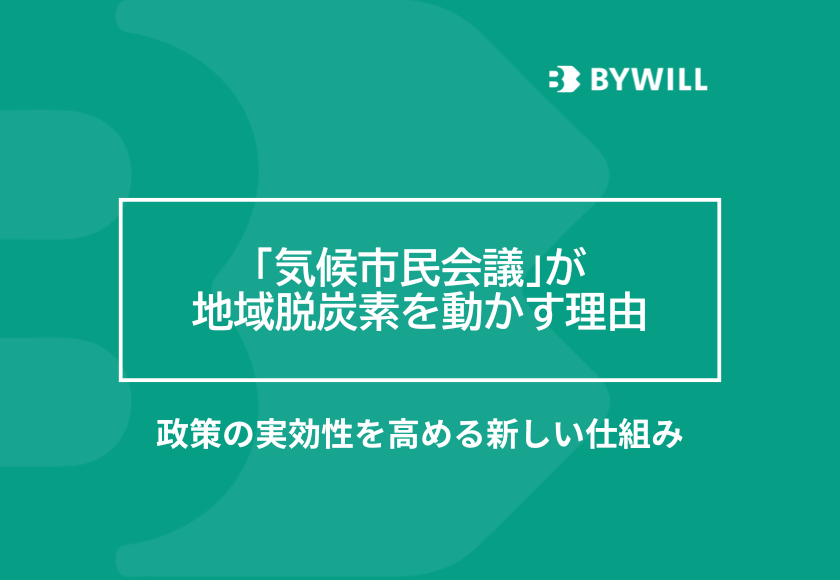バイウィル 代表取締役CSO 兼 カーボンニュートラル総研 所長の伊佐です。
GX-ETS 第2フェーズのルールがかなり明確になってきました。その影響か、国内でのカーボンクレジット取引も確実に活発化しています。国内取引全体からすると一部ではありますが、東証カーボンクレジット市場を見ても、取引数や単価(基準価格)はグングン上がってきています。
どこの国でもそうですが、新しい市場が大きく動き始めるのは、ルールや規制が明確になりはじめてからになることが多いので、この東証カーボンクレジット市場活発化の動きは当然ではあります。しかし、意外なことに、このタイミングになって弊総研に、「改めて、J-クレジットの活用方法が知りたい」「GX-ETSで使ったJ-クレジットは、それ以外にも使えるのか?」「CDP報告用に購入した再エネJ-クレジットは、GX-ETSでも使ってよいのか?」「J-クレジット市場はこれからどうなっていくのか?」などのご質問が多く寄せられています。
最初は、なぜ、いまさらそういったご質問をいただくのかと不思議に思いましたが、お話を聞いてみると、実はとても基本的な部分で認識の違いが起きてしまっていることがわかりました。そこで、今回のブログでは、できるだけわかりやすく、カーボンクレジットの種類と使い方を解説していきます。
「コンプライアンスクレジット」と「ボランタリークレジット」
まずは、「コンプライアンスクレジット」と「ボランタリークレジット」の分類についてです。インターネットなどで検索すると、よくこのように書かれています。
・コンプライアンスクレジット:
国や地域政府などが定める規制・制度におけるクレジット。義務的に使われるもの。
・ボランタリークレジット:
民間団体が運営している制度におけるクレジット。自主的に使われるもの。
さらに、日本におけるコンプライアンスクレジットとは、J-クレジットを指します。J-クレジットについて少し調べると、この表をご覧になったことがある方が多いのではないでしょうか?
この表に書かれている内容は、もちろん何ひとつ間違ってはいません。ただし、これらの知識をインプットした方の多くは、J-クレジットについてちょっとした誤解をされているケースが意外とあります。
- コンプライアンスクレジットであるJ-クレジットは、国が認める信頼性の高いものだが、J-クレジットの種類によって、用途が異なる
- ボランタリークレジットは、民間で認証されるクレジットで、世界中で大量に流通しているが信頼性が低い場合がある代わりに、自由に使える
このような理解をされている方が多数いらっしゃるのです。そのため、GX-ETS 第2フェーズ のルールメイクがおおむね明確になってきて、そろそろ対応を本気で考えなければ、という段階になった今、改めてJ-クレジットについて考えた時に「???」となることが多いのだと思います。そこで、皆さんこれを機に、カーボンクレジットの認識を、下記のように改めてください。
- コンプライアンスクレジット(J-クレジット):国の脱炭素規制対応のために作られたクレジット。
ゆえに、「国内法規制対応」に最適化されており、日本ではSHK制度(GHG排出量算定・報告・公表制度)に沿ったあらゆる国内法規制(温対法・省エネ法・GX-ETSなど)への対応には使えるが、それ以外の目的には基本的に使えない。
にもかかわらず、上記で示したJ-クレジット対応表に「CDP」「SBTi」「RE100」などの記載があるのは、あくまで例外的に、再エネJ-クレジットが「電力証書」と同様の使い方ができるからです。再エネJ-クレジットは、CDPやSBTi、RE100などで「再エネ使用量」や「再エネ化率」の主張に用いることができるのであり、使用方法はこれのみに限られています。 - ボランタリークレジット:企業の自主的なオフセットのために作られたクレジット。
ゆえに、各国ごとの脱炭素規制対応には基本的に使えず、各企業が、自社の脱炭素戦略に沿って採用するさまざまな基準やガイドラインに合わせてGHG排出量をオフセットし、情報開示(排出量の報告)をするために活用されている。
また、認証機関が国や地域政府でないからと言って、必ずしも信頼性が低いわけではなく、方法論によってはJ-クレジットでは得られなかったCORCIAやICVCMなどの適格を得ており、非常に品質・信頼性が高いものもある(そうでないものも一部あり、グリーンウォッシュの温床と言われたりする)
国内法規制と国際規制・ガイドラインのルールの違いを理解し、適切な脱炭素投資計画を
日本ではまだ本格的な脱炭素関連規制がなく、SHK制度に沿って温対法・省エネ法という「柔らかい(厳しい罰則などがなく、実質的な強制力が弱い)」規制が作られているだけです。だからこそ、実際にJ-クレジットを購入のうえ、GHG排出量をオフセットし、報告書に記載するという実務の経験者が非常に少ないことが、こうした認識のズレを生んでいるのだと思います。
別の見方をすれば、これまで日本の多くの企業は、「脱炭素に関する取り組み」はある程度していても、それと「カーボンクレジット活用やオフセット」は別物として考えているケースが多いということです。それにより、J-クレジットはあまり活用されず、今になって冒頭で申し上げたような基本的な知識が不足してしまったり、誤認したりするのでしょう。
しかし、GX-ETS 第2フェーズ始動を控え、そのルールが明確になってきた今、多くの人が「GX-ETS(をはじめとした国内法規制対応)で使うため」に、「J-クレジットを奪い合う」構図が、すでに、かつ確実に起きはじめています。国内法規制対応に使えるクレジットはJ-クレジットとJCMのみです。現在のカーボンクレジットの在庫はかき集めても500万t程度なのに、2027年以降は3,000万t以上のJ-クレジット・JCMが毎年必要になる可能性があります(※)。
(※)日本の排出量(2022年確報値):約10.8億t
GX-ETSの対象企業がカバーする量:60%=約6.5億t
この内、クレジットによるオフセット上限:5%(予想)≒3,250万t
2024年末までのJクレジット創出量(累積):約1,000万t
この内、既に使われた量:約550万t
つまり、2027年以降、供給可能なJクレジット量:約450万t
さらに踏み込んでお伝えすると、今後2026年度にGX-ETS 第2フェーズが始まり、2028年には炭素賦課金も運用が開始され、国内法規制が強化されていく予定です。そんな中、国内法規制とCDPやSBTなどの国際規制やガイドラインではオフセットのルールには乖離があります。国内法規制でオフセット可能なのはScope1です。CDPやSBTなどの国際規制やガイドラインでオフセット可能なのは、Scope2です。このルールの違いから、対象企業(多くは大手上場企業)は、前述のコンプライアンスクレジット(J-クレジット)の定義や用途に沿えば、「国内法規制対応のためのクレジット購入・Scope1のオフセット」と、「従来どおりの国際的な基準やガイドラインに沿った情報開示のための脱炭素投資(Scope2のオフセット)」が重複し、無駄な投資が発生してしまう可能性もあり得ることになります。
そうすると、当然「J-クレジットが、その他の情報開示系の基準やガイドライン(CDPとかSBT)にマッチしていること」が強く求められるでしょう。そして、前述したCORCIAやICVCMの適格をJ-クレジットが獲得する、または、同じJ-クレジットの中でも、方法論単位やプロジェクト単位で高品質なものとそうでないものが分かれてくることもあり得ます。
さらに、もうひとつ、これまでは「脱炭素の直接的投資が優先で、クレジットによるオフセット≒間接的投資は直接投資の後で」というスタンスをとってきた多くの企業が、国内法規制対応のためにクレジット活用を進めると、そのサプライヤーやバリューチェーン内に位置づけられる中堅中小企業群も、これまでよりもクレジット活用やオフセットに前向きになり、クレジット需要が急速に顕在化していくでしょう。
こうして、2027~2028年にかけて、これまで潜在化していたカーボンクレジット需要は急速に顕在化していき、あっという間に「クレジット不足」「価格急騰」という状態になっていくでしょう。この動き自体は、カーボンクレジットの信頼性がしっかりと担保されてさえいれば、大局的には脱炭素に関する資金循環を加速することにつながり、脱炭素は進むはずです。大事なのは、自社の排出削減のための直接投資と、カーボンクレジットなどの間接投資による削減、双方をしっかりと自社の脱炭素投資計画に組み込み、早めに計画を見直すことです。
日本はこれまで、ある意味真面目に「直接投資による排出量削減」に集中してきた国です。だからこそ、不思議なほどカーボンクレジットに関する正しい知識が広がっていません。ぜひ、この機会に、各企業の皆さまには気候変動対応、脱炭素計画の見直しをされることをお勧めします。