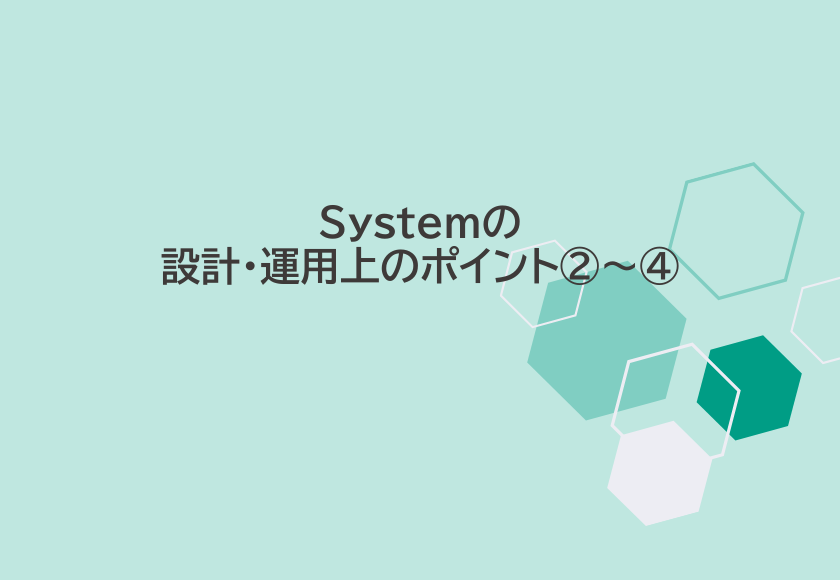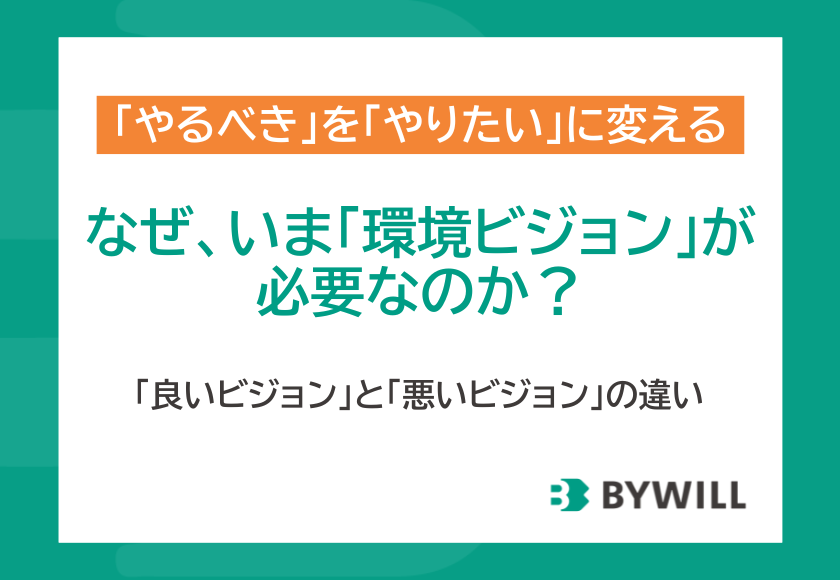こんにちは。取締役の伊佐です。
前回は、ブランドを中長期で本質的に強くしていくための鍵である
組織・業務のsystem設計・運用上のポイント①として、
「整備すべきsystemの全体像を把握すること」
「“社内=ブランド浸透の対象マーケット”と捉えること」
が重要だとお伝えしました。
今回は、system設計・運用上のポイント②~④についてお伝えしていきます。
②優先順位を付け、組織・ブランド浸透の状態に合わせて、適宜設計~運用開始する。
自社ブランドの社内浸透状況や今後の社内課題が洗い出せるような、何らかの指標を持ちましょう。そして、ブランディング開始時から随時定点観測することで、今最も必要とされている社内systemが何なのかを、常に把握しておきましょう。という話です。
当然の話ですが、社内のリソースには限りがあり、必要なものを全てやるという理想の状態にあることは、殆どありません。
また設計・導入したsystemも、運用する側にモチベーションがなければ、結局は形骸化してしまいます。本来意図した効果を発揮することなく、「意味なかったね」「やらない方が良かったのでは」という社内のネガティブな風潮の源泉にすらなってしまいます。
そうならないためにも、指標を持ってしっかり定点観測し、把握した情報を評価した上で、「皆さん(社員)の声に沿って導入しましたよ」という文脈を作ることが重要です。
更に付け加えるならば、こうした指標を設計する段階から、各階層と各部門に対して、「何故そうした指標が必要なのか」「それをどう活用する予定であるか」などを、しっかりと握っておくことも重要です。
ちなみに、弊社の社内調査ソリューション「BranDoctor」も、こうした目的(=インナーブランディング上の健康状態を定量的に把握する)に合致するように設計されたもので、概要は以下のようなものとなります。
『ブランディングのCSC』の概念構造を元に洗い出したブランディングに必要な要素48項目を、「重要度」と「実現度」の2軸を用い、『4つのS』で分析・分類しています。
◎ 「重要度」と「実現度」の2軸
■「重要度」
従業員は、各要素(48項目)をどの程度重要だと認識できているか?
■「実現度」
現在、各要素(48項目)が社内でどれだけ実践・実現できているのか?
◎ 『4つのS』
■Smile (重要度:高 × 実現度:高)
ブランディングを進めていく上での強みであり、今後も”増進”していくべき要素
■Safe (重要度:低 × 実現度:高)
重要度は高くないが実現度は高く、すぐに増進する必要はなく”維持”で十分な要素
■Sick (重要度:高 × 実現度:低)
実現度が低い上に、重要度が高い。
すぐにでも改善して欲しいという気持ちが表れている“治療”が必要な要素
■Sleep (重要度:低 × 実現度:低)
実現度は低いが、重要性も低いという意味で、
将来的なSickになりかねない“予防”が必要な要素
一見表面化していなくても、ブランディングのボトルネックになっている潜在課題が存在するケースは非常に多く見られます。このように整理することで、常にブランディングの社内課題を把握し、system設計や導入・運用の優先順位を付けるためのツールとして多くの企業様に活用いただいています。これを読んだ方も、自社でこうした指標を設計・導入される際は、参考にしてみてください。
③運用すべき必然性を高め、維持する。(必ず運用される状況を作る)
この「運用すべき必然性を高める」というのは、場合によってはsystemを精緻に設計することそのものよりも重要です。理由は先ほども述べたとおり、どのようなsystemも、運用する側に運用するモチベーションがない限り、意味のないものになってしまうからです。
「運用すべき必然性を高める」状況をつくるためには、
以下のようなアプローチが有効です。
■リスクアプローチ:
運用しなかった場合のデメリットを明確に提示することで、運用しなければならないという認識を運用サイドに醸成する
■チャンスアプローチ:
率先して運用することで、どれだけのメリットがあるかを具体的に想起させることで、運用したいという意欲を掻き立てる
■フォースアプローチ:
罰則や人事考課などを代表とする強制力を働かせることによって、運用主体が運用せざるを得ない状況を創る
■スキルアプローチ:
運用者の運用スキルを担保することで運用負荷を軽減することで、運用・定着の障壁を下げるなど
大事なことは、これらアプローチ法を適宜、多角的に用いること。
運用コストが高すぎず、適度に効果が実感できる状況を具体的に目標設定していくことです。
④期間を定め、systemやその運用法をブラッシュアップしていく。
非常にシンプルな話で、業務・組織のsystemは、どれも一度設計・運用開始したら、それが即座に理想的に機能し、効果を発揮することは難しいのです。だから、それを前提としたsystemの運用期間を設け、その都度必要なブラッシュアップをしていくのです。
大事なことは、「system設計の柔軟性」と、「system運用の強制力」のバランスを適度に保つこと。
「設計の柔軟性」が低いと、一度導入されたsystemが機能不全を起こしていたとしても変更されずに、結果的に「運用の強制力」が強すぎて、かえって形骸化を促進してしまうことになります。
逆に、「設計の柔軟性」が高すぎると、状況に合わせてコロコロとsystemが微修正されることで、結果的に「運用の強制力」がないと認識される状況になり、これも形骸化を促進することになってしまします。
大事なことは、これらを前提に於き、systemの対象となる組織の規模や複雑さ(部署や階層の数)、文化や風土、既存の仕組みとの整合性、導入システムの運用難易度などの負荷量・・・などなどを勘案し、適度なバランスをとることです。
今回も長くなってしまいましたが、ここまでで「我々が考えるブランドとは?ブランディングとは?」の骨子は粗方お伝えすることができました。
次回は、これまでの内容の総括をしてみたいと思います。