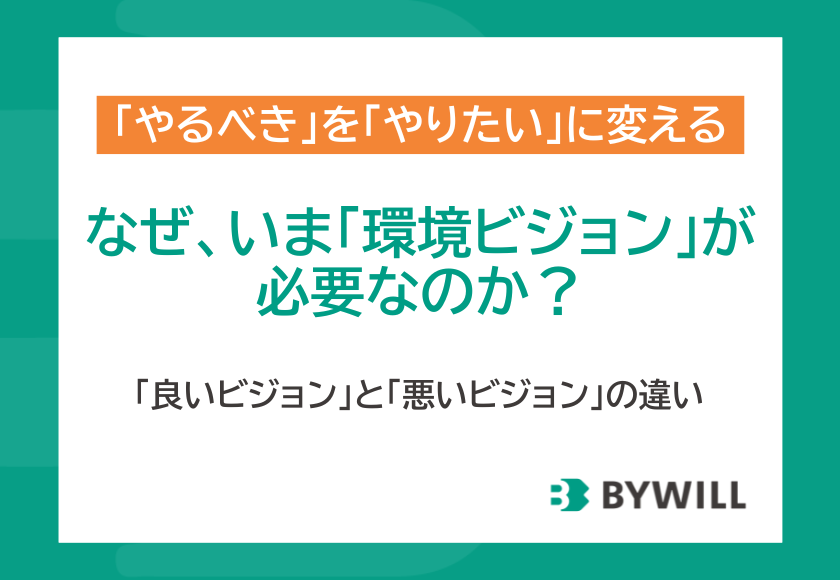マクセルと言えば、国内初の国産アルカリ乾電池生産や国内初のカセットテープ商品化などを手がけるmaxellブランドで、広く認知されている会社だ。しかし、2017年10月に日立グループから独立し社名を変更。さらには、事業ポートフォリオ変革の真っ只中にいる。この大きな変革のタイミングで、マクセルはどのようにリブランディングに取り組んでいるのか。「組織改編前のブランド」「組織改編後のブランド」「マクセルグループとしての成長戦略とブランド」という3つのフェーズに分けて、具体的な取り組みが披露された。
【マクセルホールディングスHP】https://www.maxell.co.jp/
各回の内容は以下である。
前編:マクセルグループから学ぶ、『リブランディング』で経営層が心得ておくべき5つのこと(背景)
中編:マクセルグループから学ぶ、『リブランディング』で経営層が心得ておくべき5つのこと(独立後)※今回
後編:マクセルグループから学ぶ、『リブランディング』で経営層が心得ておくべき5つのこと (今後)
日立の冠が取れてわかったのは、「maxell」の圧倒的な認知度の低さ
平氏:マクセルが日立から独立した2017年10月以降、グループ会社を増やしていきました。そんな中、「マクセルホールディングスは大きくなっていくけれど、一体どこに向かっているのかわからない」と不安を抱える社員が多くなりました。
またリクルーティングにおいては、独立前は日立グループの一員ということでブランドに助けられていた部分が大きかったのですが、マクセルという名前に変わった途端、苦戦を強いられたという現実があります。

そういった背景もありブランド専任の組織は作られました。私を含めて、ブランディングの業務経験などないメンバーばかりが集まりました。内訳としては、営業や経営戦略・技術者・新入社員、様々なメンバーで構成されています。
また、ビジネス領域の拡充を目指すMBP(マクセルビジネスプラットフォーム)という戦略により、『GSユアサ特機事業』『マクセルイズミ』『宇部マクセル京都』など、複数の会社がマクセルグループの一員になりました。
そこで、最初にしたことは、マクセルの認知度調査です。結果は、驚愕するようなものでした。20代の認知度は3割を切っており、30代は約半数。ということは、10代に至っては、ほぼ知られていないのではないかと大きな危機感を覚えました。
また、マクセル製品と聞いてイメージすることは、やはりカセットやディスクなんですね。ICカードや機能性インクを手がけていることなど、ほとんどの方が知らないという散々な結果が突きつけられました。
若年層の認知が低い上に、現在営んでいる事業については正しく理解いただけていない。では、どう認知させていくのかということで、4象限で取り組みを整理し検討していきました。横軸に年齢、縦軸に認知度と指標を置いて考えました。

例えば左下、『認知の獲得』です。若年層でマクセルのことを知らない方々のゾーンです。とにかくマクセルのことを知ってもらおう、ロゴを見てピンときてもらおうという活動がメインだと考えました。
そして右上は『理解度の促進』ですが、マクセルという名前は知っていただいているものの、「カセットだよね、電池だよね」という方々に、現在のマクセルの事業の強みや戦略を知っていただくこと。
ただし、その中でも重要だと考えたのは、真ん中の部分、従業員です。マクセルの将来が見えないと思っている従業員だらけでは、いくらブランディングの活動をしても、浸透はしない。対外的なブランディング活動と両輪で、従業員が中心となってマクセルの良さを発信していけるようにしなければと考えました。
小学生向け出前授業に水族館のネーミングライツ、正しく認知度を上げる取り組みの数々

具体的な取り組みをご紹介します。20代での認知度が3割を切っている時点で、ティーン・小学生はもう知らないだろうということで、例えば、小学生向けの出前授業。あとは、夏休みの宿題を終わらせたい親子向けのイベントです。小学生の親御さんは30代くらいが中心の為、親御さんへの認知度を上げるということも狙いに含めています。
品川駅前にあるマクセルアクアパーク品川という水族館のネーミングライツも、取り組みのひとつです。ただ冠がついているだけではなくて、マクセルの最新鋭プロジェクターを使った、イルカショーでのプロジェクションマッピングなど、まさにマクセルの事業とのシナジーが実現した水族館になってきています。これは非常に良い事例に育ってくれていると思います。

社内向け活動の1つは、ブランド情報誌の作成でしょうか。社内報と誤解されることもありますが、社内報は全てイントラネットで開示しているので別物です。製造現場の皆さんは毎日パソコンを開かない現状があるため、ペーパーレスの時代に逆行するようですが、全員に紙で配布しています。家に持ち帰ってもらいますので、本人だけではなくてご家族にも読んでくれればという気持ちも込めています。
 <マクセル株式会社 ブランド戦略統括本部 平 健介氏>
<マクセル株式会社 ブランド戦略統括本部 平 健介氏>
伊佐:ありがとうございます。組織改編後・独立後の取り組みについて、具体的にお話いただきました。最近はリブランティングについてのご相談も増えてきていますので、ここでは、リブランティングの際に起こりがちなことと、有効な対策について、広くお話できればと思います。

起こることはやはり、心理的なコンフリクトです。「理由は明確ではないけれど、なんか嫌だ」といったものから、「お互いの組織がわからない」という声。いずれにしても心理的なコンフリクトは起こりやすいからこそ、そこに対しては、先行的に相互理解を行うべきだと考えています。
我々は例えば、従業員向けの意識調査を少しカスタマイズして、「自分たちの会社をどう思っているのか」「統合する先の会社にどんなイメージを思っているのか」などを聞いて、その結果を開示し合うといったサポートもしています。
他には、トップが明確な意思を示さないままに進めると、不透明感や不安感が蔓延することにつながります。社員が認識できる意思表示を、トップが行うことは非常に重要だと言えます。

マクセルグループから学ぶ、『リブランディング』で経営層が心得ておくべき5つのこと (後編:今後)
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング