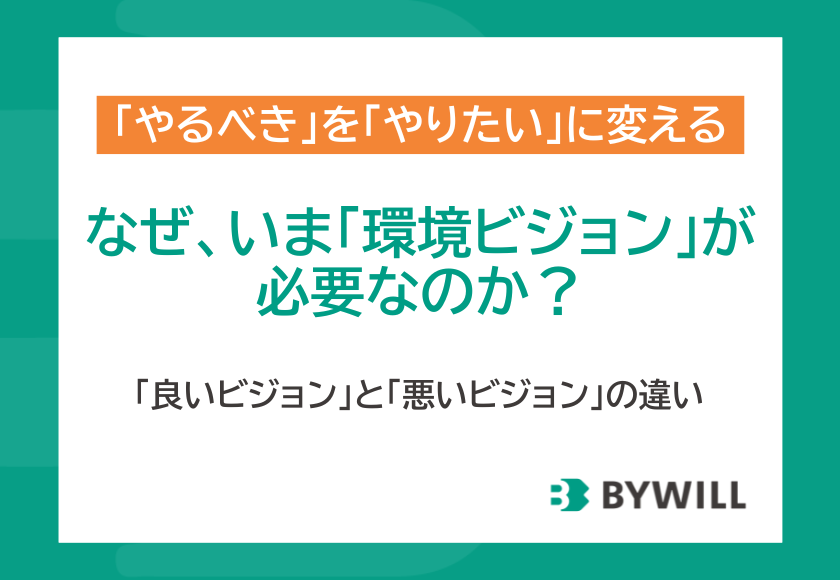多くのBtoB企業で「マーケティング・営業活動のデジタルシフト」が進み、これを機にWebサイトリニューアルを図る企業も少なくありません。このような状況の中、BtoB企業は「オンライン上で自社ブランドの価値をわかりやすく・魅力的に伝えていくこと」がより一層求められ、従来のBtoB的な考え方・手法だけでなく、DtoC的な発想を取り入れて「企画、設計」を行っていく事が必要不可欠になります。
そこで、ブランディング観点からのECサイト構築やDtoCブランドの立ち上げに豊富な実績を持つ、株式会社フラクタ河野貴伸氏をお迎えし、「これからのBtoBブランディング」というテーマで対談を行いましたので、その様子をお届けいたします。
【株式会社フラクタ様 HP】https://fracta.co.jp/
■プロフィール
株式会社フラクタ
代表取締役 河野貴伸氏
株式会社フォワード(現:バイウィル)
代表取締役 伊佐 陽介
BtoBブランディングにおける最大の課題
伊佐陽介(以下、伊佐):BtoB企業にとってのブランディングの最大の壁は、BtoC企業と比較してブランディングに馴染みがないことだと思います。BtoBにおいては「ブランディング=自分たちには縁のないもの」という認識があったり、BtoCと比べて「ブランド」という言葉の定義の統一が難しい側面があるといえるでしょう。より具体的には「ブランディングの目的は何か」「KGIやKPIは何であるのか」を設定するのが非常に難しいです。
なので、BtoB企業のブランディングで最初に課題になるのは、「ブランドに対する理解」と「KGIやKPIに対して合意形成をすること」だと思います。合意形成に関していうと、経営陣とその下の事業部トップで「ブランド」に対する認識が違うだけで、目的や目標がかみ合わないということが起こりがちです。また、よくある構図として、例えば広報部署がブランディング推進の役割を担ったとして、1部署が部門を横断した目的・目標設定をすることは難しいため、本当は営業など他部署に対してブランドの視点でやってほしいことがあってもなかなか実効性が伴わないというパターンです。
河野貴伸氏(以下、河野氏):実はBtoCビジネスにおいても、従来ブランドに対してはどこか他人ごと感がありました。BtoBにおけるサービスは、BtoCにおいてはプロダクトということになりますが、多くの人は「商品が良ければ売れる」「物が売れるかどうかは接客が上手いかにかかっている」という認識を持っており、そうした考え方が主流でした。
しかし、まさしくDtoCという言葉が出てきた時に、ブランディングということがフォーカスされるようになりました。「なぜ自分たちがこれをやっているのか」や、その熱量を働いているメンバー皆が持っていて、それ自体をエバンジェリストしていく、そのブランドを好きな人たちが他のお客様を連れてきてくれる、みたいなことが大きくフォーカスされるようになりました。
最近では、世の中で多くの情報が溢れるようになり、個々の製品やサービスの違いが見えにくくなったことで、実際に相対する人や目にする資料の良さでしか違いが生まれなくなりました。ところが、「実際に接点を持つ前に購買の意思決定の6割がなされている」という話を考えると、どれだけ世の中に認知されているか、ブランドとして認知されているかということが必要不可欠だということになります。最近では多くの人がその事実に気付き始めている気がします。

<株式会社フラクタ 代表取締役 河野貴伸氏>
河野氏:もう一点、BtoB企業に特に伝えたいのは、ブランディングを行うことは自社が物事を判断、行動するための効率化にも繋がるということです。最近、多くのお客様から「自社にとって適切なEコマースは何か」と相談を受けることがありますが、その際多くのお客様は世の中的に良いと言われているプラットフォームだからという理由で「Shopify」を選択します。しかし、実際には半分ぐらいのお客様にとっては「Shopify」を選択しない方が良いと言えます。
というのも、自分たちのブランドが何者で、お客様にどういう価値を伝えたいかによって、適切なシステム・DXの在り方は変わるはずです。というのは、「自分たちのブランドが何者か」「お客様に何を伝えたいのか」によって、最適なシステム、最適なDXは異なるはずなんです。ただ、「本来のブランド価値が何であるか」よりもDXやシステム・ツールの導入自体が目的になってしまう例が多々あります。遠回りに見えるかもしれませんが、最初に「本来のブランド価値」を明確にしておかないと、DXにしてもECにしても最適解は見えないと思っていて、ある意味でそれがBtoBブランディングの極意になる部分なんじゃないかと思っています。
BtoBビジネスにおける、ブランドの広め方
伊佐:BtoBビジネスにおいて、ブランドを広める際の「人」のプレゼンスは今後も一定残り続けると思っています。人のプレゼンスを出すための手法はオンライン化していくと思いますが、根本的には「ブランドを語ることができる人」「ブランドと紐づけて、自社のサービスの素晴らしさを語ることができる人」が社内にどれだけいるのかということは、ベースとして大切だと思います。
ただ、それだけでは語りきれない側面ももちろんあって、そこで重要なのがサービスサイトだと思っています。研ぎ澄まされたサービスサイトこそが、BtoBブランディングにおいて最も汎用性の高いツールなのではないかと個人的には思っています。
コーポレートサイトはステークホルダーが多すぎるので、主な目的やターゲットを明確化しにくい部分がどうしてもありますが、サービスサイトの場合はターゲットを明確にできるため、必ず研ぎ澄ませることができるためです。

<株式会社フォワード(現:バイウィル) 代表取締役 伊佐 陽介>
河野氏:確かに、サービスサイトを研ぎ澄ますことは本当に大事だなと思います。例えば、BtoCの例でいくと、ECの商品ページなどはかなり研ぎ澄ますことができます。実際、サイトにどういう写真を掲載するか、サイトでどういうメッセージを伝えるかによって、コンバージョン率が細かく変化します。
ところが、BtoBビジネスになると、サービスサイトを研ぎ澄ますことを諦めている方が多いような気がします。例えば、自分たちのサービスはあまりにも複雑すぎて説明しきれないので、とりあえずスペックシートを置こうみたいな人は多いと思います。気持ちはすごくわかるのですが、「どれだけきちんと説明するか」が差別化に繋がることもまた事実だと思います。
伊佐:あとポイントになることとしては、「ブランディング」「マーケティング」「セールス」が相互に連動するようなサービスサイトになっているかどうか。どれだけデザインに凝ったサービスサイトだとしても、セールスに必要な情報が取得できる設計になっていないとか・・・。セールスの効率的な活動を損なうような設計になっていると、実は売上には繋がらないということが起こりがちです。
河野氏:ECでも、デザインがかっこいいサイトでの売上が高いかと言われると、実はそうでないこともあります。シンプルで洗練されたデザインを好む人もいれば、情報量が多くて買い物自体を楽しめるような体験を好む人もいるので、やはりターゲットによってデザインは変えるべきでしょう。先程あったように、コーポレートサイトだとステークホルダーが多いため絞り込みも難しいですが、サービスサイトはそこを明確に決めて、しっかりと作っていくというのは重要だなと思います。
コロナ禍において、BtoBブランドの広め方に起きた変化とは?
河野氏:コロナ渦以前は、BtoBサービスのサイト検索を行う場所は会社が多かったと思います。しかし、リモートワークが進展したことにより、サイト検索の場所は家に変化しました。これによってサイト検索時の心理的な変化が生じていて、あまりカッチリした固いコミュニケーションよりも、BtoC的な親しみやすいコミュニケーションの方が受け取られやすいということが出てきています。その良い例が、会社と家の中間であるタクシー内の広告です。最近のタクシー広告というのはちょっと親しみやすくて面白いものが多いですよね。ブランドの広め方という観点だと、コミュニケーションのトンマナの変化は一つあるのではないかと思います。
河野氏:最近だと、サイボウズさんやSansanさんのCMも個人と企業の中間にうまくフォーカスしていて、BtoBにおいても”バズらせる”みたいなことは重要になっている気がしますね。
BtoBのDXは何から始めるべきか
河野氏:実は以前、「真のデジタルネイティブはDXをどのように捉えているのか」を調べたことがあります。真のデジタルネイティブであるZ世代と呼ばれる人にヒアリングを行った際に分かったのは「真のデジタルネイティブは、デジタルを使わなくて良い箇所を理解している」ということでした。
つまり、本来DXは手段でしかないため「なぜDXを行うか」を考える必要があります。そのために「ブランディング」「マーケティング」「セールス」が統合された未来を考えることになりますが、そのような未来の実現のためには、ほぼ無意識的にデータを活用できる環境を整備すること、顧客に対するセールスのスピードは超高速にする必要があり、なのでデジタル化が必要であると整理することができます。であれば、それ以外のことに使うツールは多少アナログになっても良いということになります。まず初めに「なぜDXを行うか」を明確にすることが、DXのポイントなのではないかと思います。
伊佐:今でいうDXのように、業界の流行り言葉と呼ばれるものがありますよね。流行り言葉が生まれると、そこに興味関心が集まること自体には意義があると思いますが、それに取り組むことが目的化されるという残念な側面もあります。「自社では何のために、どの程度DXをするのか」「具体的に何をするのか」と順を追って考える必要があるといえます。
BtoBに取り入れることができる、DtoCならではの考え方
河野氏:これは特にスタートアップのWebサービスなどでは当たり前に行われていることですが、「いかにユーザーの声を聞くか」という考え方でしょう。というのも、特に日本のBtoBに言えることなのですが、どうしてもお客様に対して自分たちの手の内を明かさないみたいな傾向が強い気がします。
一方で、DtoCにおいては、実際のビジネスの形としてお客様との共創関係があります。自分たちのお客様が本当に求めていることや、熱狂的になってくれるものを作っていこうという部分が強いと思います。例えば、ユーザーとの結び付きが強いWebサービスとして、slackなどが挙げられます。今でこそセールスフォース社に買収されましたが、初期の頃はユーザーフィードバックを非常に大事にしていたサービスでした。あとは、AWS(アマゾンウェブサービス)も、日本に入ってきた当時はユーザーコミュニティを非常に大事にし、ユーザーの意見を吸い上げて適切なローカライズに成功した良い事例です。このように、顧客になり得るユーザーを巻き込みながら、一緒にサービスを創り上げていくみたいな姿勢は、BtoBにおいても取り入れることができます。実際にサービスを導入してくれる担当者の意見を吸い上げながら、サービスをアップデートしていくみたいなことはすぐにできると思います。
あとは、DtoCが成功した大きな要因として、データを仮説と検証にうまく活用したことが挙げられます。例えば、「日本のどういった人たちが自社のサービスを使用していて、なぜ使用しているのか」をデータで検証し、そこから新たなペインを見つけて、サービスのアップデートへ繋げるといった具合です。なので、BtoBにおいても、「どうしてこのユーザーは自社サービスを使用してくれるのか」、「自社サービスの何に共感してくれているのか」、つまり従来のブランドが持つ機能的価値だけでなく、情緒的価値やブランドに対する共感といった部分を仮説構築、検証していくことは必要だと思います。
伊佐:一方で、アップル社のiPhoneのようにプロダクトアウトで大ヒットするような商品もあると思うのですが、サービスの立ち上げ期に、技術立脚でプロダクトアウトのスタンスを取るのか、あるいは顧客の意見をこまめに吸い上げるスタンスを取るかで悩むことってありませんか?
河野氏:DtoCというビジネス形態においては、規模を大きくしない前提になっているので、基本的には顧客の狭いニーズに応えるというスタンスでサービスを立ち上げます。なので、アップル社のようなリーディングカンパニーとは考え方が若干異なると思います。
ただ一方で、プロダクトアウトのサービスでも別にいいのではないかという質問もよく頂くことがあります。それに対する私の回答としては、プロダクトアウトの商品・サービスは、おそらく未来の顧客ニーズに基づいて開発を行い、データ的な裏付けはないものの、その未来ニーズを予測という形で信じ切っていると思っています。なので、形式的には顧客ニーズに基づいてはいるが、未来予測でしかないため、ギャンブル的要素を含んでいることになります。
伊佐:時間軸と目標の規模感や高さによって、どちらの手法で商品・サービスを立ち上げていくかが変わってくるというわけですね。
ゼロからブランドを構築するときの時間軸は?
伊佐:これをすれば必ず成功するというセオリーはなく、各企業にとっての最適解は異なると思います。また、これに関しては、どれだけの人を巻き込みながら作るのかという話とセットだと思っています。実際のところ、一旦時間軸を無視して、一貫性と継続性を担保することが重要なので、トップと2人で作った後で覚悟を持って下に落としていくやり方が成功する確率は上がると思っています。その場合だと、ブランドの初期の構築は3ヶ月程度で終わります。しかし、現実には、創業家が経営に携わっている会社や外資系の規模でないと、このやり方は難しいです。なので、日系企業の多くでは、ミドルアップダウンのやり方を採用しています。事業部長などが先頭に立って、トップから合意形成を勝ち取りにいくやり方です。この場合だと、初期のブランド構築まで4〜6ヶ月程度かかることが多いです。
河野氏:DtoC的な側面でいくと、求められるブランディングのあり方が少し変化してきていて、私たちは「リアクティブなブランディング」と名付けているのですが、柔軟かつ迅速にアップデートできる状態が求められてきています。昨今の急速な社会的変化の中で、同じブランドを使い続けるのは難しくなっているため、本質的な部分だけは変えずに、他の部分は常にアップデートしていく。となると、3〜4年という時間軸でブランドを作り上げるというのは少し厳しいのではないかと思っていて、長くても1年以内には作り上げて、それをアップデートしていくという考え方を持つと良いのではないかと思います。
対談は以上になります。ご参考になりましたでしょうか?
BtoBブランディングの方法論についてより詳しく知りたい方は、以下のブログもご覧ください。
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング