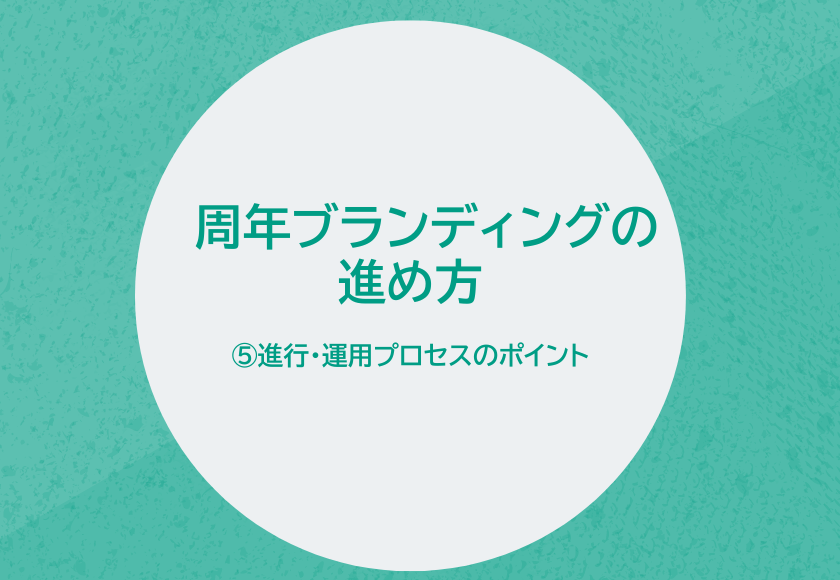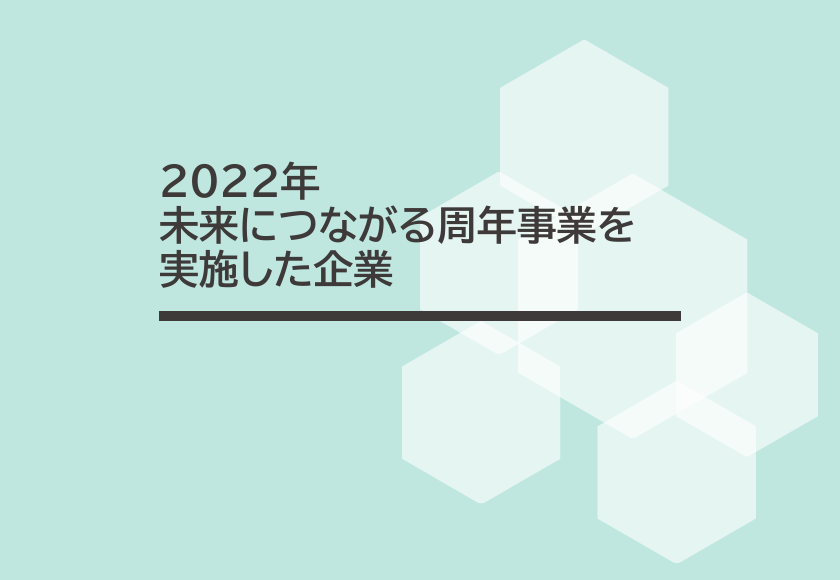今回は、周年事業を進行・運用する際の疑問である、「いつから、どんな体制で、予算はどうすればよいのか」をお伝えします。
周年事業の準備はいつから始めたら良い?
あくまで目安ですが、周年イヤーの2年前程度から着手することが望ましいです。

【2年前】前提となる概念設計
まず、経営課題を把握し、周年事業の目的を明確化します。そして、社内向け施策の前提となる理念やミッション・ビジョン・バリューの策定や、社外向け施策の前提となるブランド価値の整理を行います。少なくとも周年イヤーの前年末には終わらせておく必要があります。
【1年前】施策やコンテンツの企画・制作
目的やミッション・ビジョン・バリュー、ブランド価値に沿って、実施する企画の制作を行います。また、準備段階ではあっても、その情報を積極的かつ継続的に発信します。
【周年イヤー】実行
各種施策を実行し、継続的に社内外に情報発信を行います。特に社内向けに関しては、進捗の共有や活動報告を丁寧に行うことによって、興味関心を持続させることが重要です。
【周年後】継続・仕組み化
周年事業が“打ち上げ花火”で終わらないように、目的に基づいた継続的な施策展開を図ります。
例えば、DeNA社は2019年に創業20周年を迎え、誰もが自発的にプロジェクトを起こせる取り組み『De20(ディートゥエンティ)』を立ち上げましたが、その取り組みを継続的なものとすべく、新De20とでも言うべき新プロジェクト「Delight Board(デライトボード)」を2020年1月に発足させています。
ここまで数回のブログでお伝えしてきたように、周年事業の「目的」や伝えていくべき「理念」「ブランド価値」をしっかりと固めることが適切な周年企画の実現につながります。だからこそ、その概念設計に十分な時間をかけることが肝要です。また、概念設計や施策の企画を行う際に、適切な社員を巻き込んだり、積極的に発信したりしていくことが、周年事業の効果をさらに高めます。
どのような体制で進めればよいか
周年事業は非定例行事のため専門部署がなく、突発的に任命されることが多いですが、望ましい体制は経営トップをリーダーに、事務局を置き、その下に施策ごとの分科会があるという体制です。事務局は、経営企画や広報が中心になることが多いです。また、分科会は施策内容に合わせてアサインされますが、できるだけ部署横断で組成したほうが、視野を広げて議論することができます。実施施策がそれほど多くない場合は、分科会形式ではなく、1つのプロジェクトチームにすることもあります。

予算をどのように考えれば良い?
最初のブログでお伝えしたように、周年事業はただ感謝や祝賀をする機会だけではなく、未来に向けて経営課題を解決する機会です。そのため、周年事業の予算も「祝賀・感謝のコミュニケーション費用」ではなく、「経営課題解決の投資」と捉えるべきです。理想論としては、「今解決すべき経営課題は何か」「そのために必要な施策は何か」を考え、そのための予算を確保するべきです。しかし、現実的には、“予算ありき”で始まることも多いです。その場合は、あくまで「課題解決の投資」という考えに基づいて、広報やマーケティング、人事、事業部など現場予算の活用を検討することも1つの考え方かもしれません。

ここまで5回にわたって周年事業についてお伝えしてきました。皆様のお役に立つような情報を提供できていれば幸いです。
<各回の内容は以下の通り>
周年ブランディングの進め方 ①周年事業に取り組むときに最初にすべきこととは?
周年ブランディングの進め方 ②社内向け周年施策~理念浸透のための施策設計
周年ブランディングの進め方 ③社外向け周年施策~ブランドの価値とは
周年ブランディングの進め方 ④社外向け周年施策~メディアの活用法とその効果
周年ブランディングの進め方 ⑤進行・運用プロセスのポイント ※本記事