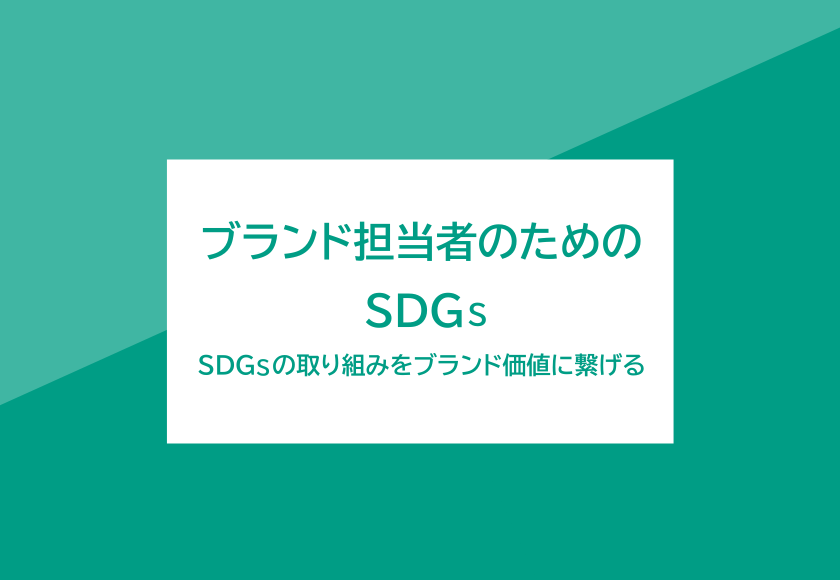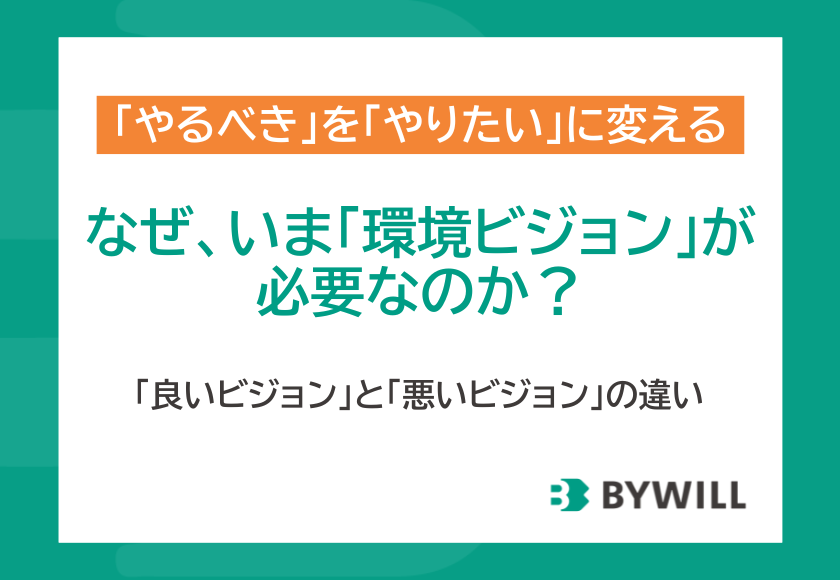現在、多くの企業がSDGsの取り組みを進めていますが、「ブランディング」という観点からこの動きをどのように捉えたらよいのか、お悩みの方も多いのではないでしょうか。本記事では、企業のブランド担当者がどのようにSDGsの取り組みをブランド価値に繋げていけばよいのかをご紹介致します。
SDGsは「ブランド」に大きなインパクトを与えはじめている
本題に入る前に、まずSDGsとは何かを再確認してみましょう。SDGsとは「Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)」の略称です。このSDGsは2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193ヵ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の大きな目標とそれらを構成するための具体的な169のターゲットで構成されています。
多くの企業で既にSDGsの取り組みが進められていますが、企業規模や業種に関わらず、あらゆる企業にとって、これから先ビジネスを存続・継続していくために、SDGsや社会課題の解決に向き合い、行動を起こしていくことが必要不可欠になっています。
実際に、SDGsへの取り組みは企業を取り巻く様々なステークホルダー(顧客・取引先・従業員・採用候補者)に影響を及ぼし、ブランドに大きなインパクトを与えています(下図参照)。

その一方で、SDGsに対する誤解もまた生まれています。それは、SDGsの取り組みを中心的に担うのは、企業のサプライチェーンの前半工程を担う「調達」「生産」などの部署やその取り組みを発信する「広報・CSR」関連部署がメインで、「ブランド担当者ができることは少ない」という誤解です。
そのような状況を踏まえて、ここからは「SDGsの取り組みをブランド価値に繋げていくための考え方」を具体的に説明していきたいと思います。
SDGsの取り組みをブランドコンセプトに落とし込む
まず前提として、弊社のブランディングの考え方をお伝えします。


そもそもブランドとは、「様々な接点での体験によって、顧客の中での価値を想起させ、“期待を高める”役割を果たすもの」と定義します。そして、ブランドを創る活動=ブランディングには、はじめに「ブランドコンセプト」が明確に規定されることが大前提となっています。コンセプトが曖昧だと、その先の取り組みは当然バラバラになってしまい、顧客体験の一貫性を保てず、顧客の期待も高めることはできません。
では、「ブランドコンセプト」はどのように規定すればよいのでしょうか?そのためにはまず「ブランドコンセプト」を構成する4つの要素を確認する必要があります。

ブランドコンセプトは、下記4つの要素から構成されます。
コアバリュー:ブランド価値を一言で言い表したもの
ベネフィット:顧客が得られる具体的な便益
エビデンス :便益をもたらす根拠・事実
リソース :根拠・事実の裏付けとなる社内資産や仕組み
ブランド担当者は、自社のSDGsの取り組みを、この要素に紐づけてブランドのコンセプト(価値規定)として組み込んでいくことが求められます。
SDGs×ブランディングの実行ステージ
ここからは、実行に向けたより具体的な考え方や事例をご紹介します。
まず、SDGsをブランド価値に接続していく段階として「4つのステージ」で捉えてみましょう。

先程、多くの企業でSDGsの取り組みが進められているとお伝えしましたが、その発信媒体は主にコーポレートサイトの「IR情報」「サステナビリティ」であることが殆どです。ただ、一般の消費者・顧客がそのようなページ・コンテンツを閲覧することは多くありません。取り組みは進めているが認知はされていない(ブランディングには機能していない)、それが上図の「Stage1」の段階です。この状態から、SDGsの取り組みをブランド価値に繋げていくためには、消費者・顧客により近い接点での動きを創り出していくことが必要です。それが、ブランド担当者が取り組むべきことであり、上図「Stage2~4」の領域にあたります。
ではそれぞれのステージについて詳しく説明していきます。
ステージ2:認知獲得
この段階は、「SDGsの取り組みは開始しているが、顧客や消費者には伝わりきっていない」という状態を、「取り組み自体は認知されている状態にする」という意味合いです。そのために取り組むべきことは自社商品・サービスやそれにまつわるプロモーション活動など、顧客の消費行動に近い媒体を活用して、SDGsの取り組みを伝えていくことです。
具体例としては、ネスレ社の「キットカット」が挙げられます。
▼実施したこと
キットカットは従来、プラスティック素材のパッケージでした。しかし、海洋プラスティックの使用量を減らすため、パッケージ素材をプラスティックから紙に変更しました。この変更は、商品を手に取ってもらえれば一目瞭然に伝わります。また、紙パッケージ自体にも素材変更したことを大きく明示し、消費者にアピールしています。
さらに、紙になったことを上手く活用し、「折り紙を作ってみよう」というハッシュタグを設定したtwitterキャンペーンを実施するなど、説明的になりすぎず、感覚的に理解が促進されるような工夫も行っています。
ステージ2「認知獲得」でのポイントは、以下3点です。
- 消費者の購買プロセス上の接点(商品名、SNS、店頭、パッケージなど)で取り組みを伝えていく
- 取り組みの事実を淡々と説明するだけでなく、右脳的・感覚的に伝わるアプローチ(折り紙の例)
- 売上に即効性があるものではないが、地道に継続して認知を獲得する
ステージ3:価値創出
この段階は、「取り組みは認知されている」という状態から、「顧客にとってのベネフィットにも繋がっている」という意味合いです。ベネフィットとは、先程ブランドコンセプトの箇所でお伝えした通り、「顧客にとっての具体的な便益」という意味になります。
具体例としてはナチュラルローソンの「洗剤の量り売り」が挙げられます。
洗剤という商材は、機能性だけでなく香りで選択されることもある、ある種の嗜好品ともいえるもので、コンビニやドラッグストアには多くの商品が並んでいます。ただ、殆どの商品は比較的大容量のもので、「少しだけ試しに使ってみたい」といったニーズに応えるものは多くありません。ナチュラルローソンはその潜在ニーズに着目し、「マイボトルを利用した完全セルフ方式での洗剤の量り売り」を導入しました。利用者は、自分の好きな香りの洗剤を好きな分量だけ購入することができます。
この取り組みは、プラスティックゴミの削減というSDGsの取り組みになると同時に、消費者にとって「少量から試すことができる」といったベネフィットに繋がるもの、すなわち「SDGsの取り組みが、消費者にとって選ぶ理由になっているもの」と捉えることができます。
ステージ3「価値創出」のポイントは以下2つです。
- SDGsの取り組みが、自社商品やサービスのベネフィットを高める or 新しいベネフィットを創り出すための切り口を考える
- 商品の基本価値(洗剤なら洗浄力など)だけでなく周辺価値(香り、買いやすさ・試しやすさなど)まで視野を広げること
ステージ4:モデル変革
ステージ4は、既存の商品やサービスという枠を超えて、新商品・新サービスや新規ビジネスの展開~多角化を目指す段階です。
具体例としては、セイコーエプソン社の「Paper Lab」が挙げられます。
「Paper Lab」は、オフィスで完結する、小さく、そして新しい資源サイクルとして導入され、水を使わずに、使用済みの紙から文書情報を完全に抹消した上で、オフィス内で新たな紙を生産できる製品です。この商品は、導入した企業のSDGs推進(水資源や森林保護、廃棄物削減)といった新しい価値を創出する新規ビジネスとして展開されています。多くの企業がSDGsの取り組みを進めていくことを支援するという、まさに今の時代に合った新しいモデルと言えるでしょう。
ステージ4「モデル変革」のポイントは以下2点です。
- 既存の商品・サービスに留まらない、新しいビジネスニーズを検討していくこと
- 上記の観点として、消費者(顧客)が商品・サービスを利用する過程・プロセス全体まで広く捉えること
SDGsの取り組みをブランド価値に繋げていく手順
このような考え方を踏まえて、改めてSDGsの取り組みをブランド価値に繋げていくコンセプトづくりについて振り返ります。
- まずは、自社のSDGsの取り組みを洗い出してみましょう(下図「リソース」の洗い出し)
- 次に、洗い出した「リソース」を、より顧客・消費者接点に近い「マーケティング4P」で伝えられる手段がないかを考えてみましょう(下図「エビデンス」の設計/前述「ステージ2」の段階)
- また、「リソース」を活用して新しい顧客の便益を創り出すことができないかを考えてみましょう
(下図「ベネフィット」の設計/前述「ステージ3」の段階) - 最後に、1~3を統合して、SDGsの観点を踏まえた「ブランドコンセプト」として整理・構造化しましょう

いかがでしたでしょうか。この記事が、皆様の「ブランド」とSDGsの関わり方について少しでもヒントとなり、アクションの手助けになれば幸いです。