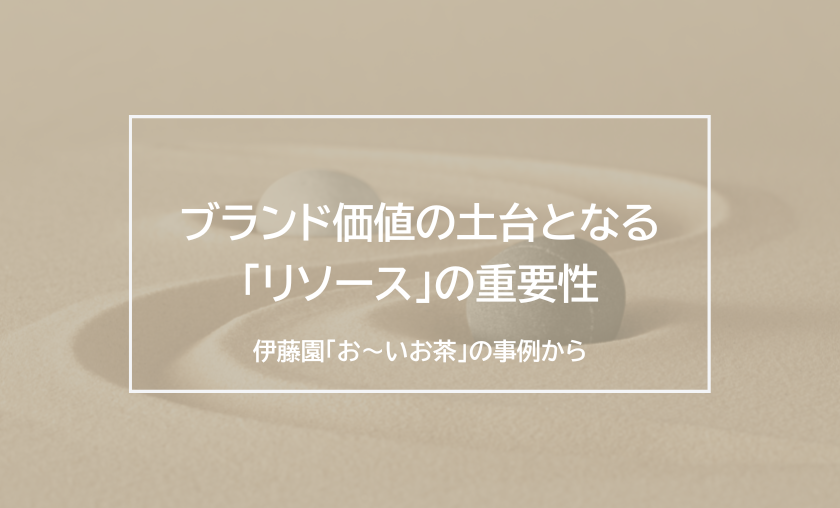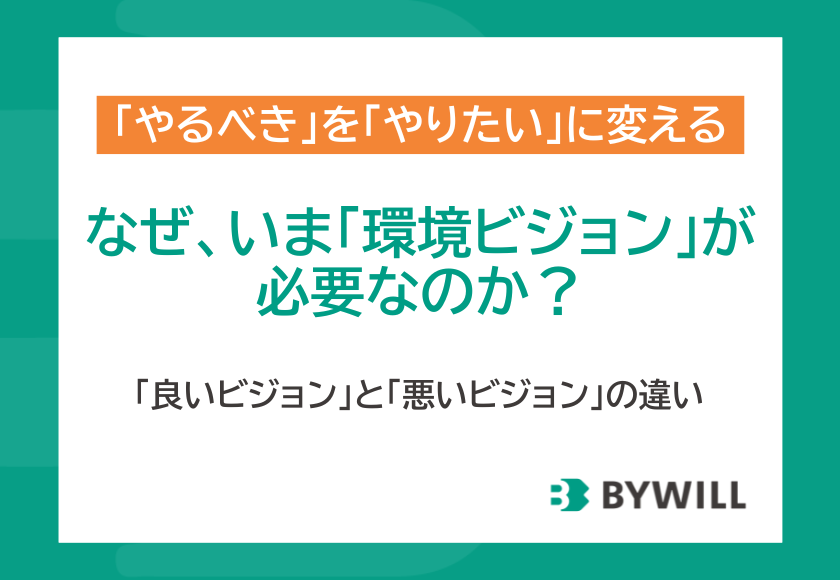インターン生の日下夏輝です。
私は現在ビジネススクール(MBA)に通いながらフォワード(現:バイウィル)でインターンをしています。
このブログでは、ビジネススクールで学んだことを、フォワード(現:バイウィル)内に蓄積されたナレッジと合わせてご紹介していきたいと思います。
緑茶系飲料トップシェアを実現した伊藤園社「お~いお茶」
今回は緑茶系飲料においてトップシェアを誇る伊藤園社「お~いお茶」のブランディングを分析していきます。
いまでこそ、ペットボトルで売られる緑茶・緑茶系飲料は、私たちにとって当たり前の商品・市場ではありますが、それは伊藤園社のブランディングならびに市場開拓があったからこそでした。

「お~いお茶」のネーミング
実は、伊藤園社の「お~いお茶」という商品名には“顧客の声”が練りこまれています。
1970年代当時に放映した”お~いお茶”というフレーズが好評だったことから、そのフレーズをそのまま商品名に採用しています。
顧客の心に残ったフレーズをそのまま商品名に採用したからこそ、「お~いお茶」は浸透したのかもしれません。
(参照)
「よくいただくご質問」
https://www.itoen.jp/customer/faq/38811
未開拓市場である緑茶飲料の市場規模を推定
伊藤園社が「お~いお茶」を発売しようとする当時、まだ緑茶飲料市場、すなわち緑茶を外で購入するという市場は顕在化されていませんでした。ウーロン茶や紅茶はすでに茶葉そのものではなく、外で飲料として購入する市場が存在していたものの、緑茶は「茶葉を購入し、家で急須で入れて飲むもの」という認識があったのです。
そのような中、当時の伊藤園社には、市場が顕在化していないためにポテンシャルもわからず、どの程度のリソースを投入すればいいのか、そしてどのような手法で市場を開拓していけばよいのかがわからないという課題がありました。
そこで伊藤園社は「飲料化比率」という指標を用いて、市場規模を推計していきます。飲料化比率とは、茶葉などの素材の全消費量に対する、缶やペットボトルといった飲料で消費される割合のことです。当時、先行して飲料として定着していたウーロン茶やコーヒー、紅茶の飲料化比率から、緑茶の飲料化比率を推計していきました。

書籍『1からのブランド経営』によると、止渇性の強いウーロン茶が50%、嗜好性の強い紅茶やコーヒーが30%であったことから、両方の特性を併せ持つ緑茶は飲料化比率30%~50%になると推計することができ、さらにその飲料化比率から、将来的な緑茶飲料市場を6,000~8,000億円と推計することができたといいます。
こうして、伊藤園社は緑茶飲料市場の成長可能性を確信し、成長期に入る前から「お~いお茶」のポジショニングを見据えた長期的な資源の投入を可能にしました。
(参照)
石井淳蔵・廣田章光(編著)『1からのブランド経営』 碩学舎 2021
模倣困難な強みを確立した、中長期的な資源投入
伊藤園社では、長期的なビジョンに基づく資源の投入により、他社が模倣困難な強みを確立しています。具体的には、2001年から国内外での大規模な生産農家の育成事業をはじめていることが挙げられます。ここでは、生産者に対して機械化や独自技術の導入、安定した単価での取引などのサポートを行い、「お~いお茶」専用茶葉の栽培も委託しています。
お茶の産地育成には10年単位での時間が必要となるために、早期から取り組んでいた伊藤園には模倣困難な強みが確立されているのです。
さらに、緑茶生産農家の育成事業を行うことで、「お~いお茶」一本の生産地や生産農家、製造方法までトレーサビリティすることができます。これも長期的なビジョンに基づく一貫した事業展開による強みの獲得だといえるでしょう。
(参照)
石井淳蔵・廣田章光(編著)『1からのブランド経営』 碩学舎 2021
強力なリソースに基づく「お~いお茶」のブランド価値
ここまで、伊藤園社が緑茶飲料に参入~拡大を図ってきた経緯をお伝えしてきましたが、これを基に、「お~いお茶」のブランド価値をバイウィルで活用する「ブランドコンセプトを構成する4つの概念=コアバリュー・ベネフィット・エビデンス・リソース」のフレームワークに当てはめて考えてみたいと思います。
定義は下の図のようになります。

上記のフレームに当てはめて伊藤園の「お~いお茶」のブランド価値を整理してみます。
- 国内外での大規模な生産農家の育成事業がリソースとなり、高品質の茶葉から抽出した緑茶、トレーサビリティというエビデンスが醸成される。
- トレーサビリティというエビデンスが「安心」というベネフィットを創出し、さらには国内外での大規模な生産農家の育成事業とともに培われてきた、伊藤園独自の「茶葉のみによる抽出方法」が、「急須でいれたような味わい」というベネフィットを創出します。
- そして、ベネフィットである「安全」と「急須で入れたような味わい」が合わさることで、「安心して本格的な味わいを楽しめる」というコアバリューを提供できている
本格的な参入を図った時点で将来の市場ポテンシャルを推計し、他社からの模倣困難な強み(生産背景)の獲得に資源を投下したことが、現在のブランド価値に繋がっているのではないでしょうか。

まとめ
伊藤園社「お~いお茶」の事例から学べることは、「ブランド価値を創り出す強力な“リソース(模倣困難な資源)”」の重要性です。
伊藤園社は緑茶飲料市場を開拓するにあたり、「急須で入れたような本格的な味わい」をブランド価値の中心に据えました。そこで必要になるのが茶葉へのこだわり。まだ市場が顕在化していない段階からでも、高いブランド価値を実現する模倣困難なリソース(生産農家の育成、お~いお茶専用の茶葉栽培委託など)の構築に力を注ぎました。
ただ、この「リソース」は決して新しく構築するものとは限りません。
皆さんの会社・ブランドの中にも、意外と見落としている“自社ならではの資産(技術やノウハウ、こだわりなど)”が既に存在しているかもしれません。
まずは“自社ならではの資産”を探してみること、それを基に改めてブランド価値の体系的な整理を行ってみるのもオススメです。