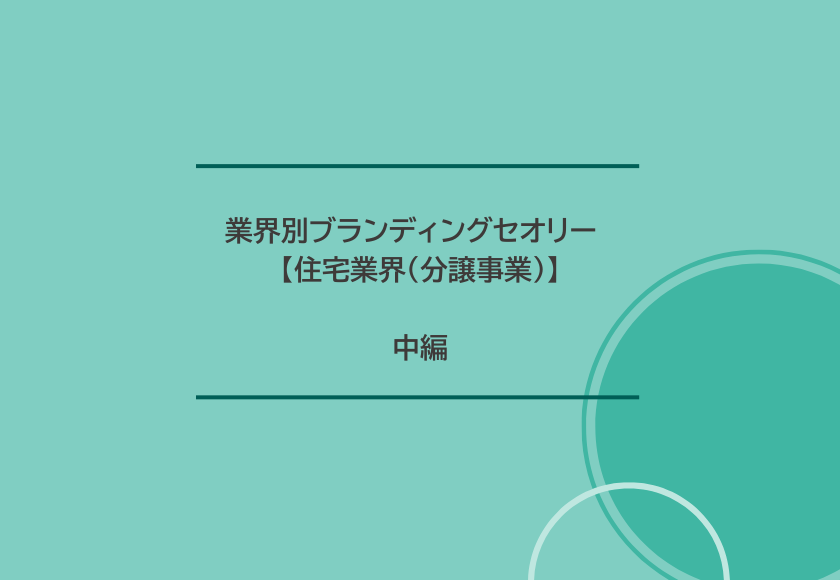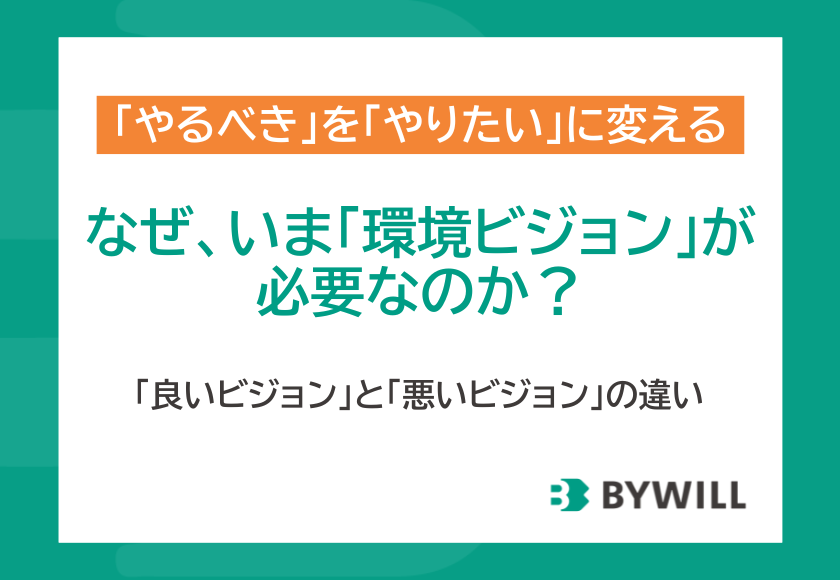こんにちは。取締役の伊佐です。
前回は住宅業界(分譲事業)に於いてブランディングに取り組む上で、必ず踏まえておくべき5つの要素を述べました。
今回は、その要素が実際にどのようにブランディングに影響するかについてお伝えしたいと思います。
【今回のコラムでお伝えしたい住宅業界ブランディング4つのポイント】
Ⅰ.住宅市場の縮小と寡占化が進んでいるからこそ、「一刻も早く、市場において検討時想起順位5位以内の地位を確立するために何ができるか」をまず考える
Ⅱ.超高額で接点が少なく、同一商品が一つもないからこそ、ブランディングのセオリーである「全ての顧客接点での一貫した顧客体験によってブランド価値を蓄積するのが難しい」ということを前提にブランディングの施策を組み立てる
Ⅲ.「売り手と買い手の情報格差」が縮小しているからこそ、ブランドコミュニケーションにおいて、「どのメディアで」「どのような情報を」伝えることが必要なのかを、現在の消費者の住宅検討~購入プロセスに合わせて再設計する
Ⅳ.仕入が困難、且つ事業や商品に対するインパクトが大きいからこそ、特にインナーブランディングを強める
I . 住宅市場の縮小と寡占化が進んでいるからこそ、住宅ブランドは「一刻も早く、市場において検討時想起順位5位以内の地位を確立するために何ができるか」をまず考える
前回のコラムでは、住宅業界の特徴の1つとして「市場が縮小し、寡占化が進んでいる」ことを挙げました。そのような市場環境の中で我々が出したひとつの住宅ブランディングの答えとして、「住宅検討時想起順位5位以内」にならなければ、ブランディングの成果が具体的な収益になりにくいということが挙げられます。
住宅購入時における消費者の行動をイメージしてみましょう。
「家を買いたい」と考えたとき、ほとんどの人はまずエリアと価格の情報収集・検討から入ります。
そのプロセスにおいては、「検討エリアに○○(ブランド名)の物件があるなら見に行かないと」という意識が働くからこそ、「“○○”のマンションギャラリーやモデルルームに行く」という行動が生まれます。そして、「マンションギャラリーを見に行く」という行動の対象となるのは、3~5社程度に絞り込まれるのが一般的です。
逆に言うと、この5社に入らない限りは、数ある選択肢の中から自社を選んでもらうというブランドの機能がそもそも働かないのです。
住宅市場の規模は将来的に確実に縮小し、住宅事業者の寡占化が進むことで、上記のような消費者の認識を獲得し得る「余白=選択肢」は、様々な業界の中でも特に少ない状況にあるという訳です。
また、この状況は今後時間を経る程に進行していくと考えられるため、一定以上の規模に成長拡大することを目指す企業は「市場において、検討時想起順位5位以内の地位を確立するために何ができるか」を一刻も早く考える必要があるということです。
Ⅱ.超高額で接点が少なく、同一商品が一つもないからこそ、ブランディングのセオリーである「全ての顧客接点での一貫した顧客体験によってブランド価値を蓄積するのが難しい」ということを前提にブランディングの施策を組み立てる
住宅業界の特徴は「市場の縮小・寡占化」だけではありません。それとは異なる特徴の1つとして、「多くの消費者にとって、住宅購入は人生でそう何度も経験するものではない」ということが挙げられます。それはつまり、「住宅というものはどういう基準で選択すべきかを、経験を通じて学ぶ機会が限られている」ということです。
また、住宅は選択に於けるパラメーターが非常に多いものです。
その対照的な例として、家電量販店でテレビを買う時を考えてみましょう。
テレビコーナーの商品には、「型数」「解像度」「チューナー数」「省エネ性能」「周辺機能(録画・外部機器連携・ネットワーク機能など)」などの項目が記載された札があります。
実際の商品を見ながらそれらの項目を比較検討することで、買うべき商品が判断できるようになっているわけですが、それは言い換えると、それらの項目で選択判断のパラメーターが概ね網羅されているということです。
一方で、住宅は『立地条件』だけでも「最寄り駅」「住所」「駅距離」「駅からの導線」「買い物のし易さ」「学校」「行政機関や医療機関へのアクセス」など非常に多くの要素が挙げられる上に、それに加えて『価格』『間取り』『向き』『広さ』『外観』『共用部』『設備機器』など、更に多くの要素とのバランスも踏まえて判断する必要があります。
そして、分譲住宅は、言うまでもなく「土地ありき」で企画~販売されるものです。全く同じ土地は1つもないと言って過言ではありません。
つまり、単純なパラメーターの比較で選択判断することが難しい商品だということです。そもそも多くのパラメーターがある上に、各パラメーターに対する習熟度を上げることが、消費者にとって非常に困難である訳です。
こうした特徴から言えることは、ブランディングのセオリーである、「全ての顧客接点での一貫した顧客体験によってブランド価値を蓄積する」ことが非常に困難だということです。
何故なら、接点が少なすぎてそもそも「蓄積」の機会が少ない上に、同一商品が皆無であることによって、「一貫した顧客体験」の創出も難しいためです。
住宅ブランディングにおいては、この点を念頭において取り組みを考えなければいけません。
Ⅲ.「売り手と買い手の情報格差」が縮小しているからこそ、ブランドコミュニケーションにおいて、「どのメディアで」「どのような情報を」伝えることが必要なのかを、現在の消費者の住宅検討~購入プロセスに合わせて再設計する
上記のような事情もあり、住宅業界は長らく「売り手と買い手の情報格差」が非常に大きな業界でもありました。
当然、この要素は「売り手」側に有利に働くことが多く、物件や販売所の現場で伝えるべき情報の取捨選択(営業トークと言い換えても良いかもしれません)によって勝負できていたのが実情でした。
しかし、そのような住宅業界でも、ネット環境や各種メディアの発達によって、ある程度「売り手と買い手の情報格差」が埋まってきています。消費者は、ネット上の住宅情報メディアによって、一定の項目について、様々な条件設定で、簡単に横比較することができ、ある程度の学習と検討をした上で実際の販売所を訪れることができるようになった訳です。
しかしそのことが、分譲事業者にとっての別の課題も浮き彫りにしました。
それは「売り手と買い手の認識ギャップ」とでも呼ぶべきものです。
これは、前述の「情報格差」とは全く意味合いが異なります。
買い手は、「自分で必要な情報は調べられる。自分で判断できる」という認識を持ちますが、売り手は、「ネット上で分かる程度の情報で、住宅の(あるいは自分が担当しているこの物件の)ことが全て分かるはずはない」ことを知っています。
この認識ギャップによって、売り手のコミュニケーションは、細かい住設機器やスペックの説明に終始したり、逆に非常に曖昧で要点の分かりにくい広告(「住宅ポエム※」などと揶揄されたりもしていますが。。。)に陥りがちになっています。逆に買い手は益々、「そんなことは分かっている。要するに他とどう違うんだ?自分にとって何がベネフィットなんだ?」という意識を強めます。
※参考 「めくるめくマンションポエムの世界」(NAVERまとめより)
http://matome.naver.jp/odai/2129013424262089301
実際、我々がこれまでに実施した市場調査では、「住宅購入時における選択重視点」について、「立地」「価格」「広さ」などに次いで、「物件コンセプト」の重視度が、「物件広告」「接客」「入居後のアフターサービス」「設備機器」などを大きく引き離して高く出ており、その傾向は近年強まってきているように思います。
これらの特徴から言えることは、ブランドコミュニケーションに於いて、「どのメディアで」「どのような情報を」伝えることが必要なのかを、現在の消費者の住宅検討~購入プロセスに合わせて再設計する必要がある、ということです。
そして同時に、今後の住宅業界に於けるブランドコミュニケーションは、「モノが良ければ、その結果としてブランドも高まる」という認識を一掃し、「要するに、この物件は○○という特徴・価値を持っています」という個別のメッセージを蓄積した先に、「つまり、このブランドは◎◎です」という認識を獲得できるように設計される必要があります。
Ⅳ.仕入が困難、且つ事業や商品に対するインパクトが大きいからこそ、特にインナーブランディングを強める
前回お伝えした“センミツ”(1,000の土地情報の中で、仕入の俎上に乗る物件は3つしかないという意味)の言葉どおり、分譲住宅事業は土地を仕入れなければ始まらないのに、その土地の仕入れが非常に困難だという前提があります。
そして、仕入れた土地が、物件全体の価値の多くを規定してしまう側面が強い上、数字的にも一つの物件のインパクトが非常に大きいという側面も持ちます。
こうした事情は、「社員の“ブランド”に対する不理解」、場合によっては「拒否反応」を招く事があります。
具体的には・・・
・ブランドがどうこう言う前に、とにかく買える土地を仕入れないと意味がない
・いい土地を仕入れれば売れる。売れればその実績がブランドになる
・土地を買った時点でどういう建物が立てられるかはだいたい決まっている
・買った土地(商圏商圏に於ける競合物件)によって広告も営業も全く違うから、ブランドなんてむしろ邪魔
・ 住宅のブランドが担保すべきは、せいぜい「安全」「信頼」くらいのものだ
このような認識や反応が根強いということです。
そして、分譲住宅事業において、こうした認識は「部分的に正しい」ところが、住宅ブランドのブランディングにとって解消困難なボトルネックだとも言えます。
つまり、これらの特徴から言えることは、住宅ブランディングでは、社員の”ブランド”に対する「拒否反応」を取り除くための「インナーブランディング」を強める必要があるということです。
以上、住宅業界のブランディングにおける4つのポイントをお伝えしました。
次回は、この4点を踏まえて実際にどのようなブランディング活動をすべきかについて述べたいと思います。