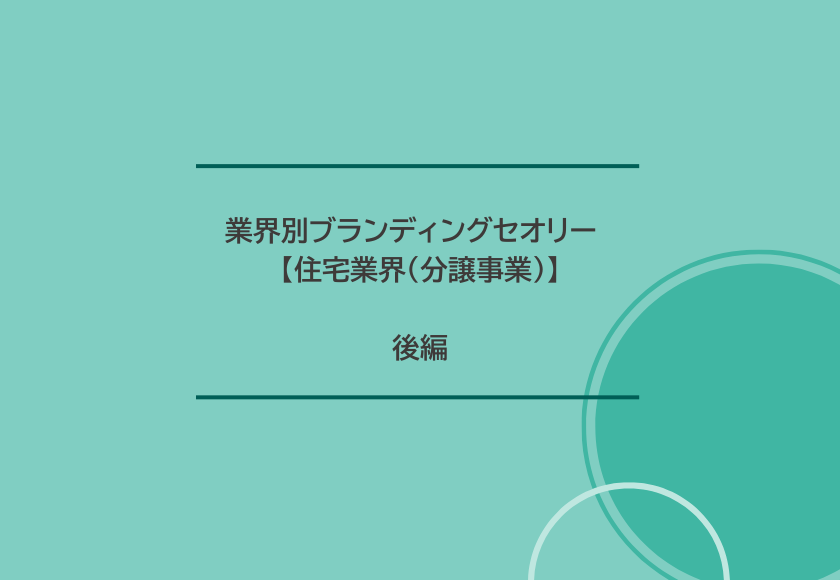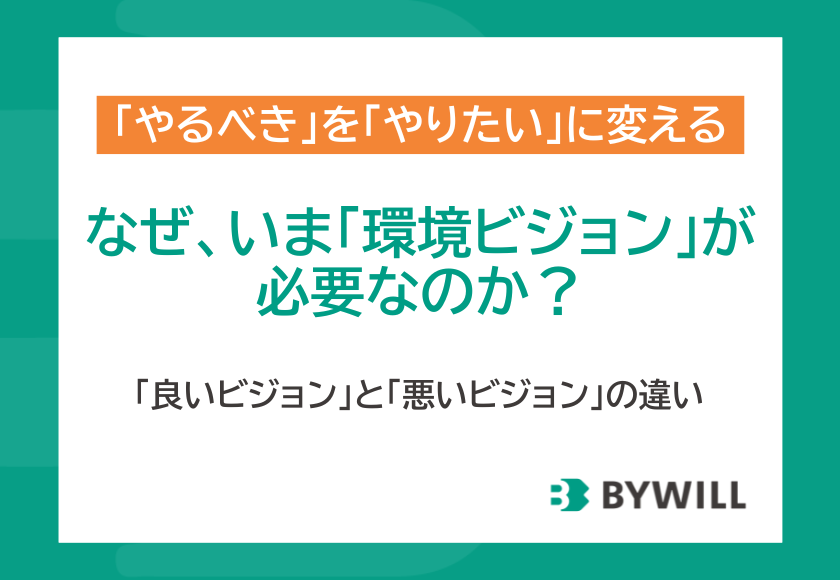こんにちは。取締役の伊佐です。
さて、色々と書かせていただいた【住宅業界(分譲事業)のブランディングセオリー】もようやく後編となりました。中編でお伝えした「4つのポイント」に紐づいて、私の実績・経験をもとに具体的なブランディング活動についてお伝えします。
■前回お伝えした住宅ブランディング4つのポイント
まずは、前回のコラムでお伝えした住宅ブランディングのポイントです。
住宅業界の市場動向や商品特性を踏まえて、以下のような点に留意することが大切です。
【Ⅰ】住宅市場の縮小と寡占化が進んでいるからこそ、「一刻も早く、市場において検討時想起順位5位以内の地位を確立するために何ができるか」をまず考える
【Ⅱ】超高額で接点が少なく、同一商品が一つもないからこそ、ブランディングのセオリーである「全ての顧客接点での一貫した顧客体験によってブランド価値を蓄積するのが難しい」ということを前提にブランディングの施策を組み立てる
【Ⅲ】「売り手と買い手の情報格差」が縮小しているからこそ、ブランドコミュニケーションにおいて、「どのメディアで」「どのような情報を」伝えることが必要なのかを、現在の消費者の住宅検討~購入プロセスに合わせて再設計する
【Ⅳ】仕入が困難、且つ事業や商品に対するインパクトが大きいからこそ、特にインナーブランディングを強める
■具体的なブランディング施策の考え方
「想起順位5位以内」が必要なワケ
上記ポイントの【Ⅰ】にある「検討時想起順位5位以内」というのは、
弊社が過去に実施した住宅購入に関する調査に基づいています。
=======================================
調査結果のポイント
①住宅を購入する際に、比較検討した平均的な物件数は5件程度
②購入する前には必ずモデルルーム等の販売所を訪れている
③販売所を訪れる前にインターネットなどで5件程度まで候補を絞り込んでいる
④単純な条件だけであれば、該当する物件は5件以上あった
=======================================
上記調査結果の中でも、注目したいのは③と④です。
一般的な消費者は、住宅購入の際にはほぼ必ず販売所を訪れます。そして、そこで「どの物件の販売所に行くか」という最初の「選択」がなされるのですが、その「選択」は、5件以上ある候補から5件程度まで、比較検討の「条件」だけではない何かによって絞り込まれている、ということです。
ここに、住宅事業でブランディングをする最大の意義があります。
物件ごとの検討母集団=販売所訪問者数を効率的に形成するために、「検討時想起順位5位以内」である必要があるのです。
そのためにすべきことは、規模や戦略によって大きく2つに分かれます。
<規模が大きい≒展開エリアが広いブランド>
継続的なマスプロモーションによって好意的認知を拡大させる
<規模が大きくない≒展開エリアを絞り込みやすいブランド>
敢えて戦略的に展開エリアを絞り込み、そのエリア内供給量を常に一定以上に保つ
自社ブランドの目指す規模や展開エリアに応じて、
想起順位UPのために適切な方法を検討していきましょう。
ブランドプロモーションの考え方
特に規模が大きく展開エリアが広いブランドにとっては、ブランドの好意的認知を高めるプロモーション活動が必要不可欠ですが、ここからは、その考え方をお伝えします。
まず前提として、「ブランドプロモーション」と「物件毎の企画・販促」の役割を明確に切り分ける必要があります。
<ブランドプロモーションの役割>
ブランドとしての好意的認知拡大と、その結果としての検討時想起順位を上げるために実施する
<各物件の企画や販促活動の役割>
ブランドプロモーションで訴求しているイメージやベネフィットなどと接続された“物件の特徴”を端的に伝え、購入決定してもらうために実施する
「ブランドプロモーション」と「各物件の販促活動」の区別は難しいですが、クリエイティブに関するトーン&マナーの統一感を高めることで、「各物件の販促活動を通じたエリア内ブランドプロモーション」として考えるのが良いでしょう。
ブランドプロモーションでは、検討時想起順位を上げることを追求したクリエイティブとメディア選択をする必要がありますが、それと同時に、「展開するどの物件とも接続可能な要素」も併せて訴求していく必要があるというわけです。
それらを担保するために必要なのが、構造的に整理されたブランドコンセプトです。
市場とターゲットを明確に定義した上で、
コアバリュー: ブランドの提供価値を端的に表現したもの
ベネフィット: コアバリューを「ターゲットにとっての便益」に要素分解したもの
エビデンス : ベネフィットを感じてもらうために(全ての物件で)備えるべき論拠
を整理し、ブランドとしてのキャラクターやイメージを設定し、徹底的に一貫性を持たせます。
住宅ならではの”タイムラグ”を活かしたプロモーション設計をしよう
また、ブランドプロモーションは、あえて先行実施することも必要です。
住宅事業の特性として、新しくブランドコンセプトを策定したとしても、それを反映した実際の物件が販売され、入居者が居住し始めるのは2~3年後になるということがあります。
その間は「ブランドプロモーションで訴求していることと実際の物件にギャップが生じる」リスクがありますが、むしろこの期間を「先行プロモーションで好意的認知と検討時想順位を上げる期間」と捉え、イメージ訴求を強めることが有効なのです。
これもブランディングのセオリーからは外れますが、住宅購入については、「販売所訪問前の情報収集や検討」と、「販売所を訪れた後の、実際に購入するつもりで行う情報収集や検討」を、全く切り離して考えた方が良いというくらい差があるからです。
乱暴な言い方をすれば、「販売所への集客は、何となくのイメージ訴求でも可能(=だからブランドプロモーションで担保できる)」ですが、「販売所訪問後の購入決断は、逆にイメージなど関係なく成される(=だから各物件の販促・接客などで担保すべき)」ことがほとんどなのです。
更に、住宅という構成要素が多い商材では、各物件の詳細なスペックの理解や比較評価が難しいため、ブランドとしてのイメージが各物件の商品評価に与える影響が大きいという側面もあります。
我々の研究でも、タイムラグ期間(=ブランドプロモーションの訴求要素と実際の物件にギャップが生じるリスクがある期間)のブランドプロモーションによって好意的認知が上がった結果、その期間の商品性に変化はないにも関わらず、消費者の商品評価が軒並み向上した、という結果も出ています。
担当者によって異なる”ブランド”への認識
前述ポイントの【Ⅳ】で述べた「仕入が困難、且つ事業や商品へのインパクトが大きい」ということは、各部署・担当のブランドに対する認識にも影響を及ぼします。
以下は、以前私が携わったある企業様での実例です。
◆仕入担当Aさんの認識
「良い土地を適正価格で仕入れれば勝てる」
「その結果として自然とブランド化する」、あるいは「ブランドは不要」
◆商品企画担当Bさんの認識
「全ての物件にブランドとして統一感を出すことなど不可能だ」
「ブランドがあるせいで仕事がやりにくくなる」
◆営業担当Cさんの認識
「現場は商圏内の競合環境や販売所を訪れるお客様一人一人に向き合っている」
「抽象度の高いブランドは、個別の物件とはあまり関係ない」
これらは、この企業だけでなく住宅業界では不可避といっても良い、役割による認識のギャップです。
しかし、これらは「仕方ない」で済ませることができないブランディングの大きなボトルネックになり兼ねません。
なぜならば、分譲住宅事業でも、「広告宣伝活動だけでブランドは確立し得ない」というブランディングセオリーは真実だからです。
役割を超えて社内を統合するインナーブランディング
特にブランドプロモーションを先行させる場合は、ブランディングを継続的且つ一貫性を持って実践していくための仕組みづくりを取組初期から実施していくことが重要です。
◆ブランディングのロードマップと役割分担・基準の整備
企業として中期経営計画があるように、その経営計画とリンクした「ブランディングの中期計画」を策定することが有効です。
そもそもブランドが何を目指すのかというミッションと、やるべきことが何で、それぞれ誰(どの部署)が担当するのかという役割分担と、どういった方針で、どの程度のレベルまでやるのか、その指標(KPI)が何かという基準を明確に規定し、運用していくことが必要となります。
また、これらの策定プロセスに各部署の意思決定権者を巻き込み、合意形成をしながら進めることも、認識の食い違いを解消するために有効なポイントです。
◆リアルな「場」を通じた意識や認識の共通化
どのような計画・役割分担・基準を整備しても、それだけで認識の食い違いやブランディングのボトルネックが解消する訳ではありません。
特に大企業では、成果物をイントラネットやメールなどの社内コミュニケーションツールを通じて「伝える」ことで済ませてしまいがちです。
しかし、重要なのは「伝える」ことではなく「伝わること」です。
左脳だけではなく右脳で、頭だけではなく心で、共感や納得感を得られて初めてメンバーのブランディング実践行動を誘発できます。
ブランドやブランディングに対するネガティブな認識が不可避的に起こる住宅業界では、特にそのきっかけとしてのリアルな「場」の重要性が高いと言えます。時間的・人的コストがかかっても、コンセプト共有会などのリアルな「場」を継続的に持つことが必要なのです。
また、社内へのブランド浸透も、社外のそれと同様にキャズム(断層)が存在します。
そのキャズムを超え、臨界点を超えられれば、インナーブランディングを意識せずともブランドが根付いて自律的なブランドマネジメントがなされる状況になりますが、それまでは「まずは最初の2割の強い共感をどう生み出すか」という視点で、こうした「場」を持ち続けるべきなのです。
◆目標設定やマネジメントへの反映
最終的には、ブランド起点の考え方や行動が、社内で完全に定着する必要があります。
そのためには、インナーブランディング初期~中期には強制力として作用し、その後はリマインダーやインセンティブとして作用するように、諸制度に落とし込むことが有効です。
例えば、下記のようなものが挙げられます。
・部署や個人の目標設定の内「最低ひとつはブランドに関する項目を定め、評価の○%分加味する」というルールを設定する
・ブランディングの部署別KPIの進捗を確認し、課題とアクションプランを議論する会議体をルーティーン化する
・管理職対象の研修メニューに「ブランド研修」を、あるいは、昇格試験や資格が定められている場合には、そこに「ブランド」要素を組み込む
「ブランドロードマップ(長期計画)と役割分担・基準」
「リアルな「場」を通じた意識や認識の共通化」
「目標設定やマネジメントへの反映」
この3本柱を段階的に取り組み、「ブランディングを実践することが当たり前である」という風土と状況を作り上げることが、住宅業界のブランディングでは特に重要だと言えるでしょう。
住宅業界に携わる方や、これまでにお伝えした「特徴」「要素」「注意点」が
共通する事業者の方々に参考にしていただければ幸いです。