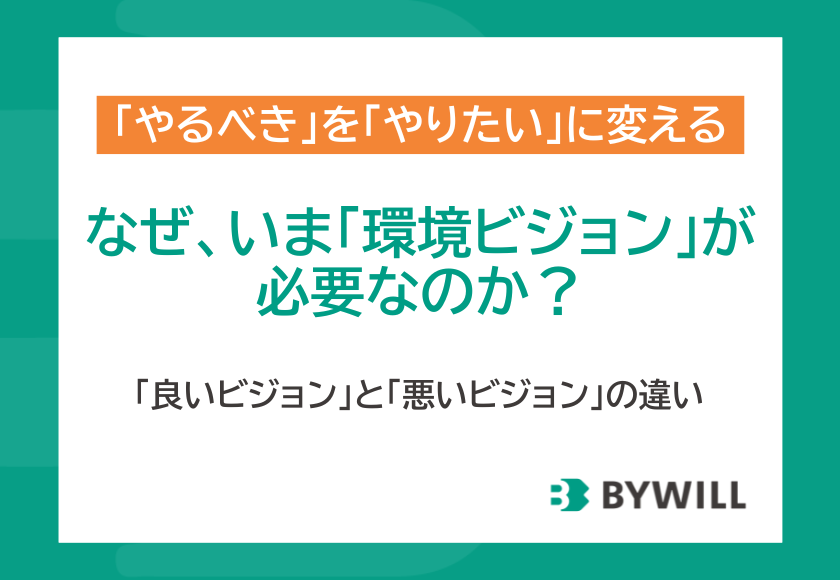みなさんこんにちは。取締役の伊佐です。
ブランド戦略に特化したコンサルティング会社である弊社は、これまでの経験と理論に基づいて、様々なクライアント様やセミナーにご参加いただいた方々に対して、「アウターブランディング偏重ではなく、インナーとアウターの両輪でブランディングを進めないと、いずれ一貫性と継続性を保てなくなりブランディングは失敗します。」とお伝えしております。
今更言うまでもなく、漸く世間でも「インナーブランディングが大切」や「CS向上を目指すならまずES向上」などが当たり前に言われております。
しかし、こうした考え方は分かっていても「ES向上➡CS向上」「インナー➡アウター」が、どのように繋がっているのかを、具体的にイメージできていない、あるいは、それを信じきれていない方が、クライアント様の中にも意外と多いのです。
そこで、今回は、私の消費者としての経験や、最近クライアント様とのお話の中で出てきた具体例を用いて、「インナーとアウターの繋がり」をお伝えしたいと思います。
✓某自動車会社のディーラーで点検整備をお願いした電話にて・・・
我々も、実はブランド戦略セミナーで「ブランディングの成功例」として取り上げさせていただいています。
しかし、先日、私が点検整備をお願いした際に、らしからぬ対応に遭遇してしまったのです。
最初の予約時の電話対応で、自分の車の型番を伝え、どのくらい時間がかかるのかをお聞きしたときのお話です。
対応してくれた女性オペレーターは、「持ってきていただかないと分かりません。目安ですか?お答えしかねます。ケースバイケースで様々なもので・・・。一応、予約だけなさいますか?いずれにせよ、持ってきていただいてからでないとお答えはできませんが。予約に関しても、一旦こちらでお受けして、そのお時間でご対応可能かどうかを、後でご連絡させていただきますので。」
・・・このような対応をされて、こちらがどう感じるか、語らずともご想像いただけると思います。下手に所要時間を答えて、それを超過した際のクレームを回避する目的であったとしても、流石に某自動車会社のディーラーとして、この対応は期待を裏切っていると言わざるを得ないでしょう。
実際に、ディーラーでの対応や点検終了した車を引き取った後に車の調子を確認する丁寧なお電話は、流石のひとことでした。
しかし、既に私の中に入ったネガティブな印象が消えることはありませんでした。接客の一貫性がいかに大事か、ということを身を持って体験してしまったのです。
加えて、こうした具体的な「接遇」や「トーク」は、マニュアル化によって解決することが非常に難しいものです。マニュアル作成や従業員のトレーニングが困難なだけでなく、実際は、話すスピードや間の取り方、トーンや抑揚などによっても、相手が受ける印象は変わってしまうからです。
したがって、ビジネスプロセスの中で「接客」「電話対応」などの「対人コミュニケーション」が不可欠な企業様は、アウターブランディングの質的向上は難しい課題であるはずです。しかし、誤解を恐れずに言えば、アウターブランディングは、結局は『個人レベル』でその会社で働くことや自分の役割にプライドを持ち、深く理解できているかという点に集約されると言えるでしょう。
そのように考えると、アウターとインナーには繋がりがあり、こうした課題もインナーブランディングの強化によって解決していくべきことではないでしょうか?
✓総合不動産デベロッパーのクライアント様とのディスカッションにて・・・
先日某総合不動産デベロッパーのオフィス事業ブランディングのご担当者様とお話しさせていただいた際に、「TVや新聞でマス広告を打っても効果は薄いので、インナーブランディングの強化を重視し、様々な取組みを行いました。ブランドステートメントを作り、クレドを作り、表彰制度を作り、社内ポスターを作って張り、分科会などの社内的な情報共有・サービス向上・意識高揚の場を設けました」というお話をお伺いしました。
そしてその後続いた内容は「しかし、お客さま(テナント)のクレーム減少や、満足度向上などのポジティブな反応がなく、管理人など当事者の意識・行動も変わりませんでした。やはりインナーブランディングをアウターブランディングに繋げるのは無理なのでしょうか・・・それとも、BtoBでブランディングを成功させること自体が無理なのでしょうか?」というものでした。
この方からは「一般的にインナーブランディングでやるべきこと」を一通り実施されている印象を受けました。また、BtoBビジネスでは、BtoCビジネスのブランディングに比べ、顧客の判断がより経済合理軸によって成されやすいなど、なかなかアウターブランディングを成功させるのが難しいことも確かです。
しかし、更に具体的にお話を聞いてみると、
・ブランドステートメント&クレド
→ブランディング担当者が代理店と作成
・表彰制度&社内ポスター
→表彰者やプロジェクトを選定・発表し、福利厚生費を割いて副賞を授与
ポスターは取組初期に代理店と作成し、各事業所に一律で張り出し依頼
・分科会
→分科会メンバーを選定し、テーマ設定、進行を一任。年に4回の結果報告を実施
という形でインナーブランディングを行われているようでした。
一見、おかしなところの無い、極めて一般的な取組みに見えますが、実はここに改善すべきポイントがあったのです。
これらの取組みをよくみてみると、「一連の取組みを受けて、自分の会社や仕事に対するプライドや理解を深められる人がどれだけいるのか。」という視点で計画・実施されておらず、形だけのものになってしまっていたのです。
―なぜ、ブランドステートメントやクレドを作る際に、それを「落し込むべきターゲット=自社やパートナー会社の従業員」を巻き込まなかったのか?
―なぜ、表彰制度は「受賞を逃した人が何を感じるか?」の視点で設計されていないのか?
―なぜ、社内ポスターは、一度作成されて以降、ただ張りっぱなしにされているのか?
―なぜ、分科会メンバーを募らず、結果を報告させるだけなのか?
もちろん、ヒト・モノ・カネ・ジカンが有限な中、止むを得ない事情の中でそうしたのでしょうが、先述の通りブランディングの難しいBtoBビジネスだからこそ、インナーブランディングを個々人の意識まで強烈に浸透するレベルまで行わない限り、ブランディングはただのヒト・モノ・カネ・ジカンの浪費と化します。
繰り返しにはなりますが、対人コミュニケーションを伴う企業様では、従業員の個人レベルまで、その会社で働くことや自分の役割にプライドを持ち、深く理解できているかがアウターブランディングにも影響してくるのです。
いかがでしょうか?少しは皆様に、「インナーブランディングとアウターブランディングの繋がり」や「アウターブランディングの質を高めるには、まずインナーから」ということをお伝えできたでしょうか?
何か感じるものがあった方は、まず、自社のインナーブランディングに関する取組みが、従業員の方々に、その会社で働くことや自分の役割にプライドを持っているのかについて個人レベルで見つめ直すところから始めてみてはいかがでしょうか?何か、自社のブランディングの効果を高める改善点が見つかるかもしれません。