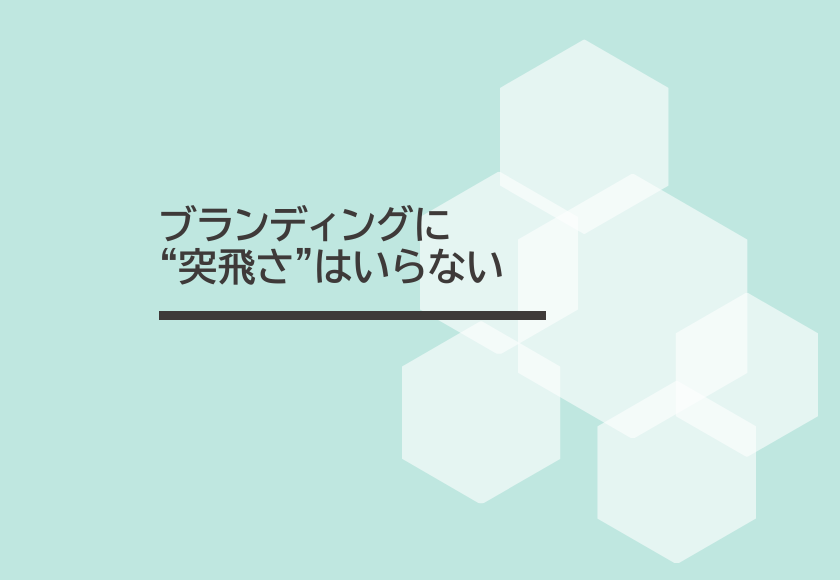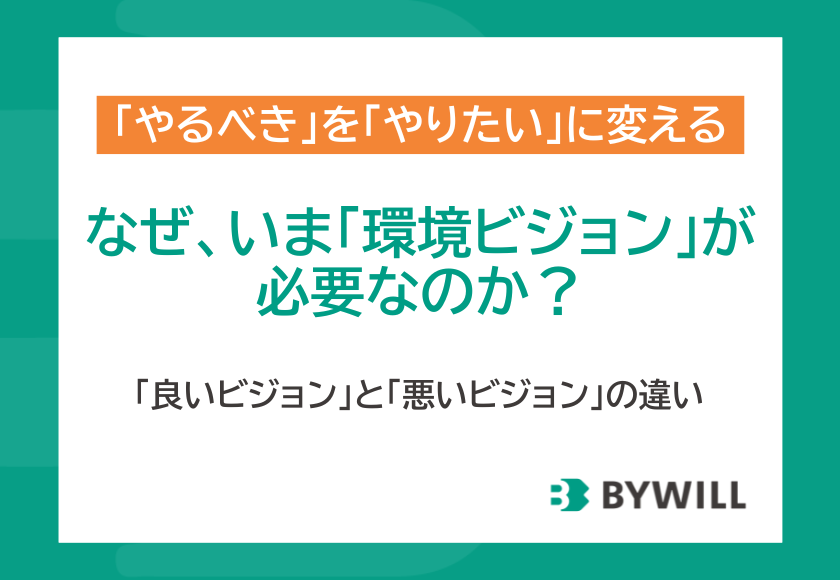こんにちは。シニアコンサルタントの早川です。
今回は、先日私がダイエットを始めた際のある出来事から、ブランディングについて書いてみたいと思います。
―遡ること1ヶ月前―
妻より凄い剣幕で「痩せて欲しい。一緒に歩いていて恥ずかしい。」と言われ、ランニングによるダイエットを本格的に始動することを決意。(食事制限は、性分に合わず・・・笑)
―先日―
まずは恰好から入ろうと考え、ニューバランスの直営店に足を運んでみました。
販売員と会話をしていて、初めて知ったことが2つ。
「社名の由来は、履いた人に”新しい(new)、バランス(balance)感覚をもたらすことによる。」
「ファッションシューズで価格の開きがあるのは、製造拠点によるもの。(USA製の一部は、現在でも職人の手で作られている)」
そこで、ニューバランスにさらに興味がわき、会社の歴史について調べてみると、実はこの会社、元々は1906年、アーチサポートインソールや矯正靴のメーカーとして誕生していたのです。
そんなニューバランスの現状は、“ニューバランス=おしゃれ”が完全に定着し、“ファッションアイテム”として、男性だけでなく女性や子供にも人気なブランドとして確立しています。
ここで疑問となるのが、「自分が学生のころには、そこまで幅広い層に支持をされるようなブランドではなかったよな?では、なぜ、ニューバランスに対するイメージに劇的な変化が起きたのか?」という点です。
上記の疑問に対して、少し考察してみたいと思います。
前提として、現状のニューバランスの商品カテゴリーのうち、著しく成長しているのは「ライフスタイル(ファッションシューズ)」「キッズ」「ランニング」の3つです。
簡単に各カテゴリーで考えてみると・・・
「ライフスタイル」「キッズ」に関して
1990年代の日本では、男性を中心に「ナイキエアマックス」「コンバースオールスター」に代表されるようなスニーカーブームが起こったものの、ニューバランスはコアファンにしか受け入れられていませんでした。
その理由の一つは、当時流行していた“カラーバリエーション”や“過度なソール、クッション材の使用”を一切行わず、
①創業当初から変わらない、落ち着いた色味のみを展開
②矯正靴であったノウハウをベースとした、履き心地を徹底的に追及
を行い続けていたことです。
しかし、実際は、これが重要な成長の種であったと、個人的には捉えています。
なぜなら、ニューバランスは上記①②をブラすことなく続けていたため、「男性ミーハー層は、ナイキorコンバース」「流行に左右されない男性マニア層は、ニューバランス」という棲み分けが自然と構築され、ニューバランスの成長に繋がったと考えるからです。
そして2000年代に入り、「その男性マニア層が家庭を持ち、“ニューバランスのブランドストーリーに裏付けされる機能性、履き心地”を家族に伝えていたこと」「同時期に人気モデル・著名MD等がファッションアイテムとして取り上げる様になったこと」が重なり、現在のブランドイメージが醸成されたと考えられます。
このようにみると、男性コアファンの心を掴みつづけて、「男性コアファンが好むスニーカー」から「ファミリーや女子がファッションとしても楽しめるスニーカー」へと変貌した、珍しいブランドだと言えそうです。
「ランニング」に関して
前述の「ライフスタイル」に注力する傍ら、2000年代から「ランニング」のマーケティング活動にも注力しており、ランニングイベントのサポートや協賛を続けています。その方法も、ただ会場にロゴ掲出しブース出展するだけでなく、近年では“ニューバランスのランニングイベントでしか味わえない体験”をつくり出しているといえます。
例)
・湘南国際マラソンでは、大会前にコースの動画をWebサイトで公開して、下見をしてもらうよう情報発信。
・東京マラソンでは、GPS連動ソーシャルゲームと連携して、限定アイテムが獲得できるような仕掛けを準備。
・リアル店舗での購入体験をFacebook上で実現させる試み。
参加するランナーが何を考えてどういったことを望んでいるのかを把握し、バーチャルとリアルの融合を図り、ファンとの関係性を築きあげているのです。
さらに、2016年に世界第3位のスポーツブランドになる目標を掲げているニューバランスは、
・2010年にテニス領域に参入し、ランキング最高位4位のラオニッチ選手と契約
・2010年にベースボール領域に参入し、現在MLBのスパイクシェアを3割以上に伸長
・2015年からフットボール領域に参入し、イングランドのリバプール等とサプライヤー契約・ヤヌザイ選手等と契約
など、現在、主要の「ライフスタイル」「キッズ」「ランニング」以外のスポーツカテゴリへの進出にも力を入れています。
上記を踏まえて、ニューバランスにみるブランド拡張戦略について整理します。
【ブランド拡張戦略】
・商品の同質化が究極まで進んでいると言われている中、一部の人しか味わえない濃いブランド体験価値をいかに広げていけるか
【アプローチ】
・流行への過度な対応を行わず、自らの強みを一貫して訴求し続ける
・上記によって、ブランドに共感し、ストーリーを語れるコアファンを育てる
・顧客と分野の拡張(顧客:男性コアファンから女性&ファミリー、分野:ライフスタイルやランニングからスポーツカテゴリ全般)
・ブランド価値は時代を超えて一貫性を保つが、それを伝える手段は時代に対応する(近年のバーチャルとリアルの融合)
改めて考えると、ニューバランスの戦略に“突飛なこと”はないことがお分かりいただけると思います。
最後に紹介したいのが、ニューバランスのブランドコミュニケーションチームマネージャーのインタビュー記事です。
「経理やシステム部門、人事・総務など、実際のプロダクトや営業活動と直接かかわっていない部署に対しても、情報や意識の共有は必須です。必ずしも、営業やマーケティングの人間だけがニューバランスの顔ではない。名刺にブランドのロゴを載せている以上は、誰もがニューバランスの顔であり、ブランドのプレゼンテーターだと考えています。」
※「netpr.jp」2014年8月27日記事より http://netpr.jp/case/14550/
つまり、突飛な戦略よりも、戦略を支える仕組みや従業員の共通認識が重要というわけです。
上記の考え方の下、弊社がブランディングをお手伝いする際には、「従業員の方々が自ブランドに対してどう思うか?」をまず調査します。
弊社はコンサルティングを生業にしていますので、いわゆる”パッケージ化”された商品は少ないですが、数少ない商品(プロダクト)として、ブランド浸透度調査「BranDoctor」を保有しています。
「ブランドを創り出す主体である、従業員へ着目していること」
「ブランドビジョン・コンセプト等を実現するために必要な、アクションに繋がる課題抽出が可能であること」
「ブランド浸透度を、定量的に測れること」などの特徴がある調査です。
おかげさまで株式会社フォワード(現:バイウィル)というコーポレートブランドの認知は少しずつ拡がってきておりますが、これからはプロダクトブランド「BranDoctor」をもっと皆様に認知して頂けるよう、サービスの充実に努めて参ります!