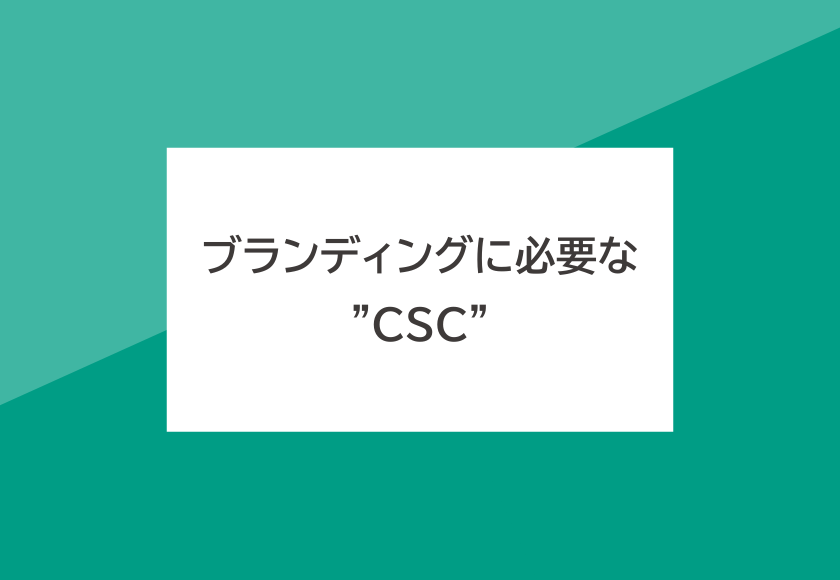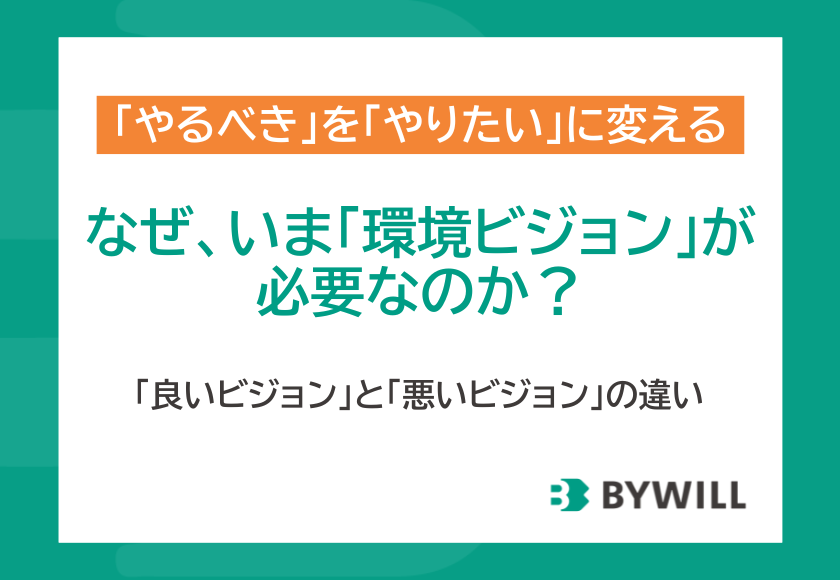こんにちは。取締役の伊佐です。
前回は「ブランディングの落とし穴」について、
様々な企業のブランディングの進め方や考え方のパターンごとにご紹介しました。
要約すると、
①『内発型』⇔『外部適応型』
内発型の落とし穴:検証不足による「当たるも八卦、当たらぬも八卦」
外部適応型の落とし穴:顕在ニーズ後追いによる「大ヒット不在」
②『トップダウン型』⇔『ボトムアップ型』
トップダウン型の落とし穴:トップ依存・属人化による「自律的マネジメント不全」
ボトムアップ型の落とし穴: 人的・時間的コスト過多による「スピード・推進力不足」
③『コンセプト重視型』⇔『アウトプット重視型』
コンセプト重視型の落とし穴:アウトプット反映の軽視による「収益力不足」
アウトプット重視型の落とし穴:アウトプット偏重による「PDCA不全」
といった内容でした。
今回は、これらも踏まえて「ブランディングを成功させるには?」について
お伝えしたいと思います。
まずはその前提として、ブランディングが成功した状態について確認しておきましょう。
ブランディングの成功例、と言われて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?
ハイブランドでありながら、今や日本では誰もがひとつくらいはアイテムを持っていると言わんばかりの浸透力を誇るルイ・ヴィトン?
圧倒的な価格優位とチャネル展開、そしてシンプルながら独自の開発力と新たなチャレンジで成長を続けるユニクロ?
グローバルブランドランキングでトップを走り続けるコカ・コーラ?
次々と画期的で業界に捕われないなサービスを提供し続けるIT業界の雄であるグーグルやアマゾン?
“ブランド”の捉え方や、何を以ってブランディングの“成功例”と評価するのかによって、人それぞれ思い浮かべることは様々でしょう。そして、上記のブランド群は全て、成功例として挙げてなんら問題のないものだと思います。
しかし、私がコラムで最初に述べた「ブランドとは、選ばれ続ける力」という定義に立って、敢えて上記のブランド群に共通する要素を抜き出すことで、「ブランディングが成功した状態」と言えるために必要なことを挙げるなら、
A.識別記号(ブランドネームやロゴなど)と知覚価値(「●●(ブランド)と言えばコレ」という意識・無意識で感じている価値)が連動・確立している
B.Aによってステークホルダーの選択判断が簡略化されている(常に完全にフラットな比較検討をされることなく自ブランドに有利な判断を引き出せる)
C.Bによって、ブランドが経営の効率化・収益力の向上に繋がっている
D.Cによって、ステークホルダーから見てそのブランドに一貫性を感じるまでに、中長期的にブランディング活動がルーティーン化されている
と言ったところでしょうか。
逆に言えば、上記A~Dが満たされていないブランドは、外からどう見えようとも、あるいはメディアがどう報じていようとも、「ブランディングの成功例」とは言えないと私は考えています。
では、上記A~Dを満たし、且つ、前述の「ブランディングの落とし穴」①~③を回避・克服するためには、何が必要なのか。(これが、冒頭で掲げた「ブランディングを成功させるには?」のアンサーに当たります。)
私たちはこれを「ブランディングに必要なCSC」として標榜しています。
即ち、
Concept ブランドの根幹たる思想・概念や提供価値
System ブランドのコンセプト(上記Concept)を、継続的、且つ一貫してアウトプット(ブランドと顧客のあらゆる接点)に反映させるための業務上・組織上の仕組み
Contact ブランドと顧客のあらゆる接点=ブランドの成果物
が、全て統合的に設計・運用され、機能していることが、ブランディングを成功させるために必要だと考えている訳です。
次回コラムでは、「ブランディングを成功させるには?」の第2弾として、この「ブランディングに必要なCSC」をひとつづつ噛み砕いて書いてみたいと思います。