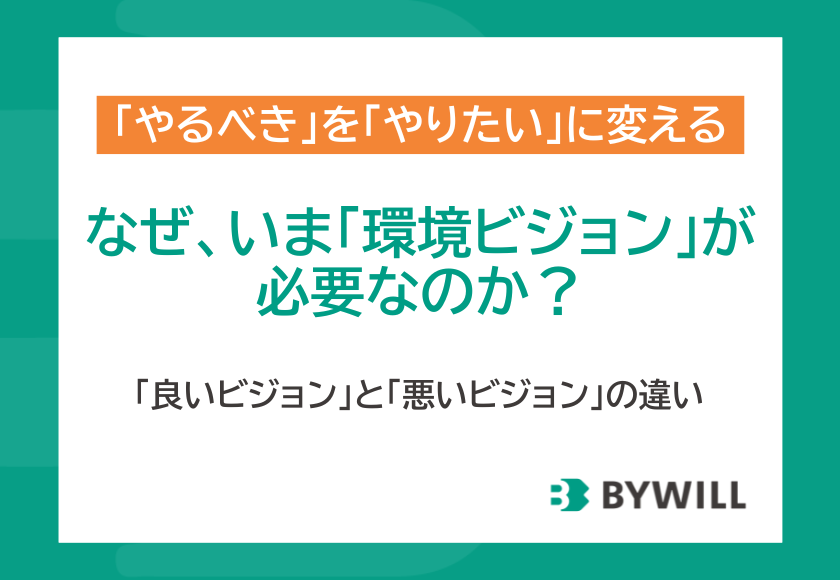マクセルと言えば、国内初の国産アルカリ乾電池生産や国内初のカセットテープ商品化などを手がけるmaxellブランドで、広く認知されている会社だ。しかし、2017年10月に日立グループから独立し社名を変更。さらには、事業ポートフォリオ変革の真っ只中にいる。この大きな変革のタイミングで、マクセルはどのようにリブランディングに取り組んでいるのか。「組織改編前のブランド」「組織改編後のブランド」「マクセルグループとしての成長戦略とブランド」という3つのフェーズに分けて、具体的な取り組みが披露された。
【マクセルホールディングスHP】https://www.maxell.co.

■プロフィール
マクセルホールディングス株式会社 理事 ブランド戦略・広報IR担当
兼マクセル株式会社 理事 ブランド戦略統括本部長 小原 寛氏
マクセル株式会社 ブランド戦略統括本部 企画部 部長
兼マクセルホールディングス株式会社 ブランド戦略・広報IR部 担当部長 平 健介氏
株式会社フォワード(現:バイウィル)
取締役副社長 伊佐 陽介
イベント実施日
2019年7月10日(水)
17年に日立グループから独立し、リブランディングをスタート
伊佐陽介(以下、伊佐):本日のテーマは、「『リブランディング』で経営層が心得ておくべき5つのこと 」です。マクセルホールディングスの小原さん・平さんをお迎えして、お話をお伺いしていきます。
小原寛氏(以下、小原氏):皆さま、こんにちは。マクセル株式会社ブランド戦略統括本部の小原と申します。2015年に日立からマクセルに移り、去年の4月からブランド戦略本部に所属し、広報IRとブランディングの責任者をしています。
平健介氏(以下、平氏):マクセル株式会社ブランド戦略統括本部の平です。私は1994年に日立マクセルに入社しました。ブランドの仕事に携わるまでは、一貫して営業畑です。まだブランディングについては勉強中の身ではありますが、この2年間で我々が取り組んできたことについて、本日は共有できればと思っています。
 <マクセルホールディングス株式会社 ブランド戦略統括本部長 小原 寛氏>
<マクセルホールディングス株式会社 ブランド戦略統括本部長 小原 寛氏>
小原氏:取り組み内容の話に入る前に、簡単にマクセルについてご説明します。1961年創業、従業員は全世界連結で5,400名いる会社です。事業内容は、一次電池・二次電池といったエネルギー領域、テープやフィルムといった産業用部材料領域、理美容・プロジェクターといった電器・コンシューマー領域といった、セグメンテーションで分けています。
売上高はおおよそ1,500億円で利益は50億円強。2007年まで少しずつ利益が下がっていまして、2008年から2010年は3期連続で最終赤字に。その後、再上場に向けて少しずつ回復基調にあるというところです。
1つお伝えしておきたいのは、2006年当時、テープやディスクといった記録メディアの売り上げは53%ありましたが、2017年には5%に。つまり、BtoCから、材料やデバイスを売るBtoBのカンパニーに変貌しているのです。現在の売り上げ構成比は、エネルギー領域・産業用部材料領域・コンシューマー領域の3つが拮抗している状態です。
伊佐:ありがとうございます。2017年に日立グループから独立して、持株会社体制がスタートされた。その際にリブランディングの活動をスタートされたと認識しています。まず、『組織改編前のブランド』という観点でお話しいただければと思います。
組織改編前に抱えていた2つの問題。「推進役の不在」と「はっきりしないブランドコンセプト」
小原氏:日立から独立する前のマクセルがどういう状態だったか。社内・社外に対して、それぞれ強み・弱みという観点で整理しました。

例えば社外という点で、弱みは事業ドメインが広く、何をやっている会社なのかわかりにくいということ。それから、カセットテープというイメージがついて回ること。ここまで覚えて頂ける事業を運営していることはありがたいことでもあります。しかし、超えなければいけないハードルになっていると理解しています。
独立前のマクセルのブランド管理というのは経営戦略マターで、日立のブランドマネジメントにお任せ状態であり、事業ポートフォリオを大きく変えていく中で、ブランドイメージを訴求できないジレンマがありました。
ブランドコンセプトを作ったり、サブブランドのポートフォリオを描いたり、ブランドの管理を徹底していったり…色々と施策を打ったのですが、大きな成果を出せないという状況でした。
問題としては2点あったと考えています。まず、責任ある部署が取りまとめを推進していくべきですが、その推進役が不在だったこと。そして2点目は、ブランドコンセプトやメッセージの骨子がはっきりしていなかったことです。これを受けまして、『責任ある取りまとめ部署を作って推進すること』『ブランドコンセプトを明確にし、それに基づくメッセージを発信していくこと』。この2つが、独立前のマクセルの課題でした。
すべての会社に起こる、3つの壁
伊佐:ありがとうございます。独立前のマクセルということでお話をいただきました。私からは、業界や企業規模・そして置かれているフェーズに関係なく、ブランディングを行う上で、様々な会社に共通して起こる『3つの壁』についてお話ししたいと思います。

ブランディングのことを差別化という人もいれば、付加価値という人もいる。 期待と呼ぶ人もいます。これはつまり、曖昧で捉えにくいということでもある。ということは、社内外問わず『理解・共感の壁』があると言えるでしょう。
それから、ブランディングの成果や進捗度合いというのは、そもそも可視化・共有化しにくいもの。そこにも壁があります。つまり『可視化・共有化の壁』です。そして最後は、『業務接続の壁』です。ブランディングを進めていくために、各社員が何をすればいいのかというレベルにまで落とし込めている会社さんは、少ないということです。
 <株式会社フォワード(現:バイウィル) 取締役副社長 伊佐 陽介>
<株式会社フォワード(現:バイウィル) 取締役副社長 伊佐 陽介>
この3つの壁は珍しいことではなく、むしろ多くの企業で起こることだということを頭に入れておいていただければと思います。では、『組織改編後のブランド』ということで、独立後に何が起きたのか、何をどう変えて進めていったのかをお話いただきたいと思います。
マクセルグループから学ぶ、『リブランディング』で経営層が心得ておくべき5つのこと(中編:独立後)
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング