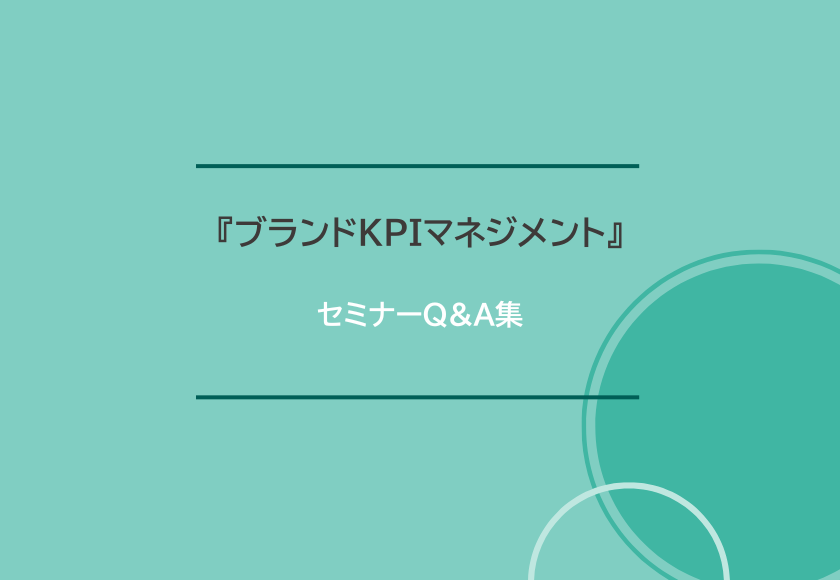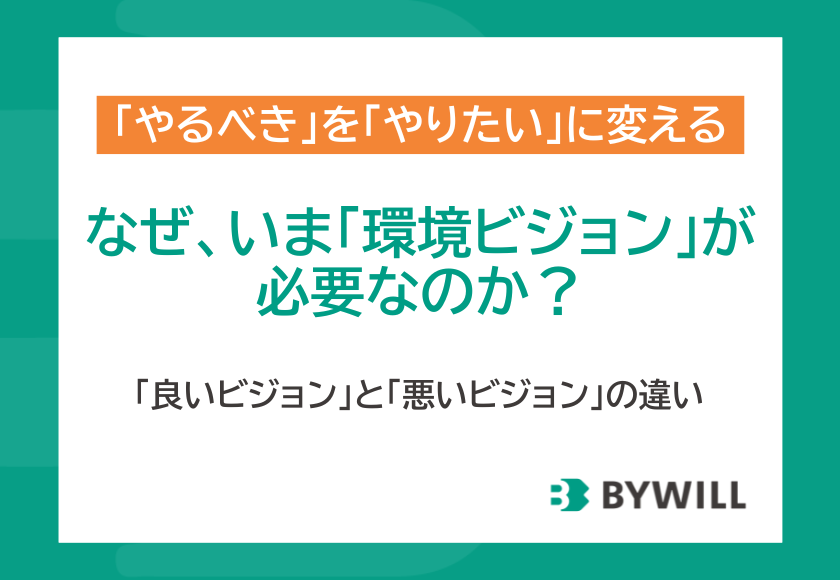この記事は、2020年5月14日(木)に開催したウェビナー『ブランドKPIマネジメント』で頂いた質問に対する回答をまとめたものです。
リモート下の組織課題がテーマだった前回に引き続き、過去満足度No.1である『ブランドKPIマネジメント』セミナーのQ&Aの内容を一部抜粋して公開致します。特に、“KPIマネジメントに取り組みたいが指標の決め方が分からない”、“ブランド戦略と現場の行動が噛み合っていない”といったお悩みがある方には、参考になるかと思いますのでぜひご覧ください。
セミナーに参加されていない方には分かりにくい箇所もあるかと思いますが、
詳細をご希望の方は下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。
内容に関するお問い合わせはこちらから
1. 獲得したいブランドイメージの定量的な目標設定について伺いたいです。
ゴールに対して獲得したいイメージの絞り込みまではできるのですが、アンケート調査などを通して具体的に何%獲得すればよいのか、の目標についてはどのように設定するべきでしょうか?
認知率やリピート率はゴールから逆算して設定しやすいのですが…
指標の目標値設定も場合によりけりで一概には言えませんが、過去の例では、
・ベンチマーク競合が明確に存在する場合は、その競合以上の水準に設定する
・「イメージシェア」という考え方に沿って、ランチェスターの法則(クープマンモデル)を応用して設定する
・経年分析によって、ゴールとの相関係数を割り出して設定する
(KPIが◎ポイント上がれば、ゴールとなる目標は×ポイント上がる)
などが有効でした。
2. ブランドの再構築ステージで、ブランドがすでに陳腐化してしまっている場合に“原点に帰って磨き直しする”か、“現在のターゲットにフィットした新たなアクションを起こす”といったアクションが考えられ、ケースバイケースだと思いますが、どのように決めるべきでしょうか。
最初に考えるべきは、「陳腐化」というのが何を指すのかですかね。
再構築ステージに立っているぐらいなので、ブランドが世の中に広く一般に浸透し切ったという意味で陳腐化しているのか、ロイヤル顧客の一部の人たちにとって、最初は尖っていたが最近は他と変わらないと思われ始めてきたという話なのか。
総じて売上が伸び悩んでいる場合にブランドを再構築しましょうという話になることが多いと思いますが、本当にそのブランドが「陳腐化」しているのかは冷静に見なければいけないと思います。
ずっと同じやり方でやってきて下がってきてしまった、でも実は同じターゲットに対してマーケティング4Pの見直しによって伸びるということもありますし、やっぱりターゲットがずれてきましたね、ということも往々にしてあります。
感覚的には、立ち上げて十年二十年経っているブランドは、これまで試行錯誤してきた結果としてそのブランドが本来持っていた価値が希薄化してしまっていることもあり、その場合は原点に立ち返ることも必要です。
いずれにしても、「本当にブランド価値が陳腐化しているのか?」「陳腐化しているとしたら、誰にとってか?」「元々の価値は何か?」を考えるべきだと思います。
3. ブランディングを進めていく際に、社内的には定量的なKPIでコントロールしていくことが大事なのはよくわかりましたが…活動に対して「褒めてもらう」ことが、その推進力になる気がします。
社内で褒め合うツールを入れたり、お客様からのお褒めのことばを共有する…等も重要だと思いますが、いかがでしょうか?
企業活動として社員に何かをして欲しいというメッセージを発する以上は、個人の具体的な業務や評価の仕組みに落とし込むことなく長期的に行動を継続するのは難しいと思っています。
なので「褒め合う」ということは我々も重視していて、表彰式をブランドの観点で再設計するということも行います。
また、お客様からのお褒めの言葉に関しては、「ブランディング活動で実施したことが、お客様にベネフィットとしてこう伝わり、印象がこう変わりました」ということをよく社内にフィードバックします。
対外的な活動・施策に対する生の声が、社内に跳ね返ってくるように設計するというのは大切です。
さらに、自分たちの感覚とお客様が思っていることとのギャップを認識するということも有効です。
我々がよく行うのは、従業員の方に「お客様からはどんなイメージ・ベネフィットだと思われているでしょうか?」という調査をして、同じ内容を実際のお客様にも調査します。
すると、自分たちとお客様との認識ギャップが明らかになるのですが、自分たちが想像もしていなかったところでお客さまから高い評価を得ていたりすることもあります。
そういったことも、ブランディングの活動を一貫・継続していく上では良い刺激になっていると思います。
4. 一貫したブランディングのためには”社員の行動”が肝というお話でしたが、社員の行動に一貫性を持たせるために、効果的な施策例がありましたらご教示いただきたいです。
企業規模や組織体制、企業風土などによってバリエーションが多く、やるべきことの優先順位付けが難しいですが、我々はよく「やるべき(MUST)」「やりたい(WILL)」「やれそう(CAN)」の全てが一定以上の水準に達していないと一貫・継続した行動は難しい、とお伝えしております。
具体的には、インナーブランディング活動として、
・「やりたい」:共有会、ブランドムービー、表彰
・「やらなきゃ」:目標管理・評価
・「やれそう」:ワークショップや研修
などの施策を、各社様の状況に合わせてご支援させて頂くことが多いです。
5. KPIを達成するための部署別アクションテーマを設定して行動に移すことはとても重要ですが、ハードルも高い気がします。
設定の際は、部署の自主性に任せたほうがいいのでしょうか。
組織体制にも関係しており、ブランドマネジャー制をとっている会社であれば、ブランドマネジャーが有機的にブランドの視点と業績の視点をリンクさせながらKPIマネジメントを推進しやすいと考えます。
ただし、ブランドマネジャー制ではない会社の場合は、ブランディングの目的や業績向上との接続感を各部署の方が認識しているかどうか。
認識しているのであれば現場に任せたほうが走るなという感覚です。
そうでない場合、よくありがちなのは、各部署のやりたいことをブランドに無理やり意味づけてしまったり、KPIが形骸化してしまうことです。
前提として「やりたい・やらなきゃ・やれそう」というフレームワークがありましたが、社内各部署の方が一定以上、ブランディングを「やるべき」だという認識と「やりたい」という意思、「やれそう」という実現可能性を感じられていることが、自主性に任せても成功するかどうかのポイントだと思います。
セミナーQ&Aは以上となります。
ブランドKPIマネジメントに関して、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちら