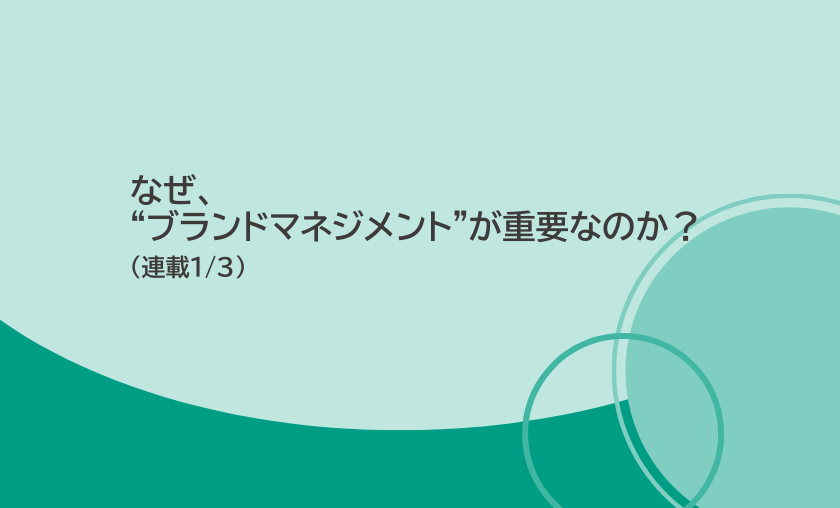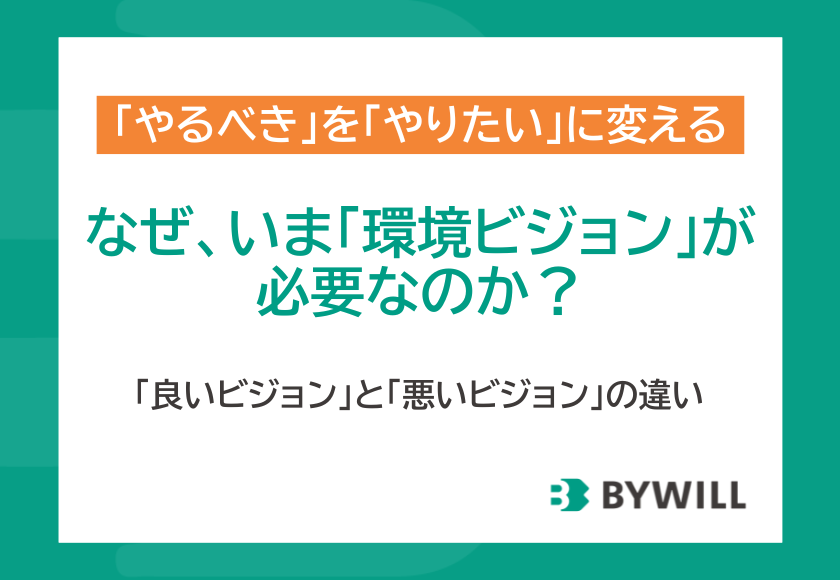皆さん、こんにちは。伊佐です。
今日は、最近お客様からよくご相談をいただく事柄について、お伝えしたいと思います。
テーマはズバリ、『ブランドマネジメント』。このコラムをご覧になっている方々にとっては、非常に耳慣れたワードだと思います。ブランド力を高めていくためには、「ブランドマネジメント」が重要であることも、同様にご存じのはず。しかし、改めて、どれがどういったことなのか、考えてみたことがありますか?
辞書的な意味は様々な書かれ方をしていますが、総じて言えば、ブランドエクイティを高めるための継続的な活動。これだけ見て、「じゃあ、今日からブランドマネジメントを実践しよう」と行動に移せる人はあまり居ないはずです。そして、それは今このコラムを読んでくださっているあなただけではありません(安心してください!笑)。
今回を含めた三回にわたるコラムでは、この知っているようで意外と分かりにくい「ブランドマネジメント」に関する内容を皆様にお届けしたいと思います!
以下、各回の内容です。
第一回:なぜ、「ブランドマネジメント」が重要なのか?(重要性)
第二回:どのように「ブランドマネジメント」を組み立てるか?(設計の考え方)
第三回:どうすれば、有効な「ブランドマネジメント」が行えるか?(運用のポイント)
昨今、様々なブランドが興隆する中で、ブランド強化を図るべくブランドマネジメントに力を入れる企業は多くなっていますが、
中には途中で頓挫する例も少なくありません。(これは「ブランド」を「理念」「ミッション」「ビジョン」「WAY」「バリュー(ズ)」などに置き換えても同様のことが言えます)
そして、そのような企業様からよくお聞きする次のような声からは、ブランディングを企業活動として継続的に取り組んでいくための3つの壁が透けて見えます。
- ブランドという概念自体がそもそも曖昧で捉えにくく、とっつきにくい
➔“理解・共感の壁” - ブランディングの成果が出ているのかが分からない
➔“可視化・共有化の壁” - 日々の業務レベルで、ブランドの落とし込みができない
➔“業務接続の壁”
ブランドマネジメントが、「ブランドエクイティを高めていくための継続的な活動」であるならば、人の集合体である企業が「継続的に」取り組んでいくために、これらの壁がボトルネックになってしまうことは当然とも言えます。
なぜなら、人は、可視化・共有化された目標やあるべき姿に対し、理解・共感(あるいは納得)し、自分の業務と紐づけられてはじめて、継続的に動き続けることができるからです。
では、これらの3つの壁を乗り越えるために、なにが必要なのでしょうか?
.jpg)
結論から言うと、ブランドという目に見えない、曖昧なものを、目に見えない状態のままで扱わないことです。
つまり、ブランドを可視化して、日々の業務レベルで身近な目標に落とし込みさえすれば、少なくとも前述の3つの壁を乗り越えるきっかけをつくることができます。
では、具体的にどのようにブランドを「可視化し、日々の業務レベルで身近な目標に落とし込む」のでしょうか?
以下の3つのポイントに沿って紹介します。
①定量・定性の両面からブランドを規定
②社外・社内の両方の視点を持つ
③目標・指標をアクションプランとして具体化する(業務接続)
まず、①に関してですが、ブランドマネジメントを行う際には、ブランドのあるべき姿や目標を描くことが必要です。
これがなければそもそもブランドは、ただのラベル・名称にしかなりません。皆さんも、「そんなの当たり前」と感じる方が多いのではないでしょうか?
しかし実は、これまで私たちがブランディングのお手伝いをしていく中で、
- ブランドの定性目標(ステートメントやキャッチコピーなど)はあるが、定量目標はない
- そもそも、自分たちが何故、今、何を求めて「ブランディング」に注力すべきなのかが明確に示されていない/経営層と共通認識化されていない
- ブランドをどのように育てていくのか、マイルストーン(途中目標やステップ)がない
例えば、定量的な目標だけを設定した場合、何のためにその数字の達成を目指しているのか?達成した時は自分たちのブランドがどうなっているのか?があやふやになってしまい、ブランドを体現する社員のモチベーションに支障を来したり、行動のベクトルが揃わなかったりします。
また、定性的な目標だけを設定したり、マイルストーンが設定されていない場合は、ブランドが本当に確立されていっているのかどうかを客観視することができず、ブランディング のPDCAを回すことができません。
したがって、ブランド目標は定量面・定性面の双方から規定し、自社のブランディング活動がどこに向かって行われているかを明確にし、“ブレ”をなくすべくPDCAを回していくことが重要です。
.jpg)
次に、②に関してですが、ブランドマネジメントの際には、社外・社内両方の視点を持つことが必要です。
よくある例としては、ブランドが浸透しているかどうかを見極める際に、社外にばかり目が行き、社内におけるブランド浸透具合は確認しないというパターンです。
一見、社外視点でブランド浸透具合を確認すれば良さそうですが、企業のブランド価値は社員ひとりひとりの行動を通じてインターナルに発揮・伝播されるため、社内でブランドが浸透していない場合、ブランディングに一貫性と継続性を持たせることは難しくなります。
よって、ブランドマネジメントは社外・社内双方の視点で行うことが大切です。
最後に、③に関してですが、ブランド目標は掲げて終わるのではなく、日々の業務、社員のアクションにまで落とし込まなければなりません。多くの社員にとっては、そうすることではじめて、曖昧な概念でしかなかった「ブランド」が、「業務」=「自分たちの役割」として認識されるようになります。
以上、ブランドマネジメントのポイントを簡単に紹介してきましたが、こうして見ると、「ブランドマネジメント」は、言ってみれば、一般的な中計とは時間軸の違う「中長期経営計画」のようなもの、と言えるのかもしれません。
(一般的な中計が、企業活動の軸であるとすれば、ブランドマネジメントの形がそれに似たものになることも、当然なのかもしれませんね)
本日は、入り口としての概論を書きましたが、いかがでしたか?
次回からは、これらのポイントに注意しながら、どのようにブランドマネジメントの「設計」を行えばよいのかついて書きたいと思います!
是非ご覧になっていただけると幸いです。
▼次回はこちら
第二回:どのように「ブランドマネジメント」を組み立てるか?(設計の考え方)
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング