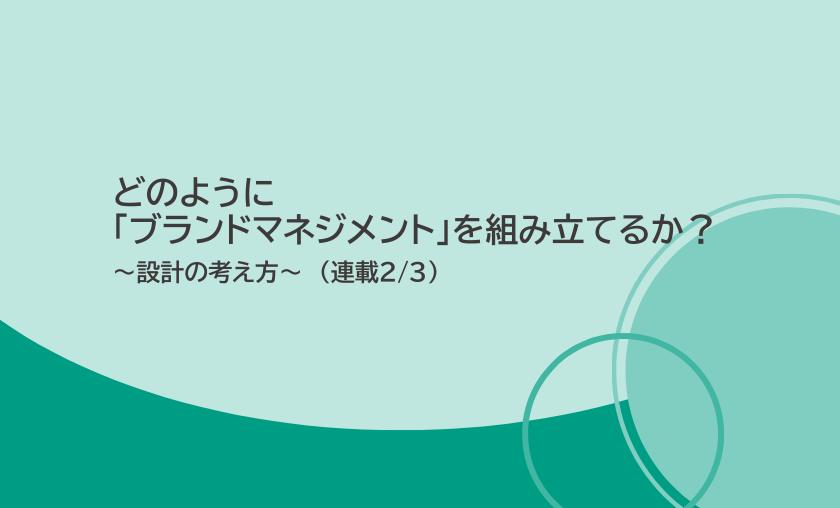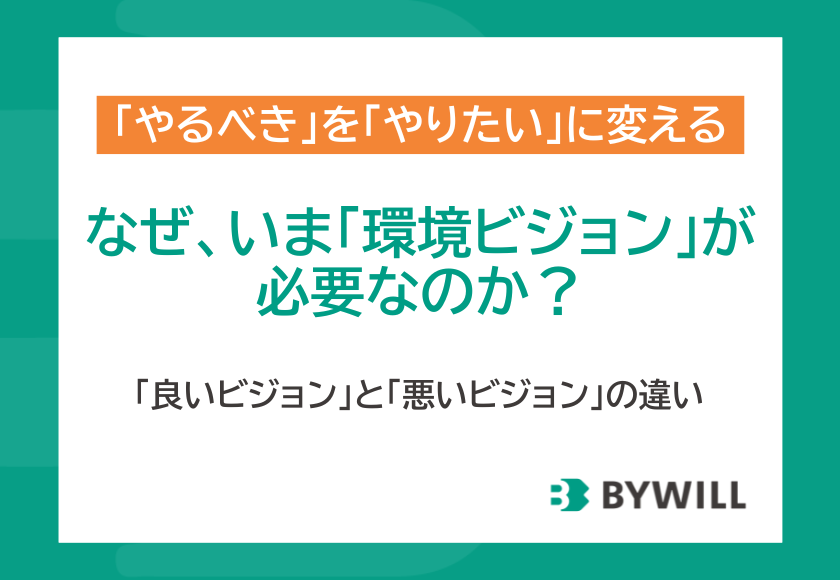皆さん、こんにちは。伊佐です。
前回に引き続き、今回も「ブランドマネジメント」についてコラムをお届けしたいと思います。今回のテーマは、「どのようにブランドマネジメントをするか(設計の考え方)」についてです。
※この連載では、『ブランドマネジメント』について、3回にわたってコラムをお届けしており今回は2回目です。
以下各回の内容です。
第一回:なぜ、「ブランドマネジメント」が重要なのか?(重要性)
第二回:どのように「ブランドマネジメント」を組み立てるか?(設計の考え方)※今回
第三回:どうすれば、有効な「ブランドマネジメント」が行えるか?(運用のポイント)
まず、前回のコラムを振り返ります。
ブランドを強くするためには、一貫性、継続性を持った取組・施策を通じて、顧客の記憶に明確なイメージやベネフィットを蓄積していくことが必要です。しかしながら実際には、ブランディング活動をする中で下記のような『壁』に直面するという声をよくお聞きします。
- 「ブランドという概念がそもそも捉えにくい」
→理解・共感の壁 - 「成果が出ているか分からない」
→可視化・共有化の壁 - 「業務レベルで落とし込みができない」
→業務接続の壁
「ブランドマネジメント」が必要なのは、上記の『壁』を乗り越えて「一貫性」と「継続性」を保ったブランディングをしていくためです。「ブランド」という目に見えない概念だからこそ、ブランドの目標を明確化し、指標化し、目標に対する現在地と課題を可視化し、PDCAを回しながら「マネジメント」をしていく必要があります。
しかしながら、「ブランドマネジメント」という概念の重要性やポイントは理解していても、いざ、自分の所属する企業で継続的に取り組んで成果を出そうとなると、苦戦される方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は「ブランドマネジメント」に着手する際に、どのようにブランドマネジメントを設計したら良いのか、ポイントをかいつまんで、前回のコラムよりも少し具体的なお話しができればと思います。
最初に、ブランドマネジメントに取り組むために重要なことは、「企業活動の『仕組み』をブランドと紐づけて構築・運用すること」です。
企業活動の『仕組み』にブランドの観点を取り入れることで、ベクトルをずらさず、企業全体として一貫性・継続性を持ったブランディングが可能となります。
企業活動の『仕組み』について、組織の『仕組み』、業務の『仕組み』、組織体制の3つの観点から考えてみます。
1. 組織の『仕組み』に落とし込む
組織の仕組みには人事制度(等級・評価・報酬)、採用、育成、その他表彰制度のようなサブルールなどがあります(というよりは、我々はこれを、「組織の仕組み」と便宜的に呼んでいます。後の、「業務の仕組み」と区別するためです)。
組織の仕組みを変更することにはかなりのパワーがかかったり、各部署との調整・擦り合わせなどが大変、ということで、ブランドコンセプトを浸透させることを目的に、人事制度や育成体系まで踏み込むことには抵抗のある担当者が多いようです。しかし、ブランドコンセプトの実現につながるように入念に設計された人事制度、中でも、目標設定(個人)や評価への落とし込みこそが、社員に対するダイレクトなメッセージツールになります。
例えば、等級定義(日本企業の多くは役割期待・職能定義)の内容がブランドコンセプトやブランド目標としっかりと紐づけられていれば、社員からは「当たり前にやるべきこと」、「自分にもメリットがあること」として認識されます。すると、社員もインセンティブが働く(ちゃんとブランドに沿った判断・行動によって成果を出せば評価が上がる)ため、日々の業務でもブランドを意識するようになり、業務での意識や行動が自然とブランド目標を体現したものに変わることが期待できます。
ただし、ブランドコンセプトやブランドビジョンなど、ブランドとしての目標やゴールに当たるものを、ダイレクトにそのまま制度に落とし込むのは難しい側面があります。
例えば弊社フォワード(現:バイウィル)の例では、「好きといえるブランドがある。そのよろこびを、人に、社会に。」をミッションとしています(ご興味いただければ、是非その意味合いなどはこちらからご覧ください)が、このミッションをそのまま目標設定や評価に反映させるのは難しいですね。
そこで弊社では、ブランドコンセプトやミッション・ビジョンと、「組織の仕組み」の間に、中間概念としてクレドやバリューを作ることを推奨しています。クレドやバリューは、「社員はどんなことをしないといけないのか」「どんな価値観、判断基準、振る舞いをすべきなのか」を規定するものなので、評価に落とし込むには相性が良いためです。
先ほどの弊社フォワード(現:バイウィル)を例にとると、
ミッション
「好きといえるブランドがある。そのよろこびを、人に、社会に。」
バリュー
- 「コト」向き
どんなときもブレることなく、解決すべき課題や達成すべき目標など、成し遂げたい「コト」にフォーカスしよう。 - 圧倒的繊細
人にも、仕事にも、細部まで思いを馳せ、「圧倒的」な丁寧さを大切にしよう。 - プレゼントマインド
大切な人に渡すプレゼントを考えるときのように、相手の喜びを創り出すことにワクワクしよう。 - ロジエモ
正論だけで人は動かない。相手の行動を促すために、「ロジカル」と「エモーショナル」の両方を大切にしよう。 - 情報呼吸
情報へのアンテナはいつだって広く、高く。呼吸をするように、当たり前のように情報のINPUTとOUTPUTを繰り返そう。 - オプションX
考え方や意見が対立したときでも、諦めも妥協もなく双方の目的を果たせる「オプションX」がないか、まず自分から考えよう。 - 自利他
利他の精神を心の真ん中に。そのうえで堂々と自利を追い求めよう。
という規定があり、ミッションに比べ、バリューは人の価値観・判断軸・大事にすべきことをダイレクトに表現してあるため、目標設定や評価に反映させやすく、実際そのように運用されています。そうすることで、社員は「フォワード(現:バイウィル)の提供すべき価値を体現する」ことが評価として報いられ、また、目標設定(弊社では面談を実施しています)の際には、自らの頭で「バリューを体現する(≒ミッションを実現するための行動をする)とは、自分にとってどういうことか?を考え、話し合うという機会を得られます。この習慣化が、組織の仕組みをブランド軸で整備していくメリットです。
加えて、人事制度(に限らず、多くの社内ルール)は作ることよりも運用することの方が何倍も難しく、運用を成功させることが次の課題となります。特にブランドコンセプトを広めていく役割を担う管理職層は、「なぜブランド目標に紐づいた人事制度を運用することが大事なのか」等、運用のポイントをブランド目線で理解することが大事になります。
ブランド目標が社員に浸透しきらない例としてよくお聞きするのが、ブランド目標やコンセプトを策定したものの、それを広報やワークショップなど、単発イベントで発信して終わってしまっていることが挙げられます。時間をかけて経営層で策定したブランド目標やブランドビジョンが、時間が経つと形骸化してしまい、社員から特に意識されなくなっているというケースがあり、これは非常にもったいないことです。
2. 業務の仕組みに落とし込む
ブランドコンセプトやブランドビジョンを各部署の目標管理やアクションプランに反映させることもブランドを浸透させていく上では非常に大きな効果があります。
企業のブランド目標を部門や部署で持つべき目標にブレークダウンした上で、各部門・部署で求められるアクションテーマとして設定、落とし込みを行うことで、「組織の仕組み」と併せて、更に「やって当たり前」のものとして認識してもらうことが期待できます。部門・部署の目標やアクションとして落とし込まれれば、それは直接的・間接的にグループやチーム、そして個人の「業務」として落とし込まれていく構造ができます。多くの社員にとっては、それでようやく「やって当たり前の業務の一つ」としてブランドを捉えることができるようになります。
多くの企業では、ブランドコンセプトやブランドビジョンをつくった後、「何故今ブランドが必要なのか?」「何故このブランドコンセプト・ブランドビジョンなのか?」など、目的や背景を理解できれば行動できるはず、という考えに基づき、共有会やワークショップ、あるいはブランドブックやカードなどのツール制作を行うことがセオリーです。
このアプローチは、とても重要なものですが、部門・部署の目標やアクションテーマにブランドが落とし込まれていない状態では、残念ながら効果はかなり限定的になりがちです。現実的には、社員のほとんどが普段の業務でブランドコンセプトを意識することは少ないため、各部門別においてブランド目標を定性・定量的に落としんだ上で、注力すべきアクションを指標化し、中長期のブランドロードマップを描いておくことが有効でしょう。
さらに言えば、個人別のアクションテーマや目標設定にも、ブランド目標を反映させることで「やって当たり前」「やったら良いことがある」と思ってもらう状態に持っていくのが理想的です。
ブランド目標やブランド戦略という抽象的な概念を「実践」に落とし込むためには、企業のブランド目標やブランド戦略を、部署別の目標やアクションテーマに落とし込むことで、「自分事化」してもらう「業務の仕組み」が求められます。
3. 組織体制
ブランドコンセプトの社内浸透は、上記2つの観点から考えることが重要ですが、「運用のための組織体制」についても抑えておく必要があります。業界特性、事業や組織の規模、フェーズ、ビジネスモデル、組織文化によって最適な体制は変わってきますが、一般的に、ブランドマネジメントを上手く回していくための組織体制には、大きく分けて2つのパターンがあります。

中央統括型は、ブランドマネジメントを専門に行う部署を経営層の直下に設け、各部門・部署のブランド規定やブランド目標の管理・推進を行う体制のことです。ブランド目標が各部門・部署内での部分最適なマネジメントにならないように、各部門・部署のブランドマネジメントを一括で管理して方向性を定めます。それぞれのパラダイムや利害関係に左右されず、ブランドの視点を一貫させやすいのがメリットですが、逆に、部門・部署ごとのパラダイムと乖離することがしばしばあるため、コンフリクトが起こりやすいのが難点です。
実際には、こうした体制は組まれているものの、ブランドマネジメントのための具体的な権限は与えられておらず、有名無実化しやすい、というのも、多くの企業様の悩みごとのようです。
一方、ライン統括型は、各部門・部署でブランドマネジメントの役割を担う担当者を決め、その人に各部門・部署内のブランドマネジメントの責任を付与します。中央統合型に比べ、部門・部署内にブランドマネジメント機能が包含されるので、コンフリクトは起こりにくく、部門・部署の成果目標とブランドの視点を総合的にマネジメントしやすい、というメリットがあります。
ただし、往々にして、部門・部署の売り上げや利益などの主要指標(目標)の方が上位に置かれることが多い結果、ブランド視点が弱くなりがち、という難点があります。
こちらも実際には、意思決定プロセスの中に、ブランド視点からの統制を図る仕掛けがされていないと、意図されたようなブランドマネジメントが機能しない、というお声をよく聞きます。
どちらも一長一短ですが、共通しているのは、「役割規定」「責任範囲」「意思決定プロセス」を明確化しないと、体制だけを構築してもブランドマネジメントは機能しない、ということです。状況や組織風土、ブランドへの社員の共感度・浸透度などを踏まえて、適切な組織体制を組むことが大切になります。
以上、ブランドマネジメントの設計の観点について、①組織の『仕組み』、②業務の『仕組み』、③組織体制、の3つの観点を紹介しましたが、今回のテーマである『設計のポイント』という意味では、これらの3つの観点を「あらかじめ、統合的に描く」ということです。そして同時に、高い効果が見込めるところから、着実に変えていくのも重要です。
例えば、よくありがちなブランドマネジメントの設計として、
① ブランドコンセプトやビジョンを描いたら、その浸透を特定に部署にミッションとして落として終わり。そのための新体制をつくって終わり
➔結果として、①②が運用されない
② ブランドコンセプトやビジョンを描いた後は、①のみ着手(多くは、表彰制度・ワークショップ・ツール制作と社内共有のみ)して、②③には踏み込まない
➔結果として、「業務接続の壁」を超えられない
③ ブランドコンセプトやビジョンを②に落とし込んだものの、①には踏み込まない、あるいは、③で権限設定はされない
➔結果として、「理解・共感の壁」は超えられない
すべてを一気に変えることは、時として大きなハレーションを起こすことがありますが、まずは理想像として、上記のような状況に陥らないように、①②③を俯瞰した設計をしていけるとよいのではないでしょうか。
第二回の記事は以上です。
▼次回はこちら
第三回:どうすれば、有効な「ブランドマネジメント」が行えるか?(運用のポイント)
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング