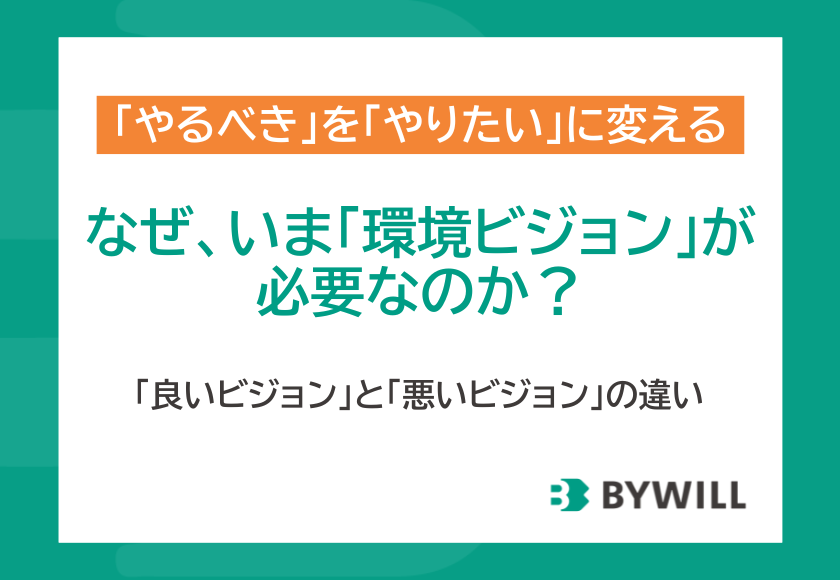大手ベビー用品メーカーとして圧倒的シェアを誇るピジョン株式会社。しかし後発で参入したベビーカー市場においては、なかなかシェアを伸ばせずにいた。2014年ベビーカー市場は大手2社が市場の9割のシェアを占める寡占状態であり、ピジョン株式会社はこの2社が作るゲームルールの中で、市場の穴を見つけることができず苦戦。今回は、そこから2015年1月発売の新商品「ランフィ」を機にたった4年でシェアを3.0%→30.3%まで伸ばした具体的な取り組みを、「開発期」「立上期」「拡大期」の3フェーズにわけて、担当者からリアルな体験談と共にご紹介頂いた。
【ピジョン株式会社HP】https://www.pigeon.co.jp/
成熟市場で圧倒的にシェアを伸ばすピジョン株式会社から学ぶ。市場に風穴を空けるブランド戦略とは?(前編:開発期)
成熟市場で圧倒的にシェアを伸ばすピジョン株式会社から学ぶ。市場に風穴を空けるブランド戦略とは?(中編:立上期)
機能的価値の訴求から、情緒的価値の訴求へ
伊佐:ありがとうございます。最後に、シェア30%まで伸ばした拡大期のお話を伺えますか。
小笠原氏:初代「ランフィ」を出してから、シェアが12%くらいまでは伸びました。しかし、それだけではベビーカーを知っている大手2社には敵わず、二の手三の手を出していく必要がありました。そこで、訴求方法を変更していきました。大手2社は機能的価値の訴求をされていました。そのため、私たちは機能的価値の訴求でなく情緒的価値の訴求を進めていきました。
最初は「16.5センチのシングルタイヤで段差を乗り越えることができます」と言っていましたが、「スイスイと押しやすい」という伝え方に変えました。そして、最終的には「赤ちゃんがお出掛けしたくなるようなベビーカーです」という情緒的な訴求に変えていきました。これがお客様に響くのかどうか、正直まだ結果は出てないですが、少なくとも直近で30%近くまでのシェアは取れています。
他の施策としては、「ランフィ」の派生品の開発や、流通との共同開発商品も発売しました。どちらも成功し、派生品の「ビングル」に関しては、カテゴリ内でシェアが1位の商品となっています。流通との共同開発商品に関しても、インストアシェアがナンバーワンになりました。流通の方と一緒に考えながら商品を開発することで、商品の価値を共有しやすくなり、さらに優先して店頭にも置いてもらえます。われわれも自信を持ってその商品を提供できますし、共同開発商品だからこそ店舗で力を入れて販売してもらえるようにもなりました。
戦略も重要だが、最終的にはマインド。諦めないこと。ブレないこと。
 <ピジョン株式会社 開発本部 ベビー大型商品開発部 チーフマネージャー 小笠原 達一郎氏>
<ピジョン株式会社 開発本部 ベビー大型商品開発部 チーフマネージャー 小笠原 達一郎氏>
小笠原氏:さらに、店舗の前線に立って当社の商品を販売してもらう専任の販売組織を新設しました。家電量販店にいるメーカーの販売員さんのようなイメージです。やはり最後は店舗で売り負けないための施策が必要です。販売組織は約40人いて、みんな僕らのピジョンのベビーカーを好いてくれています。ブランド愛が強いのか、「もっと安くすれば売れるのに」などとは言わず、むしろ安売りすることに反対されたりします。月に一回は一同に集まりミーティングをして彼女達の意見を聞き、「こういう売り方がしたい、こういうツールがあったら売れる」などの要望にはできるだけ答えるようにしています。ファンである彼女たちの熱量が店舗に伝播して、売り場を作ってもらえたりもしました。自分たちのマーケティングのプロセスにいる人たちをしっかり味方にするということが大切だと、最近改めて思います。
すごく泥臭い戦いを現場でしているんですけども、やっぱり最後店頭で競合に負けないためには彼女たちに踏ん張ってもらわなくちゃいけないですし、我々が作った商品の価値をお客様にきっちり伝えていく最前線のメディアだと思っています。どんなにきれいなプロモーションプランやマーケティングプランに見えていたとしても、やっぱり最後まで諦めないこの泥臭さは大切だと思います。
ここで組織の話をさせて頂くと、今年、大型ベビーカーのチームで動画を作りました。制作した動画でお伝えしたかったのは、この事業に関わっている人たちがどういう気持ちでこの商品を送り出しているのかということです。企画・設計・製造から販売員まで様々な人たちの愛がベビーカーには詰まっていて、最後にお客様が笑顔になっていく、というベタベタな内容なんですけど(笑)。動画をつくったのはうちのスタッフなんですが、僕は何も指示をしていません。スタッフたちが相談をし、「今、私たちが伝えたいものはこれです」ということでつくってきた動画です。
伝えたかったのは、戦略的な話はとても重要なんですけど、結局はやる人たちのマインドだなということ。それをこの数年間感じています。そのマインドセットが一番難しいですし、上長の方々はきっとその壁にぶつかるんですが、諦めないでほしい、ブレないでいてほしいと思います。
(動画はこちらからご覧いただけます)
総括:シェアを拡大するためのマーケティング戦略のポイント
 <株式会社フォワード(現:バイウィル) 代表取締役 伊佐 陽介>
<株式会社フォワード(現:バイウィル) 代表取締役 伊佐 陽介>
伊佐:貴重なお話ありがとうございました。最後に私から総括をお伝えさせて頂きたいと思います。
「潜在ニーズ」という言葉自体はよく聞かれますが、大手2社がシェア9割を占めているような成熟市場に風穴を開けていくにはアンチテーゼ性が必要です。先程の話で言うと、「段差でつまずく」というのは不満にはなっていたが、買わない理由にはなっていなかった。ただそこにフォーカスして、「乗っている人はもちろん快適。かつ運転する人も快適でなきゃいけないよね」「ベビーカーってこうやって選ぶんだよ」みたいに、乗り物の原点に立ち返って、アンチテーゼ性を出していったことが大きかったと思います。
根性論だけでブランディングは成功しないです。ですが、意志のないところに成功はない。というのも改めて感じました。小笠原さんをはじめ、開発期や立上期の泥臭いことも含めて意志を固めてやり抜いたチームの人達がいたからこその結果だったのだと思います。あと、巻き込むっていうところですね。身内を巻き込んで、流通を巻き込んで、ファン化していく。近いところからファンを作っていくからこそ、お客様にもファンが増えていったというのを感じました。
あとは、ひと息つかなかったところがすごいところだなと思いまして、市場に存在感が出始めた10数%と、20%届いた段階と、30%に届いた段階で、そうなる手前にその次を既に見据えているっていうところがやっぱりすごい。1つ1つ大きなボトルネックや壁はあるんですが、それを越えることに全力を出しつつも、その次とかさらにその次を見据えている。どこに働き掛けるんだとか、次の基軸を何にするかっていうことをずっと考え続けている。そのことも、一貫性・継続性という意味で重要だったというように思います。
本日持ち帰って頂きたいお話は山ほどありましたが、まとめるとこんなところかなということで、終了とさせて頂きたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング