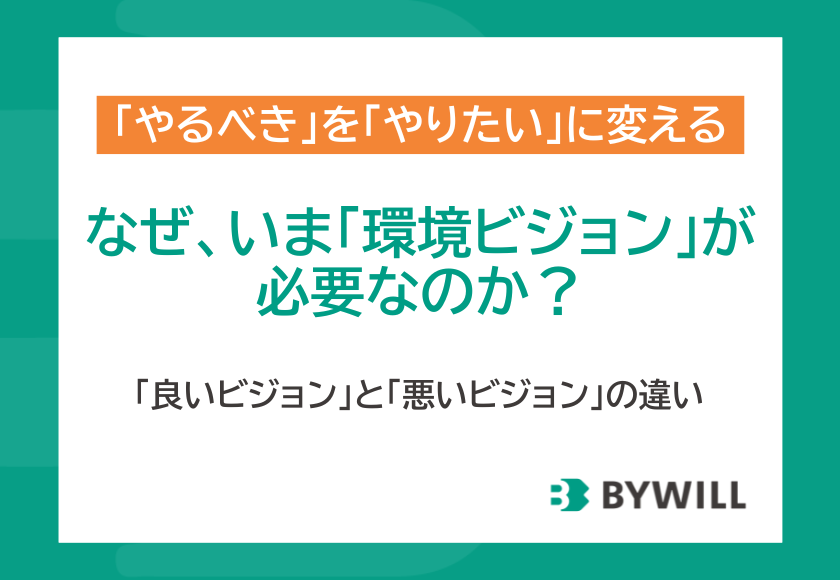オルビスは、化粧品市場にオイルカットという一つのトレンドをつくった‘通販化粧品会社’として知られ、美しいブルーグリーンの コーポレートカラーが施された商品パッケージで、多くのユーザーに支持されてきた。しかし2018年11月、「オルビスユーシリーズ」の発売と同時に、ブランドロゴ・コーポレートカラーも変更。色味を抑えたシックな印象で生まれ変わった。「顧客満足度No.1」という顧客の強い支持と明確な実績がある中でのリブランディングは、なぜ・どのように行われたのか。
 ■プロフィール
■プロフィール
オルビス株式会社
マーケティング戦略部 課長 松枝 奏輔氏 (写真左)
株式会社フォワード(現:バイウィル)
取締役 伊佐 陽介 (写真右)
■イベント実施日
2018年11月5日
「目的が不明確」「一定の売り上げが維持できている」からこそ、進まなかったリブランディング
伊佐陽介(以下、伊佐):本日は、オルビス株式会社から松枝奏輔さんをお迎えして、リブランディングという大きな決断に至った背景など、お聞かせいただきたいと思います。私からは、オルビスさんの事例に加えて、ブランドマネジメントの専門家の観点で、他業界の皆さんにも参考になるお話ができればと思っています。
松枝奏輔氏(以下、松枝氏):オルビスの松枝です、本日はどうぞ宜しくお願いします。10月23日にブランドロゴやコーポレートロゴを一新したところです。私は2004年に入社したのですが、その頃からずっとブランドをどうするのかという議論は続いていました。が、ここ2年ほどでようやく明らかな成果が出てきたと感じています。今はまさにリブランディング期の真っ只中にいますが、本日はその辺りのお話ができればと思っています。

まずブランド再構築期という名前をつけているフェーズですが、ここでの節目は「旧ORBIS=U発売」です。2014年前半、今までになかった商品で、世の中に対してオルビスってこんな会社だと打ち出したつもりでした。しかし、ブランドの新しい顔をつくったつもりが、既存のお客様にしか響かず、外向けには変化したという印象を残すことができませんでした。
模索期はまさにその字の通りで、外向けにどう打ち出していこうかと社内で一生懸命議論をしていた時期だと思います。ちなみに、フォワード(現:バイウィル)さんとお仕事をご一緒させていただくようになったのはこの頃です。
伊佐:ありがとうございます。本日最初に松枝さんにぶつけたい質問は、「なぜリブランディングは『始まらなかった』のか?」。ブランディングというテーマは常に持ち上がっており、それに対する取り組みも様々されてきたとおうかがいしています。しかし、リブランディングの提案は15年で、成果が出始めたという実感が17年。問題意識を感じられてから成果が出る実感を得るまでに、タイムラグがあるんですよね。これはオルビスさんに限ったことではなくて、経営からブランドを強くするという発信があったとしても、二転三転して進まないということはよく耳にすることです。ぜひ、リブランディングが本格的に始まらなかった理由からお聞かせください。

松枝氏:そうですね。経営からはリブランディングにブランド再構築と、様々な名前で新しいことをやるぞという発信はあったのですが、どうなりたいのかという絵がなかった。それが一番のポイントだったと思っています。社員の立場からすると、やることはいいとしても一体どこを目指しているかわからないという状態が続いていて、タイムラグはそういう状態そのものですね。どんなブランドで何を目指すのか、それはなぜかということをはっきりさせないと物事は進まないということを実感しました。
伊佐:なるほど。
松枝氏:それから、リブランディングが始まらなかった要因の一つに、売り上げもあると思います。
2006年から13年頃は、売り上げが停滞していたんですが、見方を変えると、一定の売り上げが保ててはいるとも言えたんですね。
そのため、「今のままでも500億円ほどの売り上げは保てているのに、なぜリブランディングをする必要はあるのか?」「今のままでいいんじゃないのか?」という声も根強くありました。これらの声が、進行を妨げた理由だと思います。
第三勢力台頭により市場のプレゼンスが低下しても、リブランディングは進まなかった
伊佐:内部の声を聞かせていただきましたが、外部環境としてはどのような状況だったのでしょうか。
松枝氏:スキンケア市場を価格帯でセグメントすると、オルビスと同価格帯なのは肌ラボさんやMUJIさんですが、まさにそういった異業種からの参入企業がシェアを獲得している状況もありました。我々をはじめファンケルさんなど通販化粧品会社と呼ばれるグループが苦しんでいる時でもありました。そして、通販化粧品という旧来のくくりの中で比較するのではなく、化粧品という市場で勝たなければという自覚も出てきた頃です。また、資生堂さんやKOSEさんといったいわゆる大手企業のシェアバランスや関係性は変わっていませんでしたが、ナチュラルオーガニック系のジョンマスターオーガニックさんやSABONさんが台頭してきたのもこの頃です。
この第三勢力と言われるブランドに追いやられる形で、通販化粧品会社は、市場のプレゼンスを下げてしまっていました。

伊佐:ありがとうございます。先ほど売り上げが500億円あるという意識が邪魔をしたというお話もありましたが、危機感が足りないという声は、ブランディングのプロジェクトを進める中でよく聞かれるものです。じゃあ、健全な危機感はどうやったら生まれるのかといえば、マクロトレンドから見て市場はどう変化しているのかという情報開示をするというアプローチが一般的です。
オルビスさんの場合は、こういった理屈から考えても非常に正しい課題感を社内で提示されていたにもかかわらず、すぐにはリブランディングが進んで行かなかった理由はどう捉えていらっしゃいますか。
松枝氏:個人レベルでは「まずい」という危機感はあったと思いますが、「でも売れてるよね」と捉えている社員も社内には多くいました。そのため、リブランディングを始めるということについて全く意識がかみ合わなかったんです。喧々諤々と議論はしたものの、「このまま放っておいたらまずいんじゃないか」「このままでもいけるじゃないか」と平行線を辿るだけで、あまり意味がなかったですね。物事を進めようという時には、会社の意思決定として「我々はやるんだ」と上層部から降ろさなければいけなかったと、今は思います。
オルビス社も当てはまった、リブランディングを阻む『3つの壁』
伊佐:松枝さんのお話を受けてお伝えしたいこととしては、リブランディングだけではなく、ブランドを始める時もそうだと思いますが、壁が3つあるということです。‘過去慣性の壁’・‘共通認識化の壁’、そして‘体制の壁’です。

売り上げが500億円あるという意識が邪魔をしたというエピソードは、まさに‘過去慣性の壁’ですね。ちなみに‘体制の壁’というのは、‘過去慣性の壁’と‘共通認識化の壁’を乗り越えたとしても出てくるものなんです。これをすれば絶対に解決するという方法が見いだせない壁でもあります。全社として課題認識できたとしても、誰が進めるべきかわからないという声は多く聞かれます。
今回せっかくなので、リブランディングを進めるときのポイントをまとめてみました。

松枝さんのお話に当てはめると、開始のフェーズ。何のために変わらなければいけないのかという目的が曖昧だったことが課題だと言えます。とは言え、ブランドは概念がそもそも曖昧なんです。「ブランティングって採用のためだ」という会社さんもあれば「利益率ですよ」という場合もある。
日本の多くの企業の経営目標というのは、目標化されて部門別のアクションに落とし込まれて、目標設定されているものですが、 ブランドだけは、経営トップが「ブランドを強化せよ」と発信したとしても、実は目標に落ちていないんです。だから、社員から見たらどうしたらいいのかわからない。こういう構図はよくあります。
それから、ブランドはよほど大きなイノベーションを伴わない限り、5年10年をかけてようやく実現するかどうかだという世界だと考えています。成果を長期で描き、責任部署と権限を明確にする。これは絶対にやっていただきたいことです。
ここまでは、リブランディング以前についてお話ししてきましたが、次はなぜ「リブランディングは『うまく進まなかった』のか?」について。ネガティブなタイトルが続きますが、最終的にはポジティブなお話に辿り着きますので、もうしばらくお付き合いください。オルビスさんの場合、なぜ順風満帆には進まなかったのでしょうか。

リブランディング推進のためにブランド戦略室を新設するも、機能せず
松枝氏:新しい商品をリリースしたりサービスを変えたりと、様々取り組んできたのですが、正直なところ、既存のお客様からしか反応がなかったんですね。市場で勝ちたいと改めて投入した商品についても、既存のお客様で売り上げがつくれてしまって。当初は、新規のお客様へと言っていたにもかかわらず、結果的には売れたからいいんじゃないかという展開にもなり、再び市場へ打ち出すということがしにくくなってしまいました。そういった経緯を踏まえて、後ほど遅まきながら、当初言っていたことは実現できていないんじゃないのかと反省したんです。「改めて外で、競争戦略の中で戦わないといけない」という声が上がり出したのが、進み始めるきっかけになったと思います。
また、先ほどの‘体制の課題’にも通じる話だと思いますが、事業部制の組織運営が、リブランディングを推進していく上で足かせになっていたとも思います。通販事業をやっている部署と店舗事業をやっている部署と横並びで、ブランド戦略室を新たに設置したんです。
 この体制のメリットは、チャネルがそのまま事業部になっているので、事業部単位の目標が売り上げ目標となり、立案・運用しやすいことだったと思います。一方でブランドという文脈においては、それぞれにブランド訴求方法が違うなど、ひとつのブランドを扱う会社としてはあり得ない状況を生みやすいということもありました。それを何とかしようということで、ブランド戦略室を設置したんですが、これは上手く機能しませんでした。
この体制のメリットは、チャネルがそのまま事業部になっているので、事業部単位の目標が売り上げ目標となり、立案・運用しやすいことだったと思います。一方でブランドという文脈においては、それぞれにブランド訴求方法が違うなど、ひとつのブランドを扱う会社としてはあり得ない状況を生みやすいということもありました。それを何とかしようということで、ブランド戦略室を設置したんですが、これは上手く機能しませんでした。
伊佐:上手く機能しなかった理由はどのように捉えていますか。
松枝氏:各事業部が事業部目標を追いかけて仕事を進めていますので、急に横から「ブランドとしてはこうあるべきだ」と主張したところで当然、「それでうちの売り上げ目標は達成するんですか」と、現場のメンバーたちは思うわけです。横からブランドを推進しようとしても上手くいかないぞということを、実践ベースで学んでいきました。
ブランド戦略室は1年ほどで解体になってしまったんですが、今振り返ってみれば、立ち上げる際に、もう少し現場をわかっている人をアサインできたら、結果は違っていたのかもしれないと反省しました。現場で目の前の目標を必死で追いかけている人たちにしたら、「なんでお前にそんなこと言われないといけないの?」という気持ちだったと思うんです。表立って喧嘩はしないですが、そういった気持ちは根強くあったと感じています。また、どれだけの権限をブランド戦略室に与えるのかという話を、トップから社員にすべきだったのではないかとも思います。
伊佐:誤解を生まないように補足をしますと、ブランド戦略室がダメということではないんです。事業部のラインから影響力の高い人をブランド戦略室にアサインしていれば成功はしたかもしれないですが、一方で当然ながら、事業部が機能しなくなって目標が達成しなくなるかもしれない。上層部に、「ブランドを本気でやるならばこれくらいのことをやらないといけない、そうでなければ辞めた方がいいですよ」という認識を持っていただくことがスタートだと思っています。
セミナーレポート後編:顧客満足度No.1、オルビスのリブランディングに学ぶ。狙うべきターゲットは誰だったのか?後編
*この記事のサービスについて詳しく知りたい方はこちら>>ブランドコンサルティング