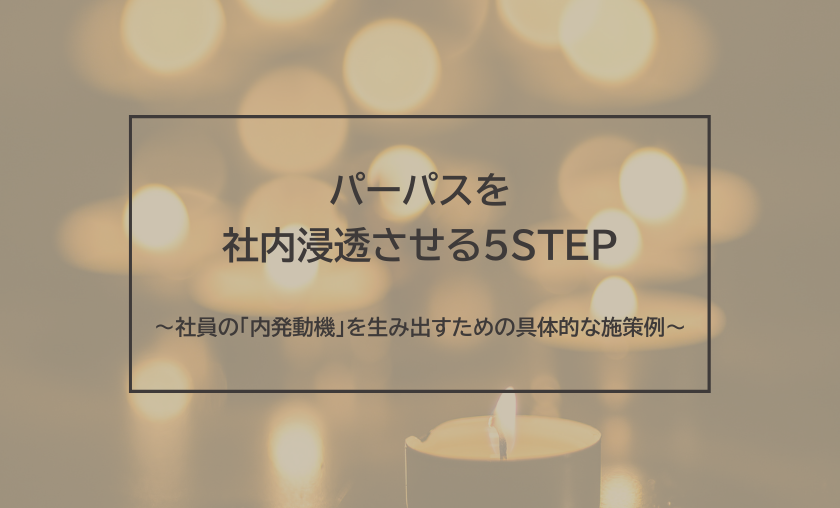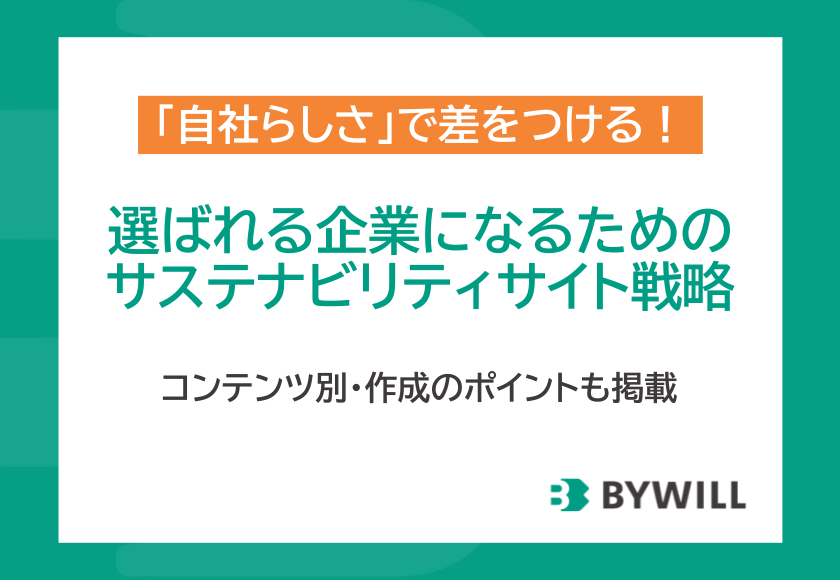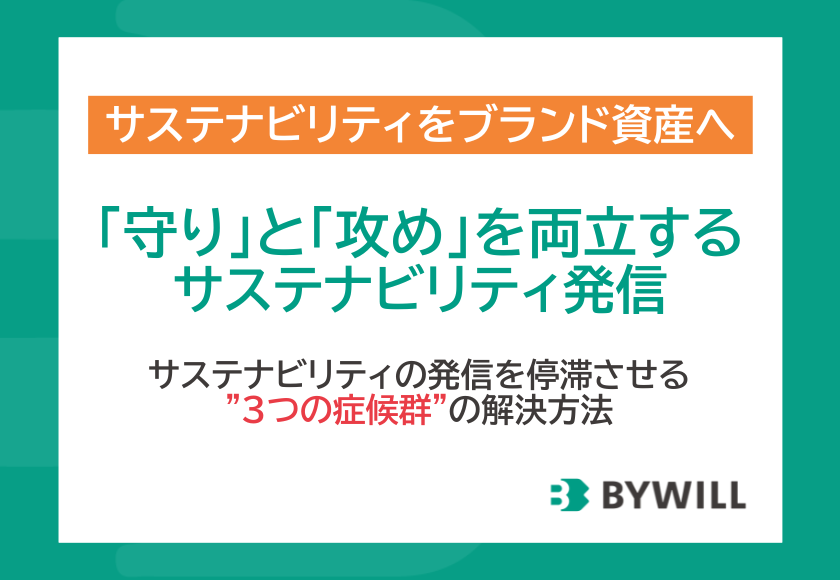前回は、パーパス浸透を成功させるためのポイントと題して、パーパス浸透に取り組む際は、最終ゴールとして「従業員一人ひとりが、企業・ブランドのパーパスを意識した思考・行動を自発的に実践している状態」を目指すべきこと、また浸透活動を始める前に「KPI・アクション」のロードマップを描いておくべきことなどをお伝えしました。
ここからは、パーパス社内浸透の5STEPを一つずつ取り上げて、具体的な施策にまで踏み込んで解説していきます。
▼パーパス策定・浸透に関するサービス紹介はこちら
https://www.bywill.co.jp/services/brand/purpose/
パーパス社内浸透の5STEP
まずパーパス社内浸透の5STEPが下記になります。各STEPについて、施策設計のポイントをお伝えしていきます。
① 認知
② 理解
③ 共感
④ コミットメント
⑤ 自発的な行動
① 認知
まずは、「認知」です。そもそも、パーパスの存在が社員にきちんと認識されていない企業様も見受けられます。これまでも色々な概念が生まれては消えてきた背景がある会社様ほど、一つ一つの概念にコミットしても意味がないと思われがちです。その場合、まずは認知から取り組むことが必要で、ポイントは「視覚化」と「多頻度接触」になります。
やはり難解で冗長な文章だけでは見る人の記憶に残りにくいので、言語化だけで終わらせず、社員が共通のイメージを持ちやすいように「視覚化(ロゴ・キービジュアル・ムービーなど)」を行うこと。また「視覚化」で制作したクリエイティブを活用しながら、日常での接触頻度が高い各種ツールに展開していくことが重要です。
比較的簡単なやり方だと、パーパスそのものやパーパスを簡略化した言葉をロゴに付記する手法があります。新しい概念に興味を持っておらず認知していない社員にとっては、とにかく目に触れる頻度を増やすことが必要です。「今更ポスター?イントラネット?Zoom背景?」などと思われるかもしれません。確かに古典的ではありますが、多頻度で接触させるという意味では有効な手段といえます。キービジュアルや特設サイトを作っただけでは接触頻度が不十分になることが多いので、数を触れさせることを意識しましょう。考え方としては広告と同じで、フリークエンシーが大事だということです。
② 理解
次に、「理解」です。パーパスのような概念は「言葉を覚えた」という表面的な認識に留まり、本質的な理解が深まっていないということもよく起こりがちです。この「理解」を促進するためには、浸透活動の推進側もそれなりのパワーを割く必要があります。施策設計のポイントとしては、「対話」や「学び」の機会を創ることになります。①の「認知」を高め、興味を持ってもらうフェーズよりも難易度が上がるのできちんとパワーを割く覚悟が必要でしょう。
「理解」においては、自社にとっての意味合いを理解してもらうことが肝になります。まず「対話の機会」を創る施策ですと、経営陣が「WHY」「WHAT」「HOW」を語る機会を定期的に設けることが代表的な手法です。我々が以前ご支援した人材系の企業様は、新たに「ミッション・ビジョン」を策定した際、経営陣から新ミッションへの想いを語る場を設けていました。その背景としては、企業統合をして新会社となり、経営陣が別会社の出身だったことです。あえて社員の前で、個々の経営陣が「自分にとってミッションにはこんな意味がある」「ビジョンのここが好きで、こういったこだわりを持って働きたい」といったお話をされました。さらに、社員からの質問に対してその場で経営陣が自分の言葉で返答するパートも設けました。
実際のところ、ここまで力を入れても一度に全員に理解してもらうことは難しいでしょう。しかし、こういった経営層の本気の姿勢に影響を受け、興味を持ち、主体的に理解しようとする人は必ず増えていきます。特に、経営層と直接対話することは大きなきっかけになりますし、そこで影響を受けた人々がその後の浸透活動の起点になることもあります。
次に「学びの機会」について、小林製薬様さんの例を見ていきましょう。「サステナビリティMeetUp!」という取り組みを行っているのですが、ポイントは1か月に1回のペースで定期的に学びの場を提供しているということです。こういった学びの機会を提供するときにありがちなのが、年に1回だけやってそれで終わりになってしまうパターンです。外部講師を招いた勉強会でも、ケースワークを通じて議論を行うのでも形式は問わないのですが、とにかく継続することが重要になります。
③ 共感
次は「共感」です。「やらなきゃ」「やるべき」とは思えているが、それほど前向きに「やりたい」とは思えていないというのもありがちな状態といえます。「共感」を醸成するために、「第三者評価」や「ストーリー化」によってこの壁を超えていきましょう。
まず「第三者評価」に関してですが、一般的にミラー効果と言われるものが有効です。「共感」の壁を超えていくためには、実は対外発信にきちんと取り組むことが重要です。社内に向けた浸透活動だけになると、共感を醸成し切るのが難しいのです。あえて社外へのアプローチも並行させる、そして、社外の好意的な反応や期待値を社員に戻してあげることによって、外部からはこう認知されているのだと社員も強く実感することができます。

社内浸透のみであっても、対話の機会を創る施策を行うと、本当にトップが腹をくくって話せば2割の積極層に火が付きます。しかし、問題は中間の6割の方々です。この6割の人たちが感化されていく流れをつくることが必要です。そしてこの6割の方たちに向けてミラー効果を活用していきます。お客様や取引先、あるいは家族や友人・知人などから「パーパス変えたのですね。御社らしくて良いですね」「CM見たよ!良いことしている会社だね!」などと言われることで、自社のパーパスの良さを再認識し、気持ちが動き、奮い立つイメージです。このように社内からの発信だと響かないですが、外部からのフィードバックなら響く人たちも一定数います。
ミラー効果によって「共感」を生む広報事例~サッポロビール社
サッポロビールでは、社内浸透を図りたいビジョンと行動規範をTVCMという形で表現しました。サッポロビールの社員はこういう価値観でこういう行動をするということを対外的に宣言したという構図になっています。そもそも自社のCMには社員の関心も高いはずですし、社外の方からの反応も産まれていそうです。ミラー効果を生む典型的な例といえるでしょう。
④ コミットメント
最後に「コミットメント」です。方針や考え方に共感はしているが、自分ごととして具体的な一歩が踏み出せるまでの内発的な動機付けができていないという状態もよくあるでしょう。その場合、個人のパーパスと会社のパーパスをすり合わせる機会を設けることが効果的です。
前提として、③の「共感」と④の「コミットメント」は分けずに浸透活動を進められる会社様の方が多いと思いますが、我々としては別のものとして分けた方がいいのではないかと考えています。なぜなら、VUCA時代と言われるように、ますます先行き不透明で未来予測が難しくなっており、また個人の働き方ややりがいが非常に多様化しているからです。このため、組織や個人の内側から湧いてくる、内発的な原動力によってドライブすることの重要性が増しているのです。
そういった文脈において、内発的動機のレベルでのすり合わせは重要であり、内発的動機となる個人のパーパスと会社のパーパスを接続していくことが有効です。具体的には、ビジネスマンとして働く意義や自分の存在意義と、自社の社会的な存在意義をすり合わせる機会を継続的に取っていくというイメージです。実際、「共感」まではしているが「行動」までは踏み出さない人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。我々がよくやる組織調査でも、様々な理念体系の「認知」の割合は8~9割となります。「共感」の割合は、高い会社で6割、低い会社では3割ほどのイメージです。一方、「行動」は1割を超えることが少ないです。ですので「共感」と「行動」の間にもかなりのギャップがあります。そして、そのギャップを超えるためのポイントになるのは、個人のパーパスと会社のパーパスをすり合わせることだと考えています。

定期的に上司と部下の間のコミュニケーションの場を持つという意味では、最低でも3か月に1回程度で1on1をやるべきだと考えています。個人のパーパスと会社のパーパスをすり合わせていくために、「自分が仕事で何をやりたいのか」「どういう姿でありたいか」を上司と会話をする素地があると進めやすいです。また、上司⇔部下の間に前提となる信頼関係がないと、どんな全社施策も響きにくくなってしまいます。まずは、仕事以外の話も含めて定期的に上司と部下が話す習慣を作りましょう。
「MYパーパス」と「SOMPOのパーパス」を重ね合わせる~SOMPO社
「SOMPOのパーパス」実現に向けて取り組む主役はSOMPOグループの社員一人ひとりであるという考えのもと、社員一人ひとりに対して「MYパーパス」に向き合うことを勧めています。「SOMPOのパーパスとMYパーパスのどの部分が共鳴するのか」深く考えて向き合うことで、自律自走した働き方を実践することが「SOMPOのパーパス」の実現に繋がっていくと考えています。
参考:MYパーパス | SOMPOホールディングス
④「コミットメント」の解説は終わりますが、ここまでの浸透活動を通して初めて、最終的なゴールである⑤「自発的な行動」にたどり着くということになります。
パーパス浸透のチェックリスト(印刷してご活用ください)
総括ということで、チェックリストを共有します。上から順に〇・△・×をつけていき、例えば理解の段階で×がついてしまったのであれば、そこにボトルネックがあると判断することができます。今後パーパスの浸透活動を展開していくうえで、自己診断ツールになると思いますので、ぜひ積極的にご活用ください。
最後になりましたが、我々もパーパス浸透の各STEPに対して、様々なソリューションを提供しています。
- 浸透活動を始める前提としてのパーパス策定やサステナビリティ方針~マテリアリティ策定、ロードマップ策定
- 「認知」を高めるための、各種クリエイティブ・ツールの開発
- 「理解」を高めるための、ワークショップや研修の設計・実施
- 「共感」を高めるための、ミラー効果狙いの企画や実行支援、オウンドメディアの支援
- 「コミットメント」を高めるためのワークショップ運営やファシリテーター養成などの支援

まずは、貴社のご状況を踏まえた無料ディスカッションからお気軽にお問い合わせください。
(お問合せはこちら)
最後までお読みいただきありがとうございました。
▼パーパス浸透に関する他の記事を読みたい方はこちら
「パーパス浸透」を成功させるポイントは?~社員の「自発的な行動」を促すために~
▼パーパスの”浸透”に取り組む前に、「パーパスとはそもそも何か」や「パーパスをどのように策定するべきか」に関心がある方は、下記もご覧ください
パーパスとミッション・ビジョンの違い~曖昧になりがちな概念を体系的に整理する~
パーパスを策定するための3STEP~最も重要な「社員視点」を担保するために~
▼パーパス策定・浸透に関するサービス紹介はこちら
https://www.bywill.co.jp/services/brand/purpose/